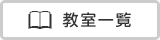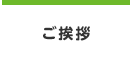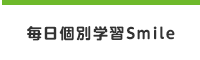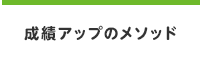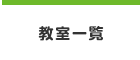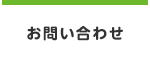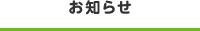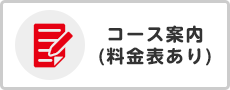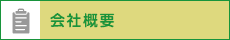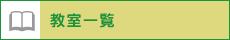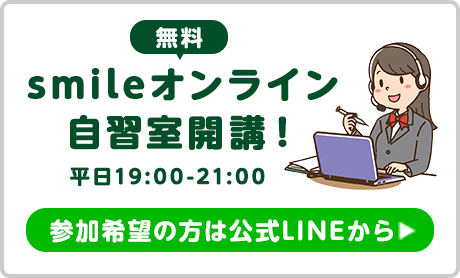月別 アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (14)
- 2025年7月 (30)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
HOME > スクールブログ
スクールブログ
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ43
毎日個別学習Smileが考える「記述が書けない本当の理由」と正しい立て直し方 ―
「選択問題や計算問題はできるのに、記述になると点が取れない」
「何を書けばいいのか分からず、空欄になってしまう」
「答えは分かっているはずなのに、文章にできない」
これは、四日市市・川越町・富洲原エリアでも、毎日個別学習Smileに非常に多く寄せられる保護者様のお悩みです。
多くの保護者様が、この状況に対して ・国語力が足りないのではないか ・語彙力が弱いのではないか ・文章を書くセンスがないのではないか と不安を感じてしまいます。 しかし、結論からはっきりお伝えします。
記述式に弱い原因は、能力や才能の問題ではありません。 ほとんどの場合、「書き方の設計」を正しく教わっていないだけなのです。
なぜ記述式問題が書けなくなるのか?
原因①「何を書けば正解なのか」が分かっていない 記述問題が苦手な子どもの多くは、 ・答えの方向性は分かっている ・本文や資料も読めている にもかかわらず、採点される答えの形を知りません。 記述式は「自由作文」ではありません。 出題者が求めている ・要素 ・語句 ・条件 を満たした型のある答えです。 この前提を知らないままでは、何を書いても不安になります。
原因②「考えを整理する前に書こうとしている」 記述が得意な子は、いきなり書き始めません。 一方、苦手な子ほど 「とりあえず書く」 「思いついたことを並べる」 という状態になります。 ・何について書くのか ・どの順番で書くのか ・どの言葉を必ず入れるのか この整理ができていないと、途中で止まり、結局書けなくなります。
原因③「正解かどうか分からない不安が強い」 記述問題は 「間違えたら恥ずかしい」 「減点されそうで怖い」 という心理的ハードルが非常に高い問題です。 そのため、 ・空欄にする ・極端に短い答えにする ・無難な言葉だけ書く という行動が起こります。 これはやる気不足ではなく、失敗を避ける防衛反応です。
保護者がやってしまいがちなNG対応
ここは非常に重要です。
❌「なんでこれが書けないの?」
❌「説明すればいいだけでしょ」
❌「国語が弱いから仕方ない」
これらの言葉は、 「記述=自分には無理」 という思い込みを強化してしまいます。 結果として、 ・書く前から諦める ・考えることをやめる ・記述問題を避ける という悪循環に入ってしまいます。
記述式が書けるようになる正しいアプローチ(Smile式)
① 記述には「型」があることを教える 毎日個別学習Smileでは、記述問題を 「才能が必要な文章」ではなく **「型に当てはめる作業」**として指導します。 例として、 ・理由を聞かれたら「〜だから」で終わる ・二つ答える問題は「①〜②〜」の構造 ・資料問題は「資料から分かること+結論」 この型を知るだけで、書くハードルは大きく下がります。
② 書く前に「口で説明させる」 いきなり書かせる必要はありません。 まずは、 「この問題、何を聞かれている?」 「答えを一文で言うと?」 と口頭で説明させます。 言葉で説明できた内容は、必ず文章にできます。 書けないのではなく、整理できていないだけなのです。
③ 減点されない書き方を身につける 記述問題で大切なのは、 「きれいな文章」ではありません。 ・聞かれた語句が入っているか ・条件を満たしているか ・ズレたことを書いていないか この3点を満たせば、点数は安定します。
まずは満点を狙わず、部分点を確実に取ることが重要です。
記述式に弱いのは「伸びる直前のサイン」
実は、記述式でつまずくのは ✔ 知識が増えてきた ✔ 考える段階に入ってきた 証拠でもあります。 ここで正しい指導を受けると、 ・思考力 ・表現力 ・応用力 が一気に伸びていきます。
四日市・川越富洲原で記述問題に悩む保護者様へ
毎日個別学習Smileでは、 ・一人ひとりの「書けない原因」を可視化 ・記述問題の型をゼロから指導 ・家庭での声かけ方法まで具体的に共有 しています。 記述が弱いのは、能力不足ではありません。 **「正しい練習順に出会っていないだけ」**です。
まずは、お子さまが 「どこで止まっているのか」 を一緒に整理してみませんか?
▶ 毎日個別学習Smile(四日市校・川越富洲原校)
▶ 無料学習相談 実施中
記述式は、正しく学べば必ず書けるようになります。 そしてその力は、入試・高校・その先まで一生の武器になります。
(毎日個別学習Smile) 2026年2月 2日 13:38
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ42
― 保護者が知っておくべき本当の原因と、今すぐできる正しい対処法 ―
「計算はできるのに、文章題になると急に手が止まる」
「最後まで問題文を読まずに、数字だけ拾って答えてしまう」
「何を聞かれているのか分かっていない気がする」
これは、**毎日個別学習Smile(四日市校・川越富洲原校)**に寄せられる相談の中でも、特に多いお悩みの一つです。
多くの保護者様が、ここで次のように感じてしまいます。
・国語力が足りないのでは?
・読解力が弱いのでは?
・文章を読む集中力がないのでは?
しかし、結論からお伝えします。 文章題を読まない・理解できない原因は、能力や性格の問題ではありません。
多くの場合、「読み方」と「考え方」を正しく教わっていないだけなのです。
なぜ子どもは文章題を読まなくなるのか?
原因①「文章=難しいもの」という思い込み 文章題が苦手な子ほど、問題文を見た瞬間に 「長い」「面倒」「分からなそう」 と無意識にブレーキがかかります。 その結果、 ・数字だけを先に探す ・条件を飛ばす ・自分なりの思い込みで解く という行動につながります。 これは怠けではなく、過去の失敗体験から生まれた防衛反応です。
原因②「何を意識して読めばいいか分かっていない」 学校や家庭では、 「文章題はよく読もう」 「問題文をちゃんと理解しなさい」 と言われがちです。 しかし実際には、 ✔ どこに線を引くのか ✔ 何を丸で囲むのか ✔ どの言葉が一番大事なのか を教わっていない子がほとんどです。 つまり、読めないのではなく、読み方を知らないのです。
原因③「式を立てる前の整理ができていない」 文章題が得意な子は、いきなり計算を始めません。 一方、苦手な子は 「とりあえず計算すれば当たるかも」 と処理を急ぎます。
この差を生むのが、 ・条件整理 ・数量関係の把握 ・ゴールの明確化 です。 これができていないと、どれだけ読んでも理解できません。
家庭でやってはいけないNG対応 ここは非常に重要です。
❌「ちゃんと読めば分かるでしょ」
❌「文章題は何回も出てるのに」
❌「国語ができないからだよ」
これらの言葉は、 「文章題=自分には無理」 という思い込みを強化してしまいます。
結果として、 ・読む前から諦める ・適当に答える ・ますます読まなくなる という悪循環に陥ります。
文章題を理解できるようになる正しいアプローチ(Smile式)
① 文章を「日本語」として読ませない 毎日個別学習Smileでは、文章題を **「日本語の文章」ではなく「情報の集合」**として扱います。 ・数字 ・条件 ・聞かれていること を一つずつ分解し、視覚的に整理します。
② 「線を引く場所」を固定する 文章題が苦手な子ほど、読むたびに見方が変わります。 そこで、 ✔ 数字には必ず線 ✔ 「〜はいくつ」には二重線 ✔ 単位は丸で囲む など、見るポイントを固定します。 これだけで、理解度は大きく変わります。
③ 式より「説明」を言わせる いきなり 「式は?」 と聞くのではなく、 「これは、何が分かっていて、何を求める問題?」 と言葉で説明させることを重視します。 言葉にできた内容は、必ず式にできます。
文章題が解けないのは「伸びる直前のサイン」
実は、文章題につまずき始めるのは ✔ 計算力がある程度ついてきた ✔ 次の思考段階に入ろうとしている 証拠でもあります。
ここで正しく関われば、 ・考える力 ・整理する力 ・応用力 が一気に伸びます。
四日市・川越富洲原で文章題に悩む保護者様へ
毎日個別学習Smileでは、 ・一人ひとりの「つまずきポイント」を可視化 ・文章題の読み方をゼロから指導 ・家庭での声かけまで具体的にサポート しています。 「文章題が苦手」なのではありません。 **「正しい学び方に、まだ出会っていないだけ」**です。
まずは、お子さまが 「どこで止まっているのか」 を一緒に整理してみませんか?
▶ 毎日個別学習Smile(四日市校・川越富洲原校)
▶ 無料学習相談 実施中
文章題は、正しく学べば必ず理解できるようになります。 そしてその先に、考える力と安定した成績が育っていきます。
(毎日個別学習Smile) 2026年1月26日 13:01
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ41
|保護者が知っておくべき本当の原因と正しい対処法
「うちの子、分かっているはずなのにケアレスミスが多くて...」 これは、毎日個別学習Smileに寄せられる保護者相談で最も多い悩みの一つです。 計算ミス、符号ミス、読み落とし、書き間違い。 結果だけを見ると「注意力がない」「集中力がない」と感じてしまいがちですが、実はその捉え方こそが、ミスを減らせない最大の原因です。 結論からお伝えします。 ケアレスミスは性格の問題でも、才能の問題でもありません。 正しい構造理解と学習設計で、確実に減らすことができます。
なぜ子どもはケアレスミスを繰り返すのか?
原因①「頭は理解しているが、処理が追いついていない」 多くの子どもは ・内容は分かっている ・解き方も知っている にもかかわらず、処理スピードと正確性が噛み合っていない状態にあります。 特に小学生〜中学生では 「考える」「書く」「確認する」を同時に行う力がまだ未成熟です。 そのため、分かっているのにミスが出るのはごく自然な発達段階なのです。
原因②「ミスの原因を言語化していない」 多くの家庭学習・学校指導では ×「ミスした」 ○「なぜそのミスが起きたか」 まで掘り下げられていません。 ・途中式を書かなかった ・問題文を最後まで読んでいなかった ・時間を意識しすぎて焦った 原因を言葉にできないミスは、必ず繰り返されます。
原因③「確認のやり方を教わっていない」 「見直ししなさい」と言われても 何をどう見直せばいいのかを教わっていない子が大半です。 ✔ 計算問題は「答え」ではなく「途中式」を見る ✔ 文章題は「聞かれている言葉」に線を引く ✔ 英語は「主語と動詞」を必ず確認する このような具体的な確認ルールがない限り、見直しは機能しません。
ケアレスミスを減らすために、家庭でやってはいけないこと
ここは非常に重要です。
❌「またミスしてるの?」
❌「何回言ったら分かるの?」
❌「注意力が足りない」
これらの言葉は、 子どもに「ミス=能力が低い」という誤認識を植え付けてしまいます。 結果として ・焦りが増える ・確認が雑になる ・さらにミスが増える という悪循環に入ります。
ケアレスミスを減らす正しいアプローチ(Smile式)
① ミスを「分類」する 毎日個別学習Smileでは、ミスを次のように整理します。 ・計算処理ミス ・読み取りミス ・書き写しミス ・思い込みミス ミスは直すものではなく、管理するものです。
② ミス専用ノートは作らない 意外に思われるかもしれませんが、 ミスノートを作らせるほど、ミスは減りません。 重要なのは 「この問題では、どこに注意すれば防げたか」を その場で一言で言語化することです。
③ 「正確さ」を評価する声かけに変える 点数よりも ✔ 途中式が丁寧だった ✔ 見直しができた ✔ 前よりミスが1つ減った プロセスを評価する声かけが、結果的に点数を押し上げます。
ケアレスミスは「伸びる直前のサイン」 これは、長年多くの生徒を見てきた中での確信です。 ✔ 内容理解が進んできた ✔ 問題量に慣れてきた ✔ 次のステージに上がる準備ができている その過程で、一時的にケアレスミスが増えることがあります。 ミスがある=伸びていない、ではありません。 正しく関われば、成績が一気に伸びる直前段階なのです。
四日市・川越富洲原で「ケアレスミスに悩む保護者様へ」
毎日個別学習Smileでは ・一人ひとりのミス傾向を分析 ・家庭学習での声かけまで含めて指導 ・「叱らず、減らす」仕組みづくり を徹底しています。 「ケアレスミスが多いから向いていない」ではなく、 「正しい指導にまだ出会っていないだけ」。 それを、私たちは何度も証明してきました。 まずは、お子さまの「ミスの正体」を一緒に整理してみませんか?
▶ 毎日個別学習Smile(四日市校・川越富洲原校)
▶ 無料学習相談 実施中
ケアレスミスは、正しく向き合えば必ず減らせます。 そしてその先に、「自信」と「安定した成績」が待っています。
(毎日個別学習Smile) 2026年1月19日 13:11
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ40
―毎日個別学習Smileが考える「理社が伸びない本当の理由」と正しい学び直し方―
「テスト前は必死に覚えているのに、すぐ忘れてしまう」 「用語は覚えているはずなのに、応用問題になると解けない」 「理科や社会は暗記科目だから仕方がないと思っている」 三重県四日市市・川越町・富洲原エリアでも、こうした理科・社会の学習に対する悩みは非常に多く寄せられます。 多くの保護者の方が感じているのは、 ・暗記量が多すぎる ・覚えても点数が安定しない ・高校入試や実力テストにつながっていない という不安です。 しかし、まずはっきりお伝えします。 理科・社会が伸びない原因は「暗記していること」そのものではありません。 問題は、暗記だけで学習が完結してしまっていることにあります。
■なぜ理科・社会は「丸暗記」で止まりやすいのか?
① 学校やテストが「用語中心」に見えるから 教科書やワーク、定期テストを見ると、 ・重要語句 ・年号 ・名称 が強調されます。 そのため子どもは、 「とにかく覚えればいい教科」 と誤解しやすくなります。
② 「なぜ?」を考える時間がない 授業の進度は速く、 ・背景 ・理由 ・因果関係 まで丁寧に扱われないことも多いのが現実です。 結果として、 意味を理解する前に覚える という学習が定着してしまいます。
③ 覚えた内容を"使う経験"が少ない 理科・社会は本来、 ・資料を読む ・グラフを分析する ・現象や出来事を説明する 教科です。 しかし、 「書いて覚える」だけで終わると、 知識は点として孤立し、すぐに忘れてしまいます。
④ 成功体験が「一夜漬け」になっている 定期テスト前に詰め込んで点が取れると、 「このやり方でいい」 と子どもは判断します。 しかしこの方法では、 実力テスト・入試問題では通用しません。
■保護者がやってしまいがちなNG対応 ●
「理社は暗記だから我慢しなさい」と言う ● ひたすら用語を書かせる ● 覚えられないことを努力不足と決めつける ● テストの点数だけで評価する これらはすべて、 理科・社会=つらい・つまらない教科 という意識を強めてしまいます。
■家庭でできる「丸暗記から抜け出す」3つのアドバイス
① 用語を「説明させる」習慣をつくる 覚えた用語を、 ・一文で説明できるか ・なぜそうなったのか言えるか を確認してください。 説明できない知識は、 実際には理解できていません。
② 図・流れ・因果関係で整理する 理科・社会は ・流れ ・つながり ・原因と結果 を意識すると、一気に理解が深まります。 ノートに 矢印・簡単な図・時系列 を書くだけでも、暗記の質が変わります。
③ 「覚える前に全体像」をつかむ いきなり用語暗記に入るのではなく、 ・今日は何の話なのか ・何を理解する単元なのか を先に共有してください。 全体像が見えると、 暗記は"意味のある作業"に変わります。
■毎日個別学習Smileが実践している理社指導の設計
毎日個別学習Smileでは、 理科・社会を次のように設計しています。 ● 用語暗記の前に「なぜ・どうして」を確認 ● 図・資料・グラフを必ずセットで扱う ● 説明できるかどうかを重視 ● 定期テスト対策と実力養成を切り分ける ● 小さな理解を積み上げて自信につなげる その結果、 「暗記が楽になった」 「問題文が読めるようになった」 「実力テストで点が落ちにくくなった」 という変化が生まれています。
■まとめ:理科・社会は「理解×暗記」で伸びる 理科・社会は決して、 丸暗記だけで戦う教科ではありません。 ・意味を理解し ・流れをつかみ ・知識を使える形にする この順番を守れば、 暗記は負担ではなく、武器になります。 毎日個別学習Smileは、 「覚えるだけで終わらせない」 「わかるところまで戻れる」 そんな理社指導を大切にしています。 理科・社会が暗記で止まっていると感じた今こそ、 学び方を見直す最適なタイミングです。
(毎日個別学習Smile) 2026年1月12日 17:40
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ39
--毎日個別学習Smileが考える"英語ができない本当の理由"と正しい立て直し方--
「英語が全然読めない」 「アルファベットは書けるけど、単語も文も意味がわからない」 「中学生になったのに、英語がまったくできていない気がする」 三重県四日市市・川越町・富洲原エリアでも、保護者の方から非常に多く寄せられるのが **"英語がまったく読めない・書けない"**という悩みです。 この相談で多くの保護者が感じるのは、 「もう手遅れなのではないか」 「英語は才能の差が大きいのではないか」 という不安です。 しかし、結論からはっきりお伝えします。 英語が読めない・書けない状態は、才能の問題ではありません。 原因はほぼ100%、英語学習の順番と設計を間違えていることにあります。
■なぜ英語が「まったく」できなくなるのか?
よくある5つの原因
① アルファベットと音の結びつきが不十分 英語が苦手な子の多くは、 ・アルファベットは見たことがある ・でも音と結びついていない 状態です。 英語は 「文字 → 音 → 意味」 の言語です。 音が入っていない英語は、暗号と同じです。
② 単語を「読めないまま」書かされてきた 小学生〜中学生でよくあるのが、 ・単語の意味だけ覚える ・スペルを丸暗記する という学習。 読めない単語は、 ・覚えられない ・使えない ・すぐ忘れる という悪循環に入ります。
③ 日本語と同じ感覚で英語を理解しようとしている 英語は ・語順 ・文の組み立て が日本語とまったく違います。 「日本語に訳してから考える」 癖が強いほど、 英文が長くなった瞬間に理解が止まります。
④ 文法が"意味不明なルール"になっている be動詞、一般動詞、三単現、過去形...。 これらを 「覚えるもの」 として扱ってきた子は、英語が一気にわからなくなります。 文法は暗記ではなく、構造理解が必要です。
⑤ 「わからないまま進んでしまった」期間が長い 英語は積み上げ教科です。 一度わからなくなると、次の単元はさらに理解できません。 ・授業が苦痛 ・英語を見るだけで拒否反応 ・書く以前に読むのを避ける この状態になると、「まったくできない」と感じるようになります。
■保護者がやってはいけないNG対応
● 「小学生で習ったでしょ?」と言う ● 単語をひたすら書かせる ● 文法用語を覚えさせようとする ● 他の子と比べる これらはすべて、 英語=無理な教科 という意識を強めてしまいます。
■家庭でできる「英語を立て直す」3つのアドバイス
① まずは「読める音」を作る 英語ができない子に最初に必要なのは、 書くことではなく、読むことです。 ・アルファベットの音 ・フォニックスの基本 ・単語を声に出して読む これだけで、英語への拒否感は大きく下がります。
② 単語は「音→意味→つづり」の順 正しい順番は以下です。 声に出して読む 意味を確認する 最後に書く いきなり書かせない。 これが英語立て直しの最大のポイントです。
③ 文法は「型」で覚える 文法を説明しようとしなくて大丈夫です。 ・I am ~ ・I like ~ ・I can ~ このような短い型を口に出して使うことで、 自然に文の形が身についていきます。
■毎日個別学習Smileが実践している「英語ができるようになる設計」
毎日個別学習Smileでは、 英語がまったくできない生徒に対して、次の順番を徹底しています。 ● 音(フォニックス)から必ずスタート ● 単語は「読める」を最優先 ● 文法はルール説明より"使い方" ● わからない状態で先に進ませない ● 小さな成功体験を毎回作る この設計により、 「英語が読めるようになった」 「単語が前より頭に残る」 「英語の授業が少し楽になった」 という変化が短期間で起こります。
■まとめ:英語ができないのは「才能」ではない
英語がまったく読めない・書けない状態は、 これまでの学習方法が合っていなかっただけです。 ・音が入っていない ・順番が逆 ・理解しないまま進んだ これらを正せば、英語は必ず立て直せます。 毎日個別学習Smileは、 英語が苦手な子を置き去りにする塾ではなく、 **「できないところからやり直せる塾」**です。 英語がまったくできないと感じた今こそ、 学習方法を根本から見直す最適なタイミングです。
(毎日個別学習Smile) 2026年1月 5日 11:47
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ38
--毎日個別学習Smileが考える"暗記できない子"を変える学習設計--
「何回書いても漢字を覚えられない」 「英単語を毎日やっているのに、テストになると出てこない」 「うちの子は暗記が苦手なのでは...」 三重県四日市市・川越町・富洲原エリアでも、保護者から非常に多く寄せられる悩みが **"漢字・英単語などの暗記ができない"**という相談です。 しかし、最初にお伝えしておきたい大切な事実があります。 暗記ができない子どもは、ほぼ存在しません。 問題は「能力」ではなく、暗記のやり方・順番・量の設計ミスです。
■なぜ漢字・英単語が覚えられないのか?
よくある5つの原因
①「書けば覚えられる」という思い込み 多くの家庭で行われているのが、 ・ひたすらノートに書く ・10回、20回と反復する という方法です。 しかしこれは、最も定着しにくい暗記法です。 意識が「文字をきれいに書くこと」に向き、 脳は記憶ではなく作業をしている状態になります。
② 覚える量が多すぎる 1回で ・漢字20個 ・英単語30個 など、一気に覚えさせようとしていませんか? 脳は一度に大量の情報を長期記憶にできません。 結果として 「やったのに覚えていない」 という状態になります。
③ 音・意味・使い方が結びついていない 暗記が苦手な子の多くは、 ・漢字の意味を知らない ・英単語を日本語と結びつけていない ・実際の使い方をイメージできていない 状態です。 これは"記号として覚えようとしている"ため、すぐ忘れます。
④ 「思い出す練習」をしていない 暗記は 見る → 覚える → 思い出す の順番が重要です。 多くの子は ・見て ・書いて 終わってしまい、 「思い出す練習」をしていません。 テストで出てこないのは、当然の結果です。
⑤ 失敗体験が積み重なっている 「また覚えられなかった」 「自分は暗記ができない」 この思い込みが、集中力と意欲を下げ、 さらに暗記がうまくいかなくなります。
■保護者がやってはいけないNG対応 ●
「何回書けば覚えるの?」と責める ● 「こんなの簡単でしょ」と言う ● 暗記量だけで努力を評価する ● 他の子と比較する これらはすべて、 暗記=苦痛 という認識を強めてしまいます。
■家庭でできる「暗記ができる子に変わる」3つのアドバイス
① 覚える量を"半分以下"にする 暗記は 少量 × 高頻度 が最も効果的です。 ・漢字は1日5個 ・英単語は1日7個 これで十分です。 「全部覚える」より 「確実に覚える」 を優先してください。
② 書く前に「読んで・言って・意味を確認」 いきなり書かせないことが最大のポイントです。 漢字なら ・読み ・意味 ・使われ方 英単語なら ・発音 ・日本語 ・短い例文 これを声に出すだけで、定着率は大きく上がります。
③ 「思い出す時間」を必ず作る 暗記の仕上げは 何も見ずに言えるか です。 ・紙を隠して言わせる ・口頭でクイズ形式にする この"思い出す練習"が、テストで点になる力を作ります。
■毎日個別学習Smileが実践している「暗記ができる仕組み」
毎日個別学習Smileでは、 暗記が苦手な生徒に対して次を徹底しています。 ● 書かせる前に必ず「理解・音・意味」を入れる ● 暗記量は最小限、反復回数を最大化 ● 「できた」を毎回可視化して成功体験を作る ● テスト前だけでなく、日常で回る暗記設計 この結果、 「漢字テストが安定した」 「英単語が前より出てくるようになった」 という変化が多く見られます。
■まとめ:暗記できないのは才能ではなく"設計の問題"
漢字や英単語の暗記ができないのは、 ・能力不足 ・努力不足 ではありません。 原因は やり方・量・順番・思い出し方 の設計ミスです。 正しい方法に変えるだけで、 暗記は誰でも必ずできるようになります。 毎日個別学習Smileは、 「暗記が苦手な子」を責める塾ではなく、 暗記が自然にできる仕組みを作る塾です。 漢字・英単語が覚えられないと感じた今こそ、 学習方法を見直す最適なタイミングです。
(毎日個別学習Smile) 2025年12月29日 12:15
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ37
--毎日個別学習Smileが考える"授業理解が止まる本当の理由"と正しい対処法--
「学校の先生の説明がわからない」 「授業を聞いていても、何を言っているのか頭に入らない」 「質問したいけど、何がわからないのかもわからない」 三重県四日市市・川越町・富洲原エリアでも、保護者の方から非常に多く寄せられるのが、この悩みです。 この言葉を聞いたとき、多くの保護者は 「先生の教え方が悪いのでは?」 「うちの子の理解力が足りないのでは?」 と不安になります。 しかし、結論からお伝えすると、 「学校の先生の説明がわからない」という言葉の裏には、もっと構造的な原因があります。 そしてその多くは、家庭と学習環境の整え方で十分に改善可能です。
■「先生の説明がわからない」は、決して珍しいことではない
まず大前提として知っておいてほしいのは、 この悩みは能力差の問題ではない ということです。 現在の学校授業は、 ・限られた時間 ・クラス全体に向けた一斉指導 ・学習指導要領に沿った進行 という条件の中で行われています。 つまり、 「今その瞬間に理解できなければ、次へ進んでしまう構造」 になっているのです。 理解に時間がかかる子、前の単元に抜けがある子にとっては、 「先生の説明がわからない」 と感じるのは、むしろ自然な反応です。
■なぜ「先生の説明」がわからなくなるのか?主な5つの原因
① 前の単元・基礎の抜けがある 最も多い原因がこれです。 ・計算の基礎が不安定 ・英単語や語彙が不足している ・用語の意味が曖昧 この状態で新しい説明を聞いても、 先生の言葉が"知らない言葉の連続"になり、理解が止まります。
② 説明スピードと処理スピードが合っていない 学校の授業はテンポが一定です。 一度つまずくと、説明を聞き直す時間はありません。 「途中から話についていけなくなった」 という感覚は、理解力の問題ではなく、処理スピードの差によるものです。
③ 聞きながら理解する力(聴解力)が育っていない 多くの子どもは、 ・ノートを書く ・板書を写す ことに意識が向き、先生の説明を十分に聞けていません。 結果として 「ノートはあるけど、内容はわからない」 という状態になります。
④ 「わからない」をその場で止めてしまう 質問できない子ほど、 「ここがわからない」 を心の中で処理せず、そのまま流してしまいます。 この小さな"わからない"の積み重ねが、 「先生の説明が全部わからない」 という感覚につながります。
⑤ 集中力・メンタル面の影響 ・疲れている ・自信がなくなっている ・前に失敗体験がある こうした状態では、説明が頭に入りにくくなります。 特に中学生以降は、メンタル要因が理解力に直結します。
■保護者がやってはいけないNG対応 ●
「ちゃんと聞いてないからでしょ?」と言う ● 先生や学校を否定する ● 「みんなわかってるのに」と比較する ● 無理に質問させようとする これらはすべて、 子どもを「理解できない側」に固定してしまう関わり方です。
■家庭でできる3つの正しいアドバイス
① 「どこからわからなくなったか」を一緒に探す 重要なのは、 「今の授業がわからない」 ではなく、 **「どこまでならわかっていたか」**を確認することです。 ・この単元の前は理解できていた? ・どの言葉が引っかかっている? ここを一緒に整理するだけで、子どもは安心します。
② ノートを"説明できるか"でチェックする ノートを見て 「ここ、どういう意味?」 と聞いてみてください。 説明できなければ、 そこが理解の抜けポイントです。 叱る必要はありません。 気づくだけで十分な前進です。
③ 家庭では「補足役」に徹する 保護者が先生役になる必要はありません。 ・教科書を一緒に読む ・用語を一つずつ確認する ・例題を一問だけ解く これだけで、授業理解は大きく改善します。
■毎日個別学習Smileが考える「授業理解を取り戻す設計」
毎日個別学習Smileでは、 「先生の説明がわからない」と感じている生徒に対し、次を徹底しています。 ● 前提知識の抜けをピンポイントで補う ● 授業内容を"かみ砕いて再構築"する ● わかったつもりを許さず、説明できるかで確認 ● 家庭でやるべき最低限の復習を明確化 この設計により、 「学校の授業が前より聞けるようになった」 という声が多く届いています。
■まとめ:「先生の説明がわからない」はSOSサイン
学校の先生の説明がわからないと言い出したとき、 それは学力が落ちたサインではなく、助けを求めるサインです。 ・基礎の抜け ・理解スピードのズレ ・学習環境のミスマッチ これらを整えれば、授業は再び理解できるようになります。 毎日個別学習Smileは、 学校の授業を否定するのではなく、 学校の授業が「わかる場所」に変わるサポートを行う塾です。 「先生の説明がわからない」と感じた今こそ、 学習の土台を整え直す最適なタイミングです。
(毎日個別学習Smile) 2025年12月22日 13:35
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ36
--毎日個別学習Smileが考える"復習しない本当の理由"と正しい関わり方--
「家ではまったく復習をしていない」 「塾や学校では頑張っているようだが、家では机に向かわない」 「復習しなさいと言うと、親子ゲンカになる」 三重県四日市市・川越町・富洲原エリアで、保護者の方から非常に多く寄せられるのが **"家で復習をしていない"**という悩みです。 しかし、結論からお伝えすると、復習をしていないこと自体は問題の本質ではありません。
問題なのは、 「なぜ復習をしていないのか」 「復習の意味が子どもに伝わっているか」 この2点が整理されていないことです。 復習は、成績を伸ばすうえで最も重要な行動ですが、 同時に最も誤解され、最も失敗しやすい学習行動でもあります。
■なぜ子どもは「家で復習をしない」のか?
① 復習の"やり方"がわからない 多くの子どもは 「復習=宿題」 だと思っています。 ・どこを ・どれくらい ・何のために 復習すればよいかを教わっていないため、結局何もしなくなります。 これはやる気の問題ではなく、設計ミスです。
② 学校や塾の授業が「わからないまま」になっている 授業内容を理解できていない場合、 復習は「思い出す作業」ではなく **「もう一度苦しむ作業」**になります。 人は、つらいことを無意識に避けます。 復習をしないのは、理解不足のサインであることが非常に多いのです。
③ 復習しても成果が実感できない 復習をしても ・点数が変わらない ・褒められない ・評価されない 状態が続くと、子どもは「やっても意味がない」と感じます。 特に小学生高学年〜中学生に多い傾向です。
④ 家庭が"復習=努力・根性論"になっている 「とにかくやりなさい」 「みんな復習している」 「やらないと成績が下がる」 この声かけは、ほぼ確実に逆効果です。 復習が義務・罰になった瞬間、子どもは学習から心を切り離します。
■復習しない子に対して、保護者がやってはいけないこと
● 毎日「復習した?」と聞く ● 勉強時間の長さで評価する ● 他の子と比較する ● 感情的に叱る これらはすべて、 「勉強=嫌なもの」 という認識を強化してしまいます。 復習は、管理するものではなく 設計し直すものです。
■家庭でできる「復習が自然に回り出す」3つのアドバイス
① 復習は「5分・1教科」でいい 復習が続かない最大の原因は 最初からハードルが高すぎることです。 ・1日1教科 ・5〜10分 ・その日の授業内容だけ これで十分です。 復習は"短く・軽く・確実に"が正解です。
② 「何を覚えたか」を言葉で説明させる 問題を解かせる必要はありません。 「今日、学校(塾)で何やった?」 「一番大事なところはどこ?」 これに答えられれば、 それは立派な復習です。 説明できない=理解が浅い という判断材料にもなります。
③ 復習のゴールを"点数"にしない 復習の目的は、 思い出せる状態を作ることです。 ・完璧に覚える ・全部解ける は必要ありません。 「思い出せた」 「前よりわかった」 この感覚を積み重ねることが、復習習慣につながります。
■塾に通っているのに復習しない場合の注意点
塾に任せきりになっている場合、 家庭と塾の役割がズレている可能性があります。 復習が回らないケースでは、 ・授業内容が難しすぎる ・家庭でやるべき復習が明確でない ・子どもが理解不足のまま進んでいる ことが非常に多いです。 塾と家庭が 「何を家で復習するか」 を共有できているかが重要です。
■毎日個別学習Smileが考える「復習が続く仕組み」
毎日個別学習Smileでは、 復習を「やらせるもの」ではなく **「自然に回る仕組み」**として設計しています。
● 授業内で"家でやる復習内容"を明確化
● 復習量は最小限、効果は最大化
● 理解できていない状態で宿題を出さない
● 復習が成果につながる体験を早期に作る この仕組みがあるからこそ、 「家で何もしていなかった子」が 少しずつ机に向かうようになります。
■まとめ:復習しないのは「怠け」ではない
家で復習をしていない子どもは、 ・やり方を知らない ・わからない状態が放置されている ・意味を感じられていない だけのケースがほとんどです。 復習は、 叱って増やすものではなく、設計して回すものです。 保護者の関わり方が変わるだけで、 復習は「苦痛」から「当たり前」に変わります。 毎日個別学習Smileは、 復習ができない子を責めるのではなく、 できるようになる環境を整える塾です。 「家で復習をしていない」と感じた今こそ、 学習のやり方を見直す最適なタイミングです。
(毎日個別学習Smile) 2025年12月15日 13:59
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ35
「最近、授業の内容をわかっていない気がする...」 「家で宿題をするときに、説明ができなくなっている」 「ノートを見ても内容がスカスカで、授業についていけていないのが心配」 三重県四日市市・川越町・富洲原エリアでも、保護者から最も多く寄せられる悩みの一つが、 **"授業を理解していない様子"**に関する相談です。 授業が理解できていないサインは、小学生・中学生・高校生すべてで共通して現れます。 そして、授業理解不足は放置すると ・定期テストの点数低下 ・実力テストの偏差値急落 ・やる気の喪失 ・学習習慣の乱れ につながり、子どもの成績が大きく下向きになる"最初のサイン"でもあります。 しかし、正しく原因をつかめば、短期間で改善するケースが非常に多く、実はこの悩みは"早期発見できれば最も改善しやすい学習課題"です。 以下では、授業を理解していないときに保護者が知るべき要因と 今日から実践できる改善アドバイスをまとめています。
■なぜ「授業を理解していない様子」が生まれるのか?
① 基礎の穴が、授業内容の理解を妨げている 授業理解ができていない多くのケースは、 「今習っている単元の前の基礎が抜けている」 ことが原因です。 たとえば ・分数が曖昧 → 比例・反比例がわからない ・英単語が読めない → 文法の理解が追いつかない ・語彙不足 → 国語・社会の説明が理解できない つまり、授業が難しいのではなく、土台が足りていないのです。
② 授業スピードと子どもの処理スピードが合っていない 現代の学校授業はスピードが早く、 理解に時間がかかる子は、その瞬間に置いていかれます。 一度置いていかれると、 「もう無理だ...」 という気持ちが強くなり、内容が頭に入らなくなります。
③ 授業中の"聞く力"が弱い 集中力が続かず、 ・板書を写すだけで精一杯 ・先生の説明を聞き逃す ・質問の意味を理解できない といった状態になると、ノートが残っていても授業内容は理解できていません。
④ わかったつもりになっている 特に中学生に多いのが "理解した気分"だけで先に進んでしまう ケース。 ・授業中にうなずいている ・問題が解けた気になっている ・実際に解かせるとできない これは"理解"ではなく"雰囲気理解"です。
⑤ 家庭学習の不足・反復不足 授業内容は、家での復習で定着します。 復習ゼロのまま次の授業に行けば、当然「わからない」が積み重なります。 学校の授業が理解できない背景には、 家庭での復習不足が最も多く存在しています。
■家庭でできる「授業理解を取り戻す」ための3つのアドバイス
① 「何がわからないか」を明確にしてあげる 子どもは自分で"何がわかっていないか"を言語化できません。 保護者ができるのは、次の3つの質問だけです。 今日の授業で「できた」と思うところは? 今日の授業で「ちょっと怪しい」と思うところは? 今日の宿題で「手が止まったところ」はどこ? これだけで、授業理解不足の大半が浮き彫りになります。
② ノートの"理解チェック"を家庭で軽く行う ノートには ・写しただけの内容 ・理解して書いた内容 が混ざっています。 家庭では、次の一言だけで十分です。 「この部分、どういう意味?」 「どうやって解いたの?」 説明できれば理解できています。 説明できなければ理解が抜けています。 時間は1分でOKです。
③ 家庭学習は「量」より"方向性" 授業を理解できていないときの家庭学習で最も重要なのは、 **"復習の順番を間違えないこと"**です。 具体的には、 今日の授業の要点を音読 教科書で同じ部分を読み直し 学校ワークで例題を解く 宿題に着手 この流れが最も効率的で、授業理解が最速で戻ります。
■毎日個別学習Smileが実践している"授業理解"アップの指導
毎日個別学習Smileでは、授業内容が理解できていない生徒に対して 次の3つのアプローチを必ず行います。
● ① 前の単元の理解度チェック 10分で行える"ミニ診断"で、基礎の穴を見つけます。
● ② 今の授業でつまずいているポイントを特定 子ども自身では気づけない"理解のズレ"をプロが補正します。
● ③ 初見問題×基礎問題のセット練習 授業理解を定着させるには、 基礎 → 応用 の順での反復が必須です。 授業理解が浅い子ほど、この組み合わせが最も効果的です。
■まとめ:授業を理解していないのは"才能不足"ではなく"改善チャンス"
授業を理解していない様子は、多くの保護者が最初に気づく"黄色信号"です。 しかしこれは、 正しいステップを踏むことで短期間で改善できる信号 でもあります。
・基礎の穴 ・授業スピードとのミスマッチ ・家庭学習の方向性のズレ ・読解力不足 これらを少しずつ修正していけば、必ず授業理解は戻ります。 毎日個別学習Smileでは、授業理解が浅いお子さまでも 「わかる → できる → 自信がつく」 のサイクルを作り、成績を安定的に伸ばすサポートを行っています。 授業を理解できていない今こそ、 お子さまの学習環境を整え、学力の土台を固める絶好のタイミングです。
(毎日個別学習Smile) 2025年12月 8日 15:51
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ34
--中学生の"実力不足"の正体を理解し、志望校合格に向けて何をすべきか-- 「学校の定期テストは点が取れているのに、実力テストになると偏差値が出ない...」 「塾では理解しているはずなのに、模試では急に点数が落ちる」 三重県四日市市・川越町・富洲原エリアの保護者の方から、最も多い相談の一つがこの"実力テストの偏差値"についてです。 実力テストは、定期テストとは形式も目的も異なり、勉強の「本当の穴」が一気に見えてしまうため、偏差値が低く出るのは珍しいことではありません。しかし、正しく原因を分析し、家庭での声かけと学習環境を整えることで、偏差値は必ず改善します。 本記事では、実力テストで偏差値が出ない理由と家庭でできるアドバイスを、保護者の方向けにわかりやすくまとめました。
■なぜ「実力テスト」だけ偏差値が低くなるのか?
① 実力テストは"初見問題"が多いから 定期テストは学校ワークや授業内容の反復で点が取れます。 しかし、実力テストは ・初めて見る問題の読解 ・応用力 ・基礎理解の深さ が試されるため、思考力の差が偏差値に直結します。 「ワークは解けるのにテストになると解けない」 という子が偏差値を落としやすい傾向です。
② "基礎"が完全に固まっていない 実力テストは、基礎が少しでも抜けていると一気に点数が下がります。 ・英単語の穴 ・数学の計算ミス ・国語の語彙不足 ・理科社会の重要語句の抜け これらはすべて偏差値に影響します。 得意科目ですら点が伸びない場合、往々にして基礎理解が感覚頼りになっています。
③ 読解力・問題文の処理力が不足している 実力テストでは、文章量が多く、問題文を丁寧に読み解く力が求められます。 ・焦って読み飛ばす ・条件を見落とす ・図や表を最後まで読まない これらは中学生に非常に多いミスで、偏差値が出ない原因の約半分を占めるとも言われています。
④ テストの"解き方"を知らない 実力テストでは、 ・時間配分 ・優先順位の判断 ・難問の切り捨て といった"戦い方"が重要になります。 しかし、多くの中学生が 「順番に全部解こうとする」 ため、時間切れになり偏差値が伸びません。
⑤ 試験当日のメンタル・集中力の問題 実力テストは普段とは違う環境で行われるため、 ・焦り ・緊張 ・自信のなさ が点数に影響します。 実力テスト特有の緊張感に慣れていないと、実力を出し切れません。
■家庭でできる「偏差値を上げる」3つのアドバイス
① 基礎の"抜けチェック"を一緒にする 偏差値が出ない多くの原因は、基礎の穴です。 週1回、5分だけでも良いので以下をチェックする習慣がおすすめです。 ・英単語の定着 ・数学の計算がスムーズか ・理社のキーワードが出てくるか 家庭で軽くチェックするだけで、子どもは"見られている意識"が生まれ、取り組みが変わります。
② 定期テスト勉強だけに偏らない 保護者が最も誤解しやすいポイントがこれです。 定期テストの高得点 = 実力テストの高偏差値 ではありません。 定期テストは"学校ワーク対策" 実力テストは"応用・初見問題対策" 目的が違うため、勉強方法も分ける必要があります。 ● 定期テスト勉強 →ワーク反復・授業内容の理解 ● 実力テスト勉強 →初見問題練習・読解トレーニング・過去問演習 この違いを家庭で説明してあげると、子どもは勉強の方向性を間違えなくなります。
③ 日常的に"読解力"を育てる環境を作る 偏差値に最も関係するのは、実は「読解力」です。 家庭でできることはシンプルで、 ・問題文を声に出して読ませる ・図や表を説明させる ・なぜその答えになるのかを聞く これだけでも読解力の向上につながります。 読解力は一朝一夕では伸びませんが、家庭での習慣が一番効果的です。
■塾を活用するときのポイント
塾に通っているのに偏差値が出ない場合、 "対策の方向性がずれている"可能性があります。 以下を塾に確認すると改善しやすくなります。 ・基礎の穴を把握しているか ・初見問題にどれだけ対応できているか ・時間配分の指導があるか ・偏差値アップのための個別対策はしているか 塾の先生と家庭が同じ方向を向くことが、偏差値改善には不可欠です。
■まとめ:偏差値が出ないのは"才能不足"ではない
実力テストの偏差値は、 "今の学習方法が合っていない"サイン であり、決して能力の問題ではありません。 ・基礎の穴 ・読解力不足 ・時間配分 ・初見問題への弱さ これらを修正すれば、偏差値は必ず上がります。 特に、三重県四日市・川越・富洲原の保護者の方からは、 「定期テストは取れるのに模試では偏差値が低い」 という相談が多く、地域全体でも同じ悩みを抱えている家庭は多いです。 偏差値が出ない今こそ、 "正しい勉強方法に変えるチャンス" です。 保護者のちょっとした声かけや環境づくりが、お子さまの偏差値アップに大きく影響します。 今日からできる工夫を取り入れ、志望校に近づくステップを一緒に作っていきましょう。
(毎日個別学習Smile) 2025年12月 1日 15:30
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。