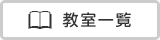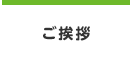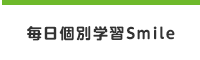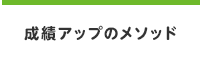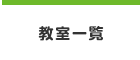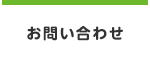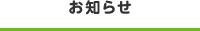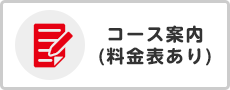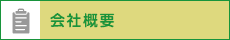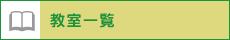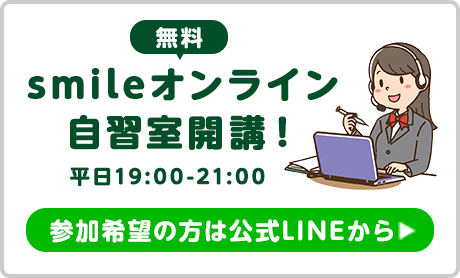月別 アーカイブ
- 2025年7月 (18)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
HOME > スクールブログ
スクールブログ
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ187
1. なぜ「ゲーム・動画を餌にしないと勉強しない」のか?
1. 子どもにとって動画やゲームは"即時報酬" ゲームや動画はカラフル・音響・達成感など刺激が多く、子どもは短時間で強い快楽を得られます。自然と勉強よりも魅力的に感じてしまうのです
2.時間感覚と自己調整力が未熟 小学生は時間や行動の見通しがつきにくく、気づけば延々と遊び続けてしまう傾向があります。親の「やめなさい」が反発につながることもしばしばです 。
3. 親も使ってしまう"ゲーム・動画誘導" 「宿題終わったらゲームOK」「動画を餌に勉強させる」のは短期的には効果がありますが、子どもの内発的な学び意欲や自己肯定感を育てることにはつながりません。
2. 親ができる"学びのスイッチづくり"5つの方法
1.一緒に楽しむ「共遊共学(JME)」を取り入れる
親子で一緒に知育ゲームや科学動画を楽しみながら、終わった後に「どうだった?」と振り返る時間を持ちましょう。研究ではこの共遊が関係性と学び意欲を高めるとされています 。
2.学びを"ゲームや動画化"する
ドリルをタイムアタック形式にしたり、漢字練習をビンゴ形式にするなどエンタメ要素をプラスすることで、「遊ぶように学ぶ」体験を提供できます。
3.学び後の報酬より「学びそのものの気持ち」を褒める
「終わらせたね」ではなく、「自分で始めたね」「集中して取り組んだね」と行動に対する気持ちを伝えることで、自主心や継続力を育めます。
4. スマホ・動画は「条件付きでOK」に
「動画見る前に勉強15分」ではなく、「出したいものを出さないと動画はなし」「今日は頑張ったら15分だけOK」と、締め切りと使い道をはっきりさせることで効果が変わります 。
5.親自身の"デジタル行動の振り返り"をセットに
親がスマホ依存傾向にあると、子どもに正しい指導をしづらいもの。親子で一緒にデジタルデトックスやルールを作ると、学び文化が家庭に根づきます
3.実践例:小学4年生の週末「学び+遊び」リズム 時間帯 内容 アプローチ
1.午前 学習タイム(タイマー15分) 表で時間と内容を可視化
2.昼前 科学動画を一緒に視聴 楽しんだ後に感想を共有
3.午後 知育ゲームやパズル 親と一緒にやることで学びを強化
4.夕方 自由タイム(ゲームOK) 学びと遊びのバランスを理解
5.夜 振り返り 「今日はどうだった?」で安心感
ポイント
1.タイマーで時間管理
2. 動画・ゲームは学びとのセットで楽しむ
3.振り返りで自己理解と学び意欲を育む
4. 続けることでうまれる親子の変化
アプローチ 子どもに育つ力 親に生まれる効果
1.共遊共学 親への信頼と学び意欲 家庭の学び文化が育つ
2.学びの遊び化 自主性と集中力 教え方に楽しさが出る
3.感情褒め やる気と自己肯定感 子どもの気持ちに寄り添える
4.条件付きルール 自制心と計画性 約束を守る文化が育つ
5.親の振り返り 生活モデルとしての影響 家庭のルールへの納得感
締めの言葉
「ゲームや動画に頼らなければ動かない親子から、"学びそのものが楽しい"親子へ。共遊し、約束を作り、振り返る。そのプロセスこそが、子どもが自ら学ぶ力を育む土台です。親が"スイッチづくり"のデザイナーになれば、子どもの未来はもっと自由で豊かになります。」 大切なのは「勉強しないこと」の責任ではなく、「どうすれば勉強したくなるか?」を一緒に考えること。その時間を親子で大切に育てることで、いつか子どもは主体的に学ぶようになります。 親子で"学びのスイッチ"を一緒にデザインしていきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月18日 14:16
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ186
1. なぜ「宿題を出していない」と言われるのか?
1.小学中学年の宿題忘れは約半数という現実
Yahoo!知恵袋にも投稿があり、宿題や音読カードを連絡帳に入れても提出が週単位で遅れるケースが報告されています。親が声かけや工夫を重ねても変わらない、その状況は"やる気不足"とは違う原因が存在するサインです
2.親の言葉が「説教」になっている可能性
教師の例では、叱るのではなく「提出は約束であり、君の人間性に関わる」と淡々と伝えたことで、自ら提出するようになった子もいます。このような"事実と想いを伝える語り"は、叱責より深く響くことが多いです 。
2.気持ちを受け止める5つの関わり方
1. 感情から入る共感対話 「宿題出さなかったね、どうしてだと思う?」と素直な質問で始めましょう。親の苛立ちよりも、子どもの本音を引き出す声かけが最初の一歩です。
2. "理由"を聞き、解決方向を探す 「寝坊した?」「わからないからやりたくなかった?」など、背景を聞くことで、単なる怠けではない理由が見えてきます。
3.提出を"義務"ではなく"自分で選んでやる"に変える 「今から15分で仕上げようか」と時間を区切り、一緒に取り組む姿勢を見せることで、子どもも"やれば終わる"と実感しやすくなります。
4.教師の言葉で伝える視点を取り入れる 「先生も提出は"約束"だと言ってたよ」「〇〇さんが楽しみにしてくれてたらどう?」など、外部の声を借りることで受け止めやすくなることがあります 。
5. 小さな"できた"を見逃さない 提出できたときは、「今日は出せたね、すごい」と親からの承認だけでなく、子ども自身の成長として共有することが大切です。
3.実践例:宿題を提出しない小学4年生の場合
ステップ 親の関わり方 子どもの気持ちへの影響
① 振り返り 「今日は宿題どうだった?」と共感 安心して本音を言える
② 背景を聴く 「教科が難しかった?」「疲れてた?」 理由が見え、次の工夫に
③ 時間短縮 「今15分一緒にやってみよう」 「やればできる」実感へ
④ 教師の言葉 「先生も提出は大切って言ってた」 第三者の言葉で責任感UP
⑤ 成功の共有 「出せたね!嬉しかった?」 小さな達成感が次へ
4. 続けることで広がる未来の可能性
1.親のあり方 子どもに育つ力 親が得られるもの
2.共感と対話 自分のペースで挑戦する安心感 子どもの声が聴ける安心
3.背景の理解 自分を知ってもらった実感 対話による関係強化
4.一緒に取り組む習慣 自分でやり遂げる達成感 楽しみながら支える自信
5.第三者の声 社会的な責任感 プレッシャーからの解放
6.成果を共有 小さな自信の積み重ね 親自身の育児満足度アップ
締めの言葉
「"宿題を出していない"と言われても、それは叱る材料ではなく、子どもの気持ちと向き合う入り口です。理由を聴き、一緒に取り組む姿勢を見せ、教師の言葉も借りて、小さな成功をともに喜ぶ----その繰り返しが、子どもの"自分でやれる"を育て、親子の安心と信頼の学びへと変わっていきます。」 忘れ物や宿題を出せない時期は、子どもにとって「やってもやらなくても同じ」になっているサイン。そこに寄り添い、問いかけ、共に進むことで、親子で少しずつ「出せた」の実感と信頼を積み重ねていけます。 一歩ずつ。親子で安心して挑む学びの時間を育んでいきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月17日 13:58
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ185
1.なぜ"書くスピードが遅い"ことが問題になるのか?
テストの持ち時間を使い切れず、解けるはずの問題を諦めることに繋がる 多くの小学生が「問題は分かっているのに書くのが間に合わない」と悩んでおり、まずは"処理速度"つまり書く速さを意識した訓練が有効です 。
2.目と手の連携が未完成だと筆記に時間がかかる
「漢字や図を写すのに時間がかかる」背景には、視覚と筆記の連動が成熟していないケースもあり、丁寧にトレーニングを重ねることで改善が期待できます 。
2.スピードも正確さも育てる5つの改善ステップ ①
1.まず現在の"速度"を数値化する 宿題やプリントの時間をタイマー計測し、「これだけの時間で▲文字書けた」を可視化。基準が見えれば改善方向が明確になります 。
2. 処理速度を妨げない声かけをする 「早くしなさい」ではなく、「時間制でやってみよう」「30秒で○文字書いて競争しよう」など具体的な声をかけることで、焦らず取り組めます 。
3. 短時間・集中型の反復練習 10問をまとめて練習するより、「5分で何問書けるか」の短時間チャレンジ型の練習を毎日少しずつ繰り返す方が効果が高くなります 。
4.口答や選択式で書く量を減らす訓練も併用 口頭で答える・選んで回答するスタイルを取り入れることで、"書く負担"を軽減しながら頭の回転を鍛えます
5. 丁寧さよりも"伝えるスピード"を優先する 図を一発で描く練習や、一度に書かずにラフで書くなど、"手順を意識して速く伝える"練習に切り替えることで効率的になります
3. 実践例:テストで時間切れになる小学4年生の場合
1.ステップ 2.内容 3.各ステップで育つ力
1.時間を測定 2.宿題漢字20字をタイマーで記録 3.自分の書くスピードが把握できる
1.チャレンジ 2.「30秒で5文字」など短チャレンジ 3.集中と達成感が生まれる
1. 写す+図練習 2.黒板の図や問題を1分で写す練習3.目⇄手の連携力が身につく
1. 書かない選択も 2.答えを口で発表、漢字は選択式 3.筆記負担を分散し集中力向上
1.一発描写の練習 2.図形を一度で描いてアウトプット 3.手順を効率化して正確さと速度を両立
4.取り組むことで得られる未来の変化
1.取り組み 2.子どもに育つ力 3.親に生まれる安心
1.書く速度の可視化 2.自分の"今の力"を理解・納得できる 3.客観的な成長実感が得られる
1.時間チャレンジ 2.集中力と自信が高まる 3.目に見える成果で安心できる
1.処理の選択肢 2.自分に合わせた方法が選べる 3.子どもの個性を受け止められる
1.手順を効率化 2.短時間で正確に伝える技術が身につく 3.学習に余裕が生まれる
1.反復でも飽きない工夫 2.持続的な学びの習慣ができる 3.家庭学習が楽しくなる
締めの言葉
「書くのが遅いと悩むことは、子どもの"協調力の発達段階"を知るサインです。時間を数値化し、小さなチャレンジを重ね、効率的に伝える方法を覚えていけば、"遅い"は"着実"に変わります。親子で少しずつ育てる学びの速度が、子どもの安心と可能性を自然に広げてくれます。」 書くスピードはすぐに速くなるものではありませんが、「数値化→焦らない声かけ→短時間集中→負担軽減→効率化」の積み重ねで、必ず進歩が見えてきます。 まずは一歩ずつ。親子で安心とともに、着実な成長のひとときを歩んでいきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月16日 13:51
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ184
1.どうして子どもは反復練習を嫌がるのか?
1.単なる繰り返しでは意味を感じられない
漢字をただ10回書かせる、計算ドリルを何度も解く...ただの繰り返しは、脳にとって"意味のない作業"に映り、集中力や定着力が下がります 。
2. ギフテッドやADHD傾向の子は興味ない反復を拒否
すでに理解している作業や単純な練習に「なぜ今やるの?」という疑問を持ち、強制されるほど反発しやすくなります 。
3. 無意識モードで進めると学びにならない
覚えようという意識がないまま書き写すだけの単調な練習は、記憶にも残らず退屈感だけが増してしまいます 。
2. 「意味ある反復」を作る5つの方法
1.目的と意味を子どもと共有する 「この漢字、どうして10回覚えるか?」「明日書けるようになったら楽しいね」と、練習の意味を言葉にして本人と確認することで、やる気が生まれやすくなります 。
2. 3~5回+関連学習に切り替える ベネッセの研究でも、「同じ漢字を3〜5回書いたら、例文や熟語を書く方が定着率が高い」と報告されています 3. ゲーム形式や短時間チャレンジを取り入れる 「2分で何問?」など時間制にして競争感覚を加える。ダラダラやるよりも集中力が引き出せます 4. 散らばり(インターリーブ)学習で切り替える 反復練習だけでなく、他教科や遊びをはさむことで刺激が変わり、集中力が回復しやすくなります
5. 子どもに振り返らせる 「前より書けるようになった?」「どの漢字が楽に書けた?」など、気づきを言葉にすることで、自ら進める動機が育ちます。
3. 実践例:漢字練習が嫌いな小学3年生の場合
ステップ 方法 期待される効果
1. 目的の確認 「この漢字で日記を書こうね」 ゴール意識が明確になる
2. 反復3回 + 例文追加 漢字3回→熟語1つ→例文1文 意味理解と記憶定着が強化
3. ゲーム:制限時間チャレンジ 「30秒で何回書ける?」 集中力と楽しさUP
4. 教科切り替え 漢字→算数→漢字...と効率調整 脳の負担軽減
5. 振り返り 「最初より上手に書けた?」 自己肯定感と次回への意欲
4.このアプローチで得られる親子の関係と効果
1.行動 2.子どもに育つもの 3.親に育つもの
1.目的共有 2.学習への納得感 3.教育への安心感
1.意味ある反復 2.無理なく記憶に定着 3.子どもの成長実感が見える
1.ゲーム形式・時間 2.集中力を引き出す 3.教え方の工夫が楽しくなる
1.教科切り替え 2.勉強が苦になりにくい 3.効率的な家庭学習ができる
1.振り返り習慣 2.自分で学ぶ力が育つ 3.親子のコミュニケーションが深まる
締めの言葉
「反復練習を嫌がるのは、意味のない作業だから。目的を持ち、短く、楽しく、振り返る。そのプロセスこそが"学びのスイッチ"。親がそのスイッチを作る橋渡し役となれば、嫌いだった練習が"学びのともだち"へと変わっていくのです。」 ただの繰り返しではなく、「知る」「使う」「気づく」をセットにする反復練習。親子で意味ある学びの時間を育てていきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月15日 14:23
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ183
1. なぜ今、「ADHD・グレーゾーン」が気になるのか?
1.発達障害の認知向上と早期支援の流れ 近年、小学生のADHD・ASD・LD・グレーゾーンへの関心が高まり、保護者の不安や相談が増えています。教育現場でも通級や特別支援など支援制度が整備されつつあり、早期発見への意識が強まっています
2.子どもの様子と社会とのギャップ 集中できなかったり、友人関係・学習に困難が見られると、「普通との違い」に親が苦しみ、自責や無力感を抱きやすいです。
3.親が育児に疲れてしまう現実 グレーゾーン児の親の疲労・孤独感を癒す方法や、相談の重要性について広く言及されており、頼れる支援を求める声が強まっています。
2.悩みを安心に変える5つのステップ
1. 小さな気づきを丁寧に記録する 「机に向かえない」「授業中落ち着かない」「忘れ物が多い」など、日々の具体的な様子を記録し、親自身の目線と感覚を整理しましょう。
2.学校とつないで支援を受ける 担任の先生やスクールカウンセラーに相談すると、通級指導や特別支援教育員のサポートが得られ、学校での理解と対応が進みます
3.専門家にアクセスすることも選択肢に 診断があるなしに関わらず、発達障害に詳しい医師や福祉機関で相談すると、家庭に合った支援や学習塾の紹介を受けられます
4.支援機関や親コミュニティを活用 ペアレントトレーニングや母親同士の支援グループ、放課後等デイなど、親が"ひとりで抱え込まない"工夫が見つかります
5. 承認+小さな成功を重ねて自信を育む 「できたら褒める」ではなく、「始めたら褒める」を実践し、小さな一歩を積み重ねて自己肯定感を育てます。
3.実践例:小2で集中困難・忘れ物が多いケース
1.ステップ 2.親の対応 3.子どもの自信・安心へ
1.記録開始 2.ノートや家族LINEに毎日様子を記録 3.未整理の不安を整理しやすく
1.学校連携 2.担任に「通級や補助員の相談は可能か」を確認 3.教室での支えが見える化
1. 専門相談 2.支援センターの相談予約を行う 3.支援の選択肢が明確に
1.代替行動支援 2.「課題に来るまで席に座れたね」と声かけ 3.ゆっくりでも前進している実感
1.親同士交流 2.オンライン親会や現地支援イベントに参加 3.支援情報や気持ちを共有できる
4. このアプローチが拓く可能性
1.親の行動 2.見えてくる子どもの世界 3.子どもに育つ力
1.気づきを記録し整理 2.支援のきっかけと愛情が見える 3.自分を知ってもらっている安心感
1.学校と共に連携 2.教育現場での配慮が得られる 3.授業や生活に安定感が生まれる
1.専門相談と紹介利用 2.家庭に合った学びの場が見つかる 3.苦手を支えて伸ばせる学びの体験
1.親同士の共感と励まし 2.親が孤立せず安心して支えられる 3.子どもも孤独を感じにくい
1.「始めたら褒める」習慣 2.小さな挑戦が積み重なり成長感が湧く 3.自己肯定感が育ち、「次もやってみよう」の意欲に
締めの言葉
「"ADHDかもしれない"、"特性かもしれない"と悩む親心は、子どもの未来を見つめる深い愛情です。記録して相談し、支援を受け、親も学び、組織や他の親とつながる。その歩みが、子どもの"自分でも進める"を育む安心の土台になります。今日から少しずつ、その安心のネットワークを広げていきましょう。」 過ぎた日々を責める必要はありません。気づいたその瞬間が、新しい支援と信頼の始まりです。親子で歩む「気づきと支え合いの学び」を大切に紡いでいきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月14日 14:59
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ182
1. なぜ学校や人間関係のストレスが勉強に影響を与えるのか?
1. 学業への影響が証明されている 学生のストレスは、集中力や自己効力感を低下させ、学業成績や学ぶ意欲にも直接悪影響を及ぼすと示されており。
2.人間関係の摩擦が心に影響 友人関連のトラブルや居場所の不安は、心理的ウェルビーイングを低下させ、勉強への意欲・身体的な健康・学校への所属感すべてに悪影響を与える可能性があります。
3. 心のストレスは身体と行動にも影響する ストレスを抱えると集中できず、集中力散漫や不安・無気力、場合によっては登校渋りや学習性無力感にもつながります
2.親ができる"共感とサポートの5つの関わり方"
1.心の声を受け止める「共感の質問」 「学校はどうだった?何かイヤなことあった?」と寄り添いの言葉から始め、子どもの心が言葉にしやすくする。
2. 放課後の声かけルーティンを作る 例えば「今日一番嬉しかったこととつらかったことを聞かせて」と対話習慣をつくることで、気づきや感情の整理が促されます。
3.身体と心の栄養に気づくサポート うまく書けなかったノートを見て、「ちょっと運動でもしようか」「好きな音楽聴いて、スッキリしてからやろう」と気持ちと体を整える方法を教えます。
4. 友達関係や学校の居場所を可視化する 「誰と遊んでるの?」と仲良しさんの話題を日常に取り込み、対人関係のストレスや絆を言葉に出せる習慣を重ねます。
5. 専門機関や学校サポートを活用する ストレスが強い場合、スクールカウンセラーや友人関係を深めるFTE・FRIENDSプログラムなど、専門的な支援を相談しながら利用します。
3.実践例:小学5年生・友達トラブル後の学習不調ケース
1.ステップ 2.親の対応 3.子どもの気持ちと成果
1.登校後 2.「今日はどうだった?」と声をかける 3.話すことでモヤモヤが整理される 1.放課後 2.「一番嫌だったこと、嬉しかったこと教えて」 3.心が軽くなり、信頼感が生まれる
1.夜 2.ノートの背景を親子で確認し、「今日は○分できたね」と話す 3.小さな「できた!」を見つけられる
1.翌日 2.一緒に散歩や音楽を聴いてリセット時間を 3.気持ちが回復し、集中力が戻る
1.翌週 2.学校に居心地が良かった瞬間を聞く 3.学びへの心理的安心が育まれる
4.この対応で得られる親子の成長と未来
1.親の働きかけ 2.子どもの変化と成長 3.親の支援力の変化
1.共感と受容 2.表現したい気持ちを素直に話せるように 3.子どもへの距離感に余裕と信頼が生まれる
1.感情整理の習慣 2.心と体の回復力が育つ 3.親も感情への対応力が高まる
1.小さな成功の見つけ方 2.自己効力感が育つ 3.成長実感を共有できるようになる
1.友達関係を話題にする習慣 2.学校への所属感や安心が戻る 3.学校生活を理解しやすくなる
1.専門支援と学校連携 2.心の土台が強くなる 3.子どものための支援を選びやすくなる
締めの言葉
「学校や友達のストレスは、そのままにしておくと勉強だけでなく心の土台を揺るがします。ですが"声をかけ、聞き、寄り添い、時には支援を使う"その姿勢が、子どもの安心と学ぶ力を取り戻す道です。親が共に声をかけ続けることで、子どもはもう一度"学びたい"心を取り戻していけるのです。」 子どものストレス発信は「SOS」でもあります。今は学習の"後ろ姿勢"になっていても、親が丁寧に寄り添い続ければ、少しずつ前向きな学びの歩みに戻れます。親子で安心と学びの時間を丁寧に紡いでいきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月14日 14:52
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ181
1. なぜ「学校での様子がわからず不安」になるのか?
1.新学期や学年が上がるときの子どもの不安
調査によると、小学生の約74%が「新学期に不安を感じている」と回答しています。 担任の先生や友人関係への心配が原因で、親は学校での日々が見えず、余計に不安を募らせがちです。
2.ICT授業などの見えにくさも増加
高学年ではタブレットなどを使った授業が頻繁になり(毎日利用は3割超)、授業の進み具合や子どものついていけているかが把握しにくくなる傾向があります
3.担任との関係も影響する見えにくさ
子どもにとって先生との相性は重要で、相性が合わないと話しにくくなり、家庭での情報共有が曇る原因になります 。
2. 不安を安心へ変える5つのコミュニケーション習慣
1. 毎日の「一言質問」で習慣化
「今日一番楽しかったことは?」「先生の話で何を感じた?」と、雑談に混ぜて軽く問いかけることで、日常の様子を聞き出しやすくなります。
2.先生への連絡帳+定期相談
ICT授業やプロジェクト学習の進みや子どもの変化を見逃さないため、定期的に担任に質問したり、個別対応の相談枠を利用しましょう。
3.お友だちとの関係を聞く工夫
「新しい友達と遊んだ?」や「放課後のクラスの雰囲気は?」と聞くことで、学校生活や人間関係の様子が浮かびやすくなります。
4. ICT利用の様子も観察対象に
タブレット授業がある日は、「今日はICTの時間あった?」と聞き、進捗や困りごとがないかを親が把握する姿勢を示しましょう。
5.学校行事・参観後には振り返りを
授業参観や公開日には、一緒に「今日の驚きは何?」と感想を共有する時間を設け、学校での体験を親子の会話に変えます 。
3. 実践例:新学期4年生・ICT授業が始まったケース
1.日付 2.親の問いかけ 3.子どもの返答 4.家庭内対応
1.月曜 2.「今日は担任の先生の話は?」 3.「ちょっと怖かった」 4.翌朝一緒に応援メッセージ
1.火曜 2.「ICT授業で何やった?」 3.「クラスで発表したよ」 4.家でも模擬発表してみる
1.水曜 2.「お友だちと何して遊んだ?」 3.「〇〇ちゃんと鬼ごっこ」 4.週末にその子を招いて遊ぶ
1.金曜 2.「今週の楽しかったこと言ってみて」 3.「先生に名前呼ばれたのが嬉しかった」 4.名前で呼びかける習慣づくりを親も実践
4.積み重ねにより得られる親子の安心と成長
1.習慣 2.子どもに育つもの 3.親に育つもの
1.日常の一言質問 2.安心感・語る習慣 3.学校での様子が見えてくる
1.先生との連携 2.学びへの信頼 3.教育内容を把握できる
1.お友だちとの会話 2.対人関係の手応え 3.人間関係への理解
1.ICTの話題共有 2.デジタル学習の安心 3.新しい授業への理解
1.参観後振り返り会話 2.体験の意味づけ 3.家庭の安心感と信頼
締めの言葉
「学校での様子がわからない不安は、親が'問いかけ'を持つことで安心へ変わります。小さい言葉がけと観察、先生や友達の話を毎日の会話に重ねることで、見えなかった世界が家庭に広がります。その積み重ねが、子どもにとっての居心地と学びへの信頼を育てるのです。」 子どもの学校の"今日"は少しずつだけど確実に家族の中にも広がっています。親子で毎日の一言から安心と信頼の時間を育んでいきましょう。それが、未来への大きな支えとなります。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月12日 13:33
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ180
1.なぜ「SNSや動画ばかり」で勉強しないのか?
1. ショート動画の中毒性と報酬系の刺激
小学生の約67%がテレビより動画を好み、特にショート動画の人気が急上昇しています。短い刺激が脳を刺激し、「もっと見たい」という気持ちが学びより優先される傾向があります
2.自制力が未成熟な子どもの前頭葉
子どもの抑制力(「やめる力」)は未発達。欲望を我慢する力が未熟なため、SNS・動画から離れられず、学習への切り替えがむずかしくなります
3.子ども自身も「勉強したかったのに...」と悩んでいる
意外なことに、子ども自身が「勉強しようと思ってもスマホやSNSに流れてしまう」と自覚しているケースも増えています
2. SNS・動画依存に揺れる親御さんが取るべき4つの親子共育習慣
1. 禁止ではなく、"小さな選択肢"を設ける
単に「見るな!」では反発を招く一方で、「〇分見たら宿題1問」「動画見る前に読書10分」など、選べるルールを設けることで自律性を育みます。 2. 家族で「SNS断ちチャレンジ」実施
土日の午前や夕食後に家族みんなでスマホ断ちに挑戦し、代わりに家族会話や遊びをすることで、居心地いい時間を感じられます
3.勉強に使えるSNS活用法を共有
学習ユースとして、YouTube「授業動画」「勉強法動画」「モチベーション動画」は中高生で高い利用率を誇ります。家庭でも勉強系チャンネルを一緒に探し、勉強への入り口に変えていけます
4. 心と体の生活リズムを整える
睡眠・運動・食事のリズムが崩れるとSNS依存が加速。朝日を浴びて起きる、夜はスクリーンタイムを制限するなど、家庭のルールで生活リズムを整えることが効果的です。
3. 実践例:「毎日SNSばかり見てる小4のケース」
1.時間帯 2.子どもの行動 3.親の関わり・仕掛け
1.帰宅後 2.スマホを手に取る 3.「10分スマホOK、その後30分だけ国語音読」など選べるルール設置
1.夕食後 2.スマホに没頭 3.「今日は家族でSNS断ちナイト。トランプしよう」など家族共通チャレンジ
1.寝る前 2.テレビやスマホで夜更かし 3.毎日21時には画面オフ、明日の楽しみを話す
1.休日 2.自由時間に何もやらない 3.お菓子作りや公園遊びなど代替リストから選ばせる
シナリオの流れ ルール共有 → 2. 子どもの選択 → 3. 約束の実行 → 4. 次の日に一言振り返り → 5. 成功体験を褒める → 習慣化と少しずつ学びへの橋が育つ。
4. このアプローチが親子にもたらすもの
1.親子関係の変化 2.子どもに育つ力
1.共通の目標で繋がる絆 2.自律的な選択力
1.親の関わりに安心感 2.生活リズムへの理解
1.勉強への興味と導入体験 2.学習モチベーションの自発化
1.禁止だけの圧力を減らす 2.親の声に柔軟に応える姿勢へ
締めの言葉
「SNSや動画ばかり見ていて勉強しない。それは"やる気のスイッチが見つからない"サインです。禁止ではなく、親子で選べるルールと代わりになる時間をつくり、共に切り替える習慣を育むとき、子どもの心が自然と学びへ向き始めます。」 一気に見せなくするのではなく、小さな選択を積み上げて、学びのリズムを作ること。親子で挑戦し、振り返り、気づき合う家庭は、やがて勉強への自信と意欲を自然に育んでいきます。 親子で共に学びとSNSの使い方を育み、未来への力を育てていきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月11日 13:57
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ179
1.「教えられない...」と感じる理由とは?
1.専門用語や新しい教科内容のギャップ
算数・理科・英語の新単元は親世代と違う教え方がされており、親が戸惑うきっかけになります。
2.学力不足や教え方の不安による罪悪感
「昔やっていたから大丈夫」と思っても、教え方が分からないと、親自身の無力感に襲われます。
3.親の焦りが子どもに伝わり、学習意欲が削がれる
親が不安を露わにすると、子どもの成長意欲も萎えてしまう可能性があります
2. 教えられない不安を安心へ変える5つのアプローチ
1. 親も一緒に「学びのプロセス」を子どもに見せる
解けない問題を前に、「一緒に調べよう」と姿を見せる。調べる→理解するという工程を見せることで、子どもは「学ぶとはこういうことか」と体感できます。
2. 小さな成功体験を一緒に作る
「分からない」を「分かった!」に変えるまでの過程を、親子で共有しましょう。計算や漢字の一文字でも、「できた!」の積み重ねが自信になります。
3.教科書・参考書・動画などの使い分けを学ぶ
親が一緒に辞書や参考書を引いたり、YouTubeや学習アプリを活用して探索する姿勢を示すと、子どもは自分で学べる力を育てます
4.「質問力」を育む声かけ
問題だけでなく「どうしてそう思ったの?」や「他に調べられる方法はある?」と問いかける。考える習慣が学びの根幹になります。
5. 第三者の力を借りる
選択肢も積極的に 学びの補助が得られる場を利用することで、親子だけで不安を抱え込まずに済みます
3.実践例:「分数の割り算」が苦手な小学5年生
1.親がチャレンジ姿を見せる → 「お母さんも忘れちゃったから一緒に調べるね!」
2.調べながら探索する時間にする → 参考書で基本公式を確認し、サンプル問題を親子で解く
3.「できた!」を両方で祝う → 「最後までできたね!」と心からの共感を伝える
4.子どもが説明できるように促す → 「じゃあ、なんでこうなるか教えてみて?」
5.次への練習設定 → 翌日は「分数のかけ算」「分数での文章問題」に挑戦する
4. 親の学びを通じて開ける子どもの可能性
1.アプローチ 2.子どもに育つ力
1.親も一緒に調べる姿勢 2.自分で調べる学びの習慣が育つ
1.小さな成功の積み重ね 2.自信とやる気が自然に育まれる
1.質問力を育む対話 2.深く考える力と思考力が伸びる
1.学びのパートナーがいる安心感 2.親子の信頼関係が強まる
1.第三者の活用 2.子どもの可能性と親の安心が広がる
締めの言葉
「親の学力では教えられない」と感じたとき、それは"次の成長へのチャンス"。親が一緒に調べ、失敗し、考える姿を子どもに見せることで、"自分で学ぶ力"を育む教育が始まります。第三者の助けも必要なら遠慮せずに活用しながら、共に歩む姿が親子双方の未来を確かなものにしていくのです。」 教えられないことは恥ずかしいことではありません。それに直面した親が、学ぶ姿勢を示すとき----そこには"最良の学び"が始まります。 学び合い、信頼し合いながら、親子で未来への一歩を踏み出しましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月10日 14:23
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ178
1.なぜ「テストの点数にショック」を受けるのか?
1.点数は見えやすい評価の象徴 家での努力や一生懸命さは目に見えにくいですが、テストの点数は「結果という数字」で明示され、親にとって胸が締めつけられる反応を呼びやすいものです。
2.学年の伸び期待とギャップの誤差 小学生の成績は「前回との比較で伸びてほしい」という期待とセットですが、伸び悩むと「うちはダメかも...」と落ち込んでしまうこともあります。
3.親自身の不安・焦りが重なると影響が倍加 「うちの子は他の子より遅れているのでは...」。そのような親自身の不安が内面化すると、点数の低さが「家庭の責任」に感じられるのです。
2.ショックを受けた後、まず取るべき5つのステップ
1. 一呼吸置く時間をつくる 点数を見た瞬間は誰でも動揺します。まずは言葉を控え、深呼吸し「夜はゆっくり話そう」と自分に時間を決めましょう。
2.感想を受け止める声かけ 「思ったより取れてなかったね?」と共感し、決して否定しない姿勢で対話を始めます。点数だけで判断しない態度が安心感を生みます。
3.点数より背景を聞く質問 「どこが難しかった?」「時間は足りた?」「気持ちはどうだった?」と、子どもの内面に焦点を当てる質問で本音を引き出します。
4. 気づきの整理と改善プラン 子どもと一緒に「ここは分かっていて、ここが難しかった」という振り返りを図にするなど、学習の課題を可視化し、次の計画を立てます。
5.小さな成功を共に喜ぶ 次の家庭学習のとき、小さな改善(漢字2問正解・10分早く読み終わったなど)に親が敏感に気づき、褒めることでリズムが生まれていきます。
実践例:「国語のテストで60点中30点だった」
1.ステップ 2.親の対応 3.効果
1. 夜に呼吸 2.一晩寝かせてから話す 3.イライラやショックが和らぐ
1. 共感 2.「今日はしんどい気持ちだった?」 3.子どもが安心して話せる
1. 背景を聴く 2.「記号問題は簡単だった?」「長文で分からなかった?」 3.問題の構造が見える
1.可視化 2.「読解はOKで、文法が苦手か」と表にまとめる 3.学ぶポイントが明確になる
1.小さな改善を認める 2.「今日は文法ドリル5分やったね!」 3.励みと自信が回復する
この一連の対応で育つ親子の信頼と成長
1.対応要素 2.子どもへの効果 3.親自身の変化
1.共感聞き取り 2.安心して自己表現できる 3.親子の対話が豊かになる
1.学習の見える化 2.どう学ぶかが明確になる 3.学びを支える方向が見える
1.小さな成長の共有 2.自信が育ち、次のやる気につながる 3.子育ての手応えを感じる
1.ショックへの関わり方 2.感情への圧迫が減り安心感が育つ 3.親も焦りすぎずに寄り添える
締めの言葉
「テストの点数は"SOSの合図"。親がまずは値ではなく、言葉の向こうにある気持ちを受け止め、背景を知り、共に振り返り、次の『できた』に気づければ、その点数はやがて成長の礎に変わります。」 低い点数にショックを受けることは自然です。でもそれが、親子の"新しい学びの入り口"にもなり得ます。点数を基準にせず、対話を通じて子どもの声を聴き、リズムと自信を取り戻せる「伴走」の時間に変えていきましょう。 ショックが実になる学びへの一歩を、親子で踏み出していきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ!
(毎日個別学習Smile) 2025年7月 9日 13:15
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。