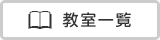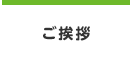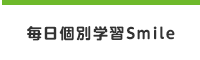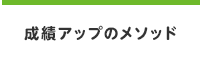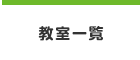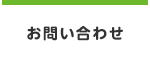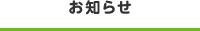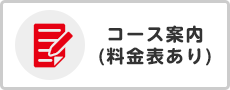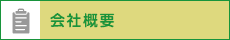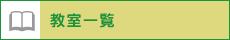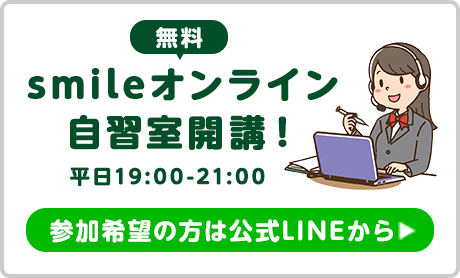月別 アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (14)
- 2025年7月 (30)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
スクールブログ 4ページ目
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ204
1.なぜ「塾に通っていても自習しない」のか?
1.自習への明確な構造がない通塾しているだけで、家庭での「何をやるか」「いつやるか」が明確になっていないと、自主的な学習習慣は生まれません。
2.誘惑が強く習慣化しづらい 家ではゲームやスマホ、テレビなど誘惑が多く、集中すべき学習時間が流れてしまいがちです。
3.目的や振り返りが見えない 「塾に行くだけで安心」という認識では、努力や達成感が伴わず、主体的な学習マインドが育ちにくい傾向があります。
2.親ができる「塾効果を最大化する自習支援」5つのステップ
① 自宅学習の習慣を「仕組み化」する 塾での内容を踏まえ「帰宅後30分間は自習する」と具体的なルールを家族で共有しましょう。 目的:習慣化と習得リズムをつくる。
② 自習内容を「見える化」して計画する ノートやToDoアプリを使って、「今日は数学の復習10問」「英単語15個」など具体的に記入し、チェックできると習慣化に繋がります。 目的:何をすべきかが明確になる。
③ 自習の場を「塾の自習室」も活用させる 塾の自習室は誘惑が少なく、集中しやすい環境ですし、講師にすぐ質問できるのも大きなメリットです 目的:学習効率と集中を引き出す環境づくり。
④ 「振り返りと承認」の習慣を入れる 毎日自習後に少し声をかけ、「よくやったね」と肯定する時間を設けると、継続意欲が自然に高まります 目的:自己肯定感を育て、自主性をサポート。
⑤ 長期計画で「少しずつ進む感」を育てる 塾と家庭を連携させて、「いつまでに何を完成させるか」中長期のスケジュールを見直しながら進めましょう 目的:目標意識と満足感を形成。
3.実践例:中1女子の"塾通いだけ生活"からステップアップモデル ステップ 実施内容 狙い
① 自習ルール 塾後20分自習+スマホは別部屋へ 生活リズムの定着
② 見えるToDo 「数学プリントP4」「英単語15個」などを記録 やるべきことの自覚
③ 自習室利用 塾の自習室を週2回活用 集中力が明らかに上がる
④ 承認タイム 「今日も頑張ったね」と声かけ 子どもも「続けよう」と思える
⑤ 振り返り予定 週末に「できたこと」共有 小さな成功の積み重ね
4.続けることで育つ力と親の安心
1.支援方法 子どもに育つ力 親の安心感
2.習慣の構造化 自主学習力とリズム 教えなくても動く姿を見る安心
3.チェック記録 自制心と計画力 頑張りが目で見える安心感
4.自習室利用 集中力と理解力 物理的な場の変化で安心
5.承認の言葉 自信と継続モチベーション わずかな成長が嬉しい安心
6.振り返り計画化 目標管理と達成実感 親子の協働感が深まる安心 締めの言葉 「塾に行くだけで安心してしまうのではなく、家庭での"自習する習慣"があって初めて、その意義が最大化します。計画と環境、承認を親が整えることで、子どもは自然に勉強を自分のものにしていきます。親子で自習のリズムを育て、安心と自信を積み重ねる時間を共に築いていきましょう。」 塾はスタート地点です。その先にある"自分で学ぶ習慣"を育てるのが、今、親ができる最高の支援かもしれません。
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 8日 12:47
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ204
1.なぜ「部活動が忙しくて勉強できない」のか?
1.時間が足りない...でも習慣はつくれる
2.部活動に追われ、帰宅が遅い中学生も多く、「勉強時間が確保できない」と嘆く声も多いです。しかし戦略的に隙間時間を活用することで、習慣はしっかり築けます
2.生活リズムが整っていないと負のスパイラルに 睡眠不足や夕食・入浴のリズムが不安定では、勉強への意欲も低下します。部活と勉強を両立するには、まず規則正しい生活が土台に必要です
3.目的意識が曖昧だと効率にムダが増えやすい 「部活が好きだから頑張りたい」「どこまで目指すか」で優先順位が変わります。目的を明確にすることで、時間とエネルギーの使い道に気づきが生まれます
4.部活と勉強を両立させる5つの実践ステップ
① スキマ時間のデザイン 通学中、着替え待ち、休憩時間--こうした「小さな空白」に、暗記や見直しを入れる習慣を取り入れます
② 短時間集中学習(20分ルール) 帰宅後すぐの「短時間集中勉強」から始め、徐々に時間を延ばしていくと疲れも少なく効果的です
③ 生活リズムの整備 夕食・入浴・勉強の時間帯を毎日ほぼ同じにすることで、勉強が"当然の時間"として定着します
④ 目的を共有し、役割意識を育てる 部活の目的やゴールを一緒に話すことで、勉強の必要性も納得した形で受け入れられ、自律を促します
⑤ 計画の可視化と振り返り 「部活後の23時までに◯◯を済ませる」など、計画を「見える化」し、翌日に実行できたことを振り返る習慣をつくります
5.実践例:中2/サッカー部の娘の1日のスケジュール案 時間帯 内容 狙い
1.17:00-18:00 通学・軽食(英単語暗記) スキマ時間の学びを習慣に
2.18:30-20:00 部活 熱中力と体力を培う時間
3.20:30-20:50 帰宅後すぐ短勉(20分) 疲れていても集中できる訓練
4.21:00-21:30 家族夕食&入浴 生活リズムの統一
5.21:40-22:00 今日の振り返りノート記入 自己管理と達成感の強化
6.日々継続することで生まれる変化
実践項目 子どもに育つ力 親に得られる安心
1.スキマ時間活用 自主的な学びの習慣 日々の成長が見えてくる
2.20分集中 集中継続力と達成感 「やったね」が自然に言える
3.生活リズム定着 睡眠・体調の安定 心身の健康の安心感
4.目的共有 自律と意志決定力 一緒に目指す関係が育つ
5.可視化+振り返り 自己調整と計画力 成果を実感できる喜び
締めの言葉
「『部活が忙しくて勉強できない』は、やる気ではなく"時間と仕組みのギャップ"。情熱を持って走る子ほど、戦略的に時間を整えると自ら学ぶ力が目覚めます。親子で時間の設計者となり、部活でも勉強でも主体的に輝く毎日を築いていきましょう。」 部活による成長と学びが共鳴する生活。それは「戦略×時間×親子の信頼」があってこそ築けるものです。どうか焦らず、少しずつ歩んでいきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 8日 12:20
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ203
1.なぜ現代の中学生はゲーム・SNSに夢中になるのか?
理由①:スマホ/ゲームの設計が強く学習を上回る
中高生の約7割が週に1回以上スマホゲームをプレイしている(1〜3時間/日)という調査があります。これは、ゲームやSNSが即時的な報酬や仲間との交流を提供し、勉強よりも遥かに魅力的に設計されているからです
理由②:禁止ではなく、親子対話と共感が効果的
単に禁止をすると、反発や隠れプレイに繋がることも。専門家は、「禁止するよりも子どもの気持ちに共感し、話し合いで制限ルールを作ることが健全だ」と提案しています
理由③:ゲーム以外に夢中になれる場がない
多くの中学生は「ゲーム以外に熱中できる趣味がない」「やることがない」ため、自然とゲームに時間が偏る傾向があります
2.親ができる「学びと遊びのバランス」5つのステップ
1.共感的な対話から始める
まず「そのゲーム楽しそうだね」「友達とつながるのが楽しいんだね」と語りかけ、子どもの感情を受け止めた上で、「でもちょっと心配なんだよ」と話し始めましょう。信頼関係が生まれ、対話の土台が築かれます
2.境界と許容を一緒に決める
「勉強30分したら15分ゲーム」「通知オフにしてから学習スタート」など、子どもと一緒にルールを決めて、自律を促す仕組みを整えます
3.代替時間・楽しい学びの選択肢を提示する
スマホを触らない代わりに、本やパズル、家族との会話、自習系アプリ(例:音声付き英語バトルアプリなど)を選べるように環境を整えましょう
4. スマホ物理的隔離と通知オフの環境設計
勉強中はスマホを別の部屋、通知もオフにして、そもそも誘惑を視界に入れない環境をつくります。机の上には文具と水のみの整理が効果的です
5. 自主性の仕組みと承認の声かけルーチン
週末に「守れたルール」を振り返り、子ども自身の意見を聞きながら改善する時間を設けることで、やる気と信頼感が育ちます。守れたら「よくやったね」と肯定的に伝えることも重要です
3.実践例:中1男子の「ゲームばかりで勉強しない」を変える3日間導入モデル ステップ 親のアクション 子どもの反応・変化
① 対話から開始
「そのゲーム、どう面白い?」と会話始め 親子の心がちょっと近づく
② ルール決め
「夜7時までゲームOKで、その後30分勉強ね」 子どもも納得しルールを受け入れやすい
③ 代替提案
「勉強後にアプリで語学バトルもあるよ」 学びも遊びのように感じ、興味が湧く
④ 環境整備 勉強部屋にスマホ持ち込まず通知オフに設定
集中時に画面を見ない習慣化が進む
⑤ 承認ルーチン
「勉強後に話せて嬉しかったよ」と夜に声かけ 自己肯定感が育ち、翌日も続けやすい
4. 続けることで育つ習慣と家庭の安心感
1.親の取り組み 子どもに育つ力 親が得られる安心
2.共感と対話 自己認識と信頼関係 子どもへの理解が深まる
3.合意したルール 自律と選択の意識 言うだけではなく納得で進む安心
4.代替活動の提供 多様な興味と気分転換力 勉強も遊びも受け入れられる雰囲気
5.スマホ隔離と通知管理 集中習慣と注意力 親が過剰に干渉せず運用できる安心
6.振り返りタームと褒め言葉 継続力と達成感 日々の成長を親も実感できる
締めの言葉
「ゲームやSNSに夢中な姿は、"子どもの声"を伝えているサインかもしれません。禁止や取り上げではなく、まずは共感と選択肢の設計から始めましょう。ルールと代替活動、承認の声かけで、親子で作る"学びと遊びのバランス"は確実に育っていきます。信頼と行動を共にデザインしていきましょう。」 ゲームやSNSは、中学生の学びを妨げる敵ではなく、上手に付き合うことで"自律の練習場"にもなります。親子で歩み寄り、小さな変化を積み重ねていくことで、やがて学ぶ時間も自然に選ばれるようになるでしょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 6日 11:54
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ203
1.なぜスマホばかり触ってしまうのか?
理由①:スマホの刺激と依存構造
スマスマートフォンの通知やSNSは即時報酬と強い刺激を与え、集中を妨げる大きな要因に。これが習慣化すると、勉強への意欲をそぐ原因になります
理由②:何度注意されても「やめなさい」では変わらない
親が親が叱るだけでは子の行動は変わらず、逆に反発や関係性の緊張を生むこともあります。持続的な改善には、信頼と自主性を促す工夫が不可欠です
理由③:ルールや代替行動がないまま自由時間が広がる
スマホスマホ使用時間に上限や代替行動が設定されていないと、つい触ってしまう環境になりがちです。生活ルールや趣味・運動の時間が限られていると、依存が加速します
2.スマホ依存を改善する親の関わり方5選
① 【ルールと選択肢を設ける】
「勉強タイ「勉強タイム中は別の部屋に置く」「スマホオン時間を1時間まで」など物理的&心理的境界を設定し、選択肢と明確な許容を整えます
② 【代替行動を一緒に探す】
「スマホ使「スマホ使う代わりに親と20分一緒に本を読む」「軽く散歩」など、スマホ以外の活動に目を向ける時間を提案しましょう
③ 【スマホを物理的に遠ざける】
ポケットやポケットや机の外、別の部屋に置く・電源を切る・ゴムバンドで操作を阻めるなど、心理的に"触りたくても触れない"環境を整えます
④ 【自主性を促す約束と見直しの仕組み】
親子で「こ親子で「このルールでやってみよう」と合意し、週単位で守れているか確認・改善する仕組みを作ることで、自律性が育ちます
⑤ 【肯定と振り返りの声かけ】
「スマホ触「スマホ触らずに1時間やってみたね」「その集中、素晴らしいよ」と声かけしていくと、行動そのものへ意欲が持続されます
3.実践例:中1男子の「スマホばかり触る」家庭での改善モデル ステップ 親の対応 子どもの反応・変化
① スマホ隔離 勉強タイム中、スマホは別室に 学習中の誘惑が減り集中できる
② 代替時間設定 30分勉強→5分外遊び or 読書 スマホ以外の楽しみが見つかる
③ 境界と合意 「夜8時以降は親部屋で充電ね」 子どもも納得感を持って守るように
④ 見直しルーチン 毎週末にルールを振り返る 守れたら「ステッカー」など効果的
⑤ 承認声かけ 「頑張って続いたね」を言葉に 自信と次回への意欲につながる
4.続けることで育つ力と家庭の安心感
1.親の工夫 子どもに育つ力 親に得られる安心
2.境界設定と選択肢提示 自律的判断と制御力 指示ではなく自主性が育つ安心感
3.代替行動設計 他の楽しみや習慣 スマホ以外の魅力が見つかる
4.物理的な距離を設ける 注意力の持続と集中力 親の負担軽減/勉強時間確保
5.定期的な振り返り 自己管理力と責任感 ルールが進歩基準になる
6.承認と振り返り 自己肯定と継続意欲 親子関係の信頼強化
締めの言葉
「スマホばかり触る姿を叱るだけでは、子どもの心と行動は動きません。境界と代替、合意と見直し、肯定の声かけを通じて、学ぶ時間とスマホのリズムを親子で整えれば、学びへのスイッチは必ず入ります。親子でデジタルと学びのバランスを共にデザインしていきましょう。」 スマホ依存は性格ではなく、習慣と設計の問題。適切な構造と支援があれば、集中できる力は誰でも取り戻せるのです。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 5日 11:47
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ202
1. なぜ家でダラダラするのか? 背景と理解を深めよう
理由①:集中力や習慣形成が未成熟
思春期の集中力は未だ安定しておらず、始めるまでの「スイッチ」がないと行動に移せない子も多いです
理由②:親がその"ダラダラ行動"にばかり注目してしまいがち
不快な行動に注目するほど悪循環になります。不満視する代わりに、親自身が行動のきっかけを作って離れる姿勢が逆効果を避けるカギです
理由③:生活リズムや計画が整っていない
多くの中学生は「計画通りに夏休みを過ごせていない」現状で、生活のメリハリや計画的な時間割がなければ、ダラダラが続きやすい傾向です
2.ダラダラから動き出す5つのポイント
1. 親自身が動くことで子どもの行動を促す
「あなたが動いてくれるなら」と期待されたり、「親が離れることでさみしくて動いた」という子も。まずは親がちょっと離れて行動することも有効です
2.『集中の筋トレ』として短時間集中スタート
最初は1〜5分だけ机に向かってみる「短く始める」方式で、集中力のきっかけをつくります。それが継続の鍵になります
3. 勉強や片づけなどにも"意味や目標"を提示する
ただ「やりなさい」ではなく、「これをやると●●がスッキリする」「終わったら一緒に歩こう」と意味を伝えることで、意欲が芽生えやすくなります
4.肯定的な声かけで承認を与える
「座っただけでいいよ」「片づけしてくれて助かったよ」と、努力や意思を軽く肯定することで、前向きな行動が生まれます
5. ルールを親子で作って話し合い・見直しをする
「ダラダラしすぎない」「ゲームは1時間だけ」「片づけタイムを16時にとる」など、子どもが納得できるルールを一緒に作れば、実行性も高まります
3. 実践例:夏休み中にダラダラしがちな中1息子へのアプローチ ステップ 親のアクション 子どもの反応・変化
① 自分から離れる
「ママは買い物行ってくるね」と声かけして外出「じゃあ自分で昼ご飯作ってみる?」という行動に変化
② 短集中チャレンジ
「まずは5分だけ勉強してみよう」とタイマー設定 やれた達成感から次も始めやすくなる
③ 意味や時間を伝える
「終わったらゲーム時間にしようか」と約束 集中への動機が生まれる
④ 軽い承認
「5分やってえらいね」「集中してたね」と声かけ 自分でも「やってよかった」と感じる習慣に
⑤ ルール提示
「夕方は15分勉強タイムを共にするね」と提案 親子ルールが納得感を生み、自然に実践へつながる
4. 続けることで育つ家庭と子どもの成長
1.行動の工夫 育まれる力 親の安心感
2.親が先に動く 自立意識と行動のきっかけ力 子どもの行動に焦りが減る
3.短い時間から始める 集中筋と自己達成感の習慣 小さな一歩でも変化が見える
4.意味のある声かけ 自発力と納得感 声かけが柔らかくなる
5.承認言葉 自己肯定感と安心感 親との信頼関係が育つ
6.ルール作成と見直し 自律と責任感 家族ルールとして共に成長する
締めの言葉
「家でダラダラする姿が続くと心配ですが、それは"今の心地よい空間"がまだ動くスイッチを持っていないから。親がちょっと行動を変え、スイッチを仕掛け、小さな成功と承認の空気を作れば、子どもの心にも自然と動きが生まれます。親子で暮らしのメリハリを少しずつ整え、学ぶ・動くリズムを育んでいきましょう。」 ダラダラは思春期に自然な一時ですが、それをメリハリあるリズムへと親子で揺さぶることができれば、小さな一歩が未来につながります。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 4日 11:42
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ201
1.なぜ「テスト前しか勉強しない」のか?
理由①:短期詰め込みが効率的に見える
実は「テスト前に一夜漬けすればいい」と感じているのは、エビングハウスの忘却曲線理論では非効率とされます。短期記憶の維持には限界があり、実践的な定着には日々の復習が不可欠です
理由②:学びの方法や意味が曖昧で日常につながらない
「テストのため」という目的だけだと、やる気の種が育ちません。日々の学びが未来につながる意味や目標を子ども自身が見いだせれば、自律的な行動へ変わります
理由③:部活・スマホ・疲労で日々の学習が後回し
日常生活に誘惑や疲れが多く、勉強が後回しになりやすい状態が「テスト前だけ勉強」のリズムを作っています
2.毎日の学びを自然にするための5つの工夫
1.テスト前ではなく"1日10分の積み重ね"をQRルーチン化
短時間日課(たとえばリビングで10分間の英語単語暗記や計算ドリル)は、義務感なく習慣化でき、小さな達成を積み上げていく起点になります
2. 使用科目ごとToDo+完了チェック表で進捗可視化
「英語:単語15個」「数学:問題集2ページ」など科目ごとにやることを書き出し、チェックして記録することで、一日一日の積み重ね感が自分で確認できます
3.家族共習タイムを導入する
親が自分の書類整理や読書をしながら一緒に机に向かう"共習"スタイルを作ることで、学習空間そのものに親子のリズムが根付きます
4.テスト以外の小テストを活用する(エラー駆動学習)
定期的に小さな確認テスト(口頭でも可)を挟むことで間違いから学べる"フィードバック型学び体験"が生まれ、自律的に学ぶ意識が高まります
5.親の承認と振り返りルーチンを設置する
「今日はここまでできたね」「継続して取り組めたね」といった声かけで、「やることそのもの」が評価される環境をつくると、習慣化を心地よく支えます
実践例:中1男子の「テスト前しか勉強しない」からの脱却プラン 時期 内容 ねらい
1.日常(平日) 毎日夜8時に10分だけ単語暗記or計算ドリル自分で始める習慣づくり
2.毎週末 英・数どちらかの小テストを実施 定期的な振り返りと課題発見
3.ToDoチェック 毎日やる内容をリスト化&✅付け 自分の進捗を可視化し動機維持
4.家族共習タイム 妹と親が同時に同じ机で勉強時間確保 孤独感の撲滅と共感の場作り
5.振り返り声かけ 「ほんの10分でも続けたね」と毎夜褒める 自己肯定感が継続の力になる
4. 続けることで育つ子どもの習慣と家庭の安心感
1.親の支援スタイル 育つ子どもの力 親が得る安心
2.小さな習慣の設計 習慣化力/継続への安心感 親が口出ししなくても進める姿が見える
3.目標とToDoの明確化 計画力/責任感 無駄な問いかけが減り対話がやさしくなる
4.共習時間の場作り 集中と安心の居場所感 学びの時間を共に楽しめる余裕
5.確認小テストの実施 ミスから学ぶ力/記憶定着 テスト前の焦りが減り得点改善へ
6.振り返り・褒め習慣 自己肯定感/やる気持続 子どもの前向きな変化が親の安心に
締めの言葉
「"テスト前だけ勉強して楽だ"という子どもも多いですが、短期記憶はすぐ抜け落ち、長期的には負担と不安になります。定期的な小さな積み重ねを自然な習慣に変えることで、勉強は『テストのため』ではなく『自分を育てる手段』に変わります。親子で学びの日常を設計し、安心と成績の向上を共に育んでいきましょう。」 テスト前だけではなく、日常が学びの場になるとき、子どもの自律とやる気は自然に育っていきます。焦らず、親子で少しずつ積み重ねを始めていきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 3日 12:49
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ200
1.なぜ「全くやる気が出ない」のか?親が理解すべき理由
理由①:目的や達成感が感じられない
多くの中学生が「何のために勉強しているのか分からない」と感じています。それでは、やる気が芽生えるわけがありません。親が子どもの興味や未来の可能性に寄り添って、意味づけをしてあげることが必要です
理由②:勉強のやり方や教材のレベルが合っていない
「難しすぎる」「方法が分からない」となると、勉強自体を避けたくなります。学力に合った教材や正しい学習法を見つけることが、やる気を育てる第一歩です
理由③:疲労や生活習慣が整っていない
部活や夜ふかし、スマホ時間の影響で疲れていると、学びに向かう余力がありません。生活リズムや睡眠の質も見直すべき重要な要素です
2.親ができる「やる気を育む5つの関わり方」
1.小さな成功体験を設計する
「今日、英単語3つ覚える」「数学の問題2問やってみる」など、誰でもできる範囲の目標を設定し、「やったね!」と声かけ。自信の蓄積が気持ちを動かします
2. 目的と意味を一緒に考える
「勉強=何かに役立つ」ではなく、本人の好奇心や将来への希望につながる話をすることが原動力になります
3.ルーティーンと環境を整備する
「夜ご飯後すぐに机に向かう」「スマホは別室」「照明、イスの高さを調整」など、学習への心理的・物理的ハードルを下げる工夫が効果的です 4.生活リズムを整える
十分な睡眠とバランスの良い食習慣、部活との両立バランスを親子で一緒に設計することで、学習への体力と意欲が整います
5. 親が共に学ぶ姿勢を見せる
親自身も読書や調べものなど「学ぶ姿」を見せることで、勉強が"親子で共に続ける時間"になります。孤立感が和らぎ、取り組みやすくなります
3.実践例:中学生でやる気が見られないケースへの3日間プラン 日/ステップ 実施内容 子どもに育つ力
Day1:28日
①「英単語3つ覚える」②リビングで共習30分 成功体験と安心感
Day2:29日
①「計算2問」②学習環境を整理③一緒に資料を読む 集中習慣の始まり
Day3:30日
①「国語読解1問」②振り返り:「できた点」を共有 自己を肯定し、次へ動ける心
4.続けることで育つ親子の関係と成長
1.親の関わり方
子どもに育つ力 親の安心と期待
2.小さな目標設定
「自分にもできる」が芽生える 子どもを見る目が変わる
3.意味を話す
「将来が自分ごとになる力」 親子の対話が自然に深まる
4.家の環境整備
集中しやすい習慣 無理なく継続できる仕掛けに
5.リズム見直し
学びに向かう体力・意欲 生活改善への光が見える
6.共に取り組む
孤独でなく共に歩む姿勢 子との信頼と安心が育つ
締めの言葉
「やる気が全く見えない子どもは、種を植える前の土壌かもしれません。焦らず、小さな成功と環境づくり、意味づけと共習。親がそっと導線を整えていくことで、子どもの中に小さな芽が芽吹きます。親子で学ぶ仕組みと心の土台を一緒に育てていきましょう。」
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル) "やる気"は押し付けるものではなく、育てるもの。親がデザイナーとなって、子どもが自分で動く「学びの場」を整えていけば、信頼と可能性に満ちた習慣が生まれていきます。
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 3日 12:37
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ199
1. なぜ"勉強習慣がない"のか?
1. 中学生の家庭では約9割の親が関与しているという現実
調査によれば、定期テスト対策に関与する親は88%にも上り、その多くは「習慣づくり」を意識していますが、子どもの自律につなげる難しさを感じていることがわかっています
2.部活・SNS・疲労など学習が後回しになりやすい学生生活
部活動やSNSへの誘惑、日々の疲れで「いつ勉強したらいいのかわからない」という声も多く、習慣がそもそも定まっていないケースが目立ちます
3. 自主性と習慣化は親の声かけ次第
専門書でも「勉強習慣は親の声かけで9割が決まる」とし、声かけの内容やタイミングが習慣化に大きく影響するとの知見があります
2.習慣を育てる親の関わり5ステップ
1. 小さな「30分学習+休憩」
ポモドーロ式を導入する 集中したいときは、30分集中+5-10分休憩のリズムを家庭で取り入れることで、学習が身近になりスタートが楽になります
2.教科ごとにToDoリストを作り、見える化する
「英語:ワークページ24〜26」「数学:問題集P17奇数」など、科目ごとにやるべきことを整理すると、目標が明確になり習慣化しやすくなります
3. 親子で一緒に学習する「共習タイム」を設ける
親が自分の読書や資料整理をする姿を見せながら、一緒に机に向かう"共習タイム"を設けると、子どもも自然に学ぶリズムをつかみます
4. AI教材やアプリで「自律型の学習」を促す
AIによる個別指導教材や学習アプリを導入すると、親が声かけしなくても子どもが取り組める仕組みが作れ、学習習慣を支える基盤になります 5.振り返りと称賛の声かけルーチンを作る
毎日「今日やれたこと」「どう感じたか」を振り返らせ、「がんばってたね」「集中してたね」と承認する習慣を取り入れると、やる気が継続します
3. 実践例:習慣がない中1のための具体プラン ステップ 実施内容 得られる力
① 初動設計 「放課後6時〜6時半ポモドーロ学習」 取りかかりやすいルーチン
② ToDo作成 ワーク科目×ページで計画表作成 自分でやることを選びやすく
③ 共習タイム 親も隣で資料読むなどして20分共に勉強 子どもが自然に集中状態へ入れる
④ AI教材利用 AI英語・数学アプリを1セッション 自律的な学び力の育成
⑤ 振り返り声かけ 夜「今日はどうだった?」で褒める 自己肯定感と学習の継続力向上
4. 続けることで育つもの・家庭の変化
1.親の関わり 子どもに育つ力 親の安心と成長
2.予定を決めて支援 自分で始める力 親が誘導しすぎず見守れる余裕
3.ToDo見える化 計画力・責任感 指示より対話が自然に
4.共習体験 自律的集中と安心感 家庭に学びの空気が定着
5.AI導入 自主性と成果の可視化 教える負担の軽減
6.振り返りルーチン 達成感と継続性 親子の信頼と成長実感形成
締めの言葉
「"勉強する習慣がない"と思っているなら、まずは習慣が生まれる"仕組みづくりのチャンス"です。ポモドーロ、ToDo、共習タイム、AIと振り返り──これらを親子で設計することで、習慣は自然に形になります。中学生という大事な時期に、学ぶ力と自ら動く力を一緒に育てていきましょう。」 学習習慣とは、親子で築くリズムです。今からでも遅くありません。設計と関わり方で、子どもの自律と可能性は必ず育っていきます。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 1日 13:00
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ199
1.なぜ子どもは「勉強を楽しめない」と感じるのか?
理由①:つまらない・強制感・無意味
東洋経済の記事では、子どもが勉強嫌いになる原因として「つまらないから」「親の強制」「非効率な学習スタイル」が挙げられており、これらが勉強意欲を削ぎます
理由②:勉強の方法が分からない
学習方法や計画がわからないことで、「何をすればいいか」迷い、結果として楽しさどころか始めることさえ難しくなる傾向があります
理由③:好奇心が育まれていない
教育評論家によれば、子どもの好奇心や没頭力を引き出すことが、苦手意識や学ぶ楽しさを克服する鍵だとされています
2.勉強を楽しみに変える5つのステップ
1.興味のある方式・テーマを選ばせる(選択型学び)
「漢字を書く? 算数動画を先に見る?」「自由研究をテーマにする?」と選択肢を与え、主体性と好奇心を刺激します
2.簡単な問題から始めて"できた喜び"を積み重ねる
取組みやすい問題から始めて成功体験を重ねることで、やる気が徐々に育ち、難しい学習にも自信を持って踏み出せます
3. ゲームやアプリを活用して学びを"楽しい体験化"する
タブレット教材やアプリ、キャラクター付きドリルを使うことで、学びを遊び感覚にする工夫が有効です
4.家族と一緒に「共習タイム」を設定する
親子や兄弟姉妹で同時に机に向かい学ぶ時間を作ることで、「自分だけではない」「頑張る姿を見られる安心感」が生まれ、集中力アップにつながります
5. 成果より「挑戦した姿勢」を褒める声かけ習慣
点数ではなく「やってみたこと」に焦点をあてて褒めることで、「勉強する行動そのもの」がポジティブに評価され、継続意欲が育ちます
3.実践例:小学3年生向け「学ぶ楽しさを取り戻す」モデル ステップ 内容 効果
① 興味選択
好きな科目やコンテンツから学びスタート興味を起点にやる気になる
② 成功体験設計
漢字1字、計算2問など少量で達成感 自信と継続意欲が芽生える
③ アプリ利用
勉強系アプリで1回数分集中学習 楽しさと学習内容の習慣化
④ 共習タイム
家族全員で20分学びタイム設定 親子の空気感と学びの共有
⑤ 挑戦を褒める
「よく聞いていたね」「最後までやったね」と声かけ やること自体が褒められる体験形成
4.継続すると見える未来
1.親の工夫 子どもに育つ力 親に生まれる安心
2.選択肢から始める学び 好奇心と主体性 学びの関心が見える
3.小さな成功設計 自己効力感と継続力 子どもの成長が具体化
4.ゲーム学習活用 楽しみながら習得できる力 工夫する楽しさと結果
5.家族共習時間 孤立せず共に進む安心感 家庭が学びの居場所に
6.挑戦を肯定する声かけ 挫折を恐れない心 やる行動への信頼感
締めの言葉
「"勉強は楽しい"とは、一部の天才だけの特権ではありません。学びを"自分事にする工夫""楽しさのデザイン""挑戦を認める心"があれば、誰でも学ぶことの面白さを感じられます。勉強が"挑戦であり遊びであり自信になる瞬間"へと親子で変えていきましょう。」 勉強が楽しくなる日は、親が学びの"設計者"になることで始まります。知識以上に、好奇心を育てる関わりを持てば、子どもは学ぶことを心から楽しめるようになるでしょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年8月 1日 12:52
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ198
1.なぜ問題の読み間違いが起きるのか?
1.「慎重」のイメージと本人の感覚にズレがある
子ども自身は「ちゃんと読んでいるつもり」でも、親や教師の"丁寧・慎重"の基準と大きくずれていることがあります。「しっかり読む」だけでは伝わらない理由です
2.焦りや時間プレッシャーによる不注意
テスト中の焦りや時間不足の意識から、確認動作が甘くなり、読み間違いや見落としが起こりやすくなります
3. 習慣としての「読む動作」が未定着
問題を読む習慣が定まっていないと、条件や設問を飛ばして解いてしまい、読み間違いの要因になります。まだ精読の利点を実感していない子も多いのです
2.読み間違いを防ぎ、正答へ導く5つのステップ
1. 指差しや線引きなどの「読む動作」を習慣化する
設問や条件、求める内容に鉛筆で線を引く「指差し呼称」方式を導入しましょう。読む→指差す→理解するという動作が、自動的にミスを防ぎます
2.声に出して読む音読チェックを取り入れる
特に読解問題や理科・算数の文章題では、音読によって自分の読み方に気づきやすくなります。黙読よりも思考の速度が追いつきやすい利点があります
3. テスト演習中も「確認専用時間」を設ける
時間配分に余裕がある場合、最後の2〜3分を"読み返しタイム"として専用に確保。ミス率を下げる仕組み作りです
4. 誤答分析ノート(ミスノート)をつける
間違えた原因(読み飛ばしか、勘違いか、条件把握ミスか)を記録し、パターン化して本人と一緒に分析します
5. 間違いの傾向を共有し、改善策を視覚化する
親子で「このタイプの問題は、この読み方をすればいい」と確認し、言語化・モデル化していくことで改善習慣が定着します
3.実践例:小学4年生が「問題を読み間違える」場合への対応モデル ステップ 親の関わり 子どもの反応と変化
① 指差し読書導入
「条件に線を引こう」と声かけ 注意深く読む習慣が芽生える
② 音読チェック
問題文を声に出して読む習慣づくり 理解しながら読む力が強まる
③ 読み返し時間設定
テスト直後に2分間の見直しタイムを設ける 誤答に気づける割合が向上
④ ミスノート作成
間違いの原因を記録し一緒に見る 自分の癖に気づき改善意識が生まれる
⑤ 傾向確認会話
「こういう条件だと要注意ね」と話す 親子で共通認識が生まれ、習慣化が進む
4.継続によって育つ力と家庭の安心感
1.取り組み
子どもに育つ力 親が得られる安心
2.動作+指差し習慣
読む力と確認力の強化 親の叱責が減り対話が楽に
3.音読チェック
理解の定着と精読力の育成 子どもの理解度が目に見える化
4.確認タイムルール
ケアレスミス対応力の向上 点数の安定と心配の軽減
5.ミスノート分析
自己理解と修正習慣 親子で原因を共有でき安心感に
6.傾向共有
自律的な注意習慣が定着 親のアドバイスに信頼が生まれる
締めの言葉
「"問題を読み間違える"という悩みは、読む習慣がまだ未完成であるサインです。親が具体的な動作や確認の仕組みを整え、間違いの傾向を共有することで、子どもの読み方は変わります。親子で読む力を育て、テストも日常も"正確に読み取り、伸びる学び"へと変えていきましょう。」 読み間違いは単なる"ミス"ではなく、気づきと改善の入口です。動作・習慣・振り返りを通して正確に読む力を育て、学びの自信と安心を積み上げていきましょう。
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年7月30日 11:41
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。