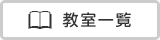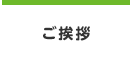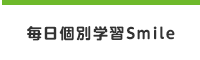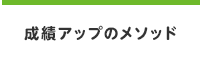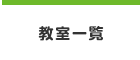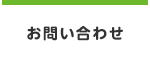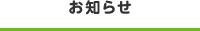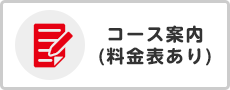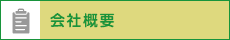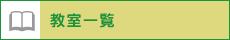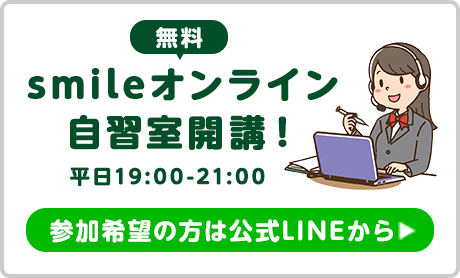月別 アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (14)
- 2025年7月 (30)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
スクールブログ 2ページ目
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ33
--保護者が知っておくべき"成績ギャップ"の正体と、家庭でできる改善策--
最近、三重県四日市市・川越町・富洲原エリアの保護者の方から増えている相談が、 「学校の成績と塾の成績が一致しない」 という声です。 塾の模試や確認テストでは高得点なのに学校の定期テストでは伸びない、または、学校では良い成績なのに塾のテストでは振るわない----。この"成績ギャップ"はどのご家庭でも起こり得る現象であり、決して珍しいことではありません。 しかし、理由を正しく理解し、対策を取ることで、学校と塾の成績をそろえ、安定した学力アップにつなげることができます。
本記事では、成績が一致しない原因と解決策を保護者向けにわかりやすく解説します。
■なぜ「学校の成績」と「塾の成績」は合わなくなるのか?
① テストの目的と作成者がそもそも違う 学校の定期テストは**"授業内容をどれだけ理解できているか"を測るもの。 一方、塾のテストは"基礎〜応用の総合力"や"入試を見据えた力"**を測るものが多く、目的が異なります。 小学生・中学生の場合、この違いが成績差として表れることが多いです。
② 出題範囲・レベル・配点基準が違う 学校は教科書準拠で範囲も明確ですが、塾は応用や発展問題が多めです。 例えば、学校では80点でも塾のテストでは50点台になることがあるのはこのためです。
③ 学校の授業スピードと塾の進度がズレる 塾では「先取り授業」を行うことが一般的で、 ・塾では理解しているのに、学校授業で混乱する ・学校の復習が足りず、定期テストで取りこぼす といった現象が起きやすくなります。
④ 子どもが「テストの種類」に合わせた勉強方法を知らない 学校の定期テストは"ワーク対策型" 塾のテストは"理解+初見対応型" と性質が違うため、同じ勉強方法では結果が一致しません。
⑤ テスト本番でのメンタル・環境が違う 「塾だと緊張しない」 「学校だと時間配分が失敗する」 といったメンタル要因も、成績のバラつきにつながります。
■成績ギャップを埋めるために家庭でできる3つのアドバイス
① 子どもが"どのテストに弱いのか"を一緒に分析する 成績が合わないときに大切なのは 「塾のテストが悪いのか、学校のテストが悪いのか」 を明確にすることです。
● 学校の成績が低い場合 →ワークの反復不足、提出物対策の弱さ、学校授業の理解不足が原因。
● 塾の成績が低い場合 →応用力、初見対応力、文章読解力の不足が原因。 保護者ができるのは、この"どちらが弱いのか"を一緒に確認することです。
② 「学校テスト用の勉強」と「塾テスト用の勉強」を分けて考える 同じ"勉強"でも、目的が違えば方法も変える必要があります。
● 学校の定期テスト対策は ・教科書 ・学校ワーク ・授業ノート この3点の反復が中心。 特にワークは"3周以上"が理想です。
● 塾のテスト対策は ・初見問題に慣れる ・基礎の式や文法を説明できるようにする ・ミスの原因を深掘りする これが得点UPにつながります。 両方を"同じ対策で済ませる"のは、成績ギャップの原因になります。
③ 得点の「取りこぼしポイント」を家庭で共有
学校テストの取りこぼしの多くは ・ケアレスミス ・見直し不足 ・単元の穴(比例反比例、図形、英単語など) といった"パターン化"された原因から起きます。 塾のテストでは ・問題文の読み違い ・応用問題での思考停止 ・基礎解説の理解不足 などが目立ちます。 家庭で「どの原因が多いのか」を共有するだけで、次のテストの伸び方が変わります。
■学校と塾の違いを活かすと成績は安定する
保護者の中には、 「どちらの成績を信じれば良いの?」 と迷われる方も多いですが、実はどちらも"必要な視点"です。
・学校の成績 → 内申点・定期テストで評価される"授業理解力"
・塾の成績 → 入試・実力を左右する"総合学力" この2つがそろって初めて、「本当の実力」が安定します。
三重県四日市・川越・富洲原の保護者の方から、 「どちらの成績も上がるようにしたい」 という相談をいただくことがありますが、そのためには"テストの目的の違い"に合わせた学習方法を選ぶことが非常に大切です。
■まとめ:成績が合わないのは"問題"ではなく"伸びしろ" 学校の成績と塾の成績が同じになる必要はありません。 それぞれが違う方向から子どもの学力を測っているからです。 大切なのは、 ・どこが伸びているか ・どこでつまずいているか ・何をどのように勉強するか この3つを整理すること。 成績が合わないときこそ、 "今の学習に何が足りないか" "どんなサポートが必要か" が見えやすいタイミングです。 保護者の声かけや家庭での環境づくりで、成績のギャップは必ず埋められます。 学校でも塾でも安定して点が取れるようになると、お子さまの自信も大きく育ち、苦手科目にも良い影響が出ます。ぜひ今日からできる小さな工夫を取り入れ、お子さまの学習をサポートしてみてください。
(毎日個別学習Smile) 2025年11月24日 15:47
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ32
考えられる4つの要因
① 基礎が「感覚頼り」で固まっていない 得意科目は「なんとなくできる」状態で進んでしまう子が多く、実は基礎があいまいなまま中級・上級レベルに突入します。 中学生になると、感覚だけで解けた問題が解けなくなり、点数が停滞することがよくあります。
② 学習量の"質"が上がっていない 得意科目は苦手科目ほど時間を割かれず、復習量が不足しやすく、気付かないうちに成績が横ばいになるケースが多いです。
③ 本人の「成長実感」が薄くモチベーションが下がる 得意だからこそ、伸びにくくなると落差を感じてやる気を失う子もいます。 これは特に小学校高学年~中学生に多い傾向です。
④ テストのレベルが上がり、必要な思考力が変わる 中学生の定期テスト・実力テストは、単純な暗記では突破できず、思考力や文章読解力が要求されます。 「得意」と思っていた科目の"方向性"が変わることで伸び悩むケースがあります。
■家庭でできる「得意科目を再び伸ばす」3つのアドバイス
①「説明できる?」を合言葉にする 得意科目を伸ばすカギは、"自分の言葉で説明する力"です。 ・なぜこの答えになるのか? ・式の意味は? ・別パターンでも通用する? これを親子の会話で軽く聞くだけで、理解の定着が変わります。特に算数・数学・英語で効果的です。
②「同じ問題で満点」より"新しい問題で合格ライン"を評価 伸び悩む子は「ワークはできるけど初見問題が解けない」状態になりがちです。 得意科目の成長には、"初見問題でどれだけ通用するか"をチェックすることが重要です。
③ 苦手科目に時間をとられすぎないようバランスを調整 よくあるのが 「苦手科目ばかり対策して得意科目のメンテナンスが不足」 という状態。 得意科目ほど短時間で効果が出るため、毎日10分でも良いので触れる時間を作ると成績は安定します。
■塾を活用する場合のポイント
得意科目の伸び悩みを解決するには、 "わかる→できる→点数になる"の3段階を明確にしてくれる学習環境 が必要です。 特に、 ・基礎が抜けていないかの確認 ・初見問題での弱点の洗い出し ・自走できる練習方法の習得 この3つを丁寧に行う塾は、得意科目をワンランク上げるのに有効です。 三重県四日市市・川越町・富洲原エリアの保護者の方からは、 「得意科目の点数が止まった」 「苦手克服ばかり気にして得意科目の伸ばし方がわからない」 といった相談が毎年増えています。
■まとめ:得意科目は"少しの工夫"で一気に伸びる
得意科目が伸びないのは「能力不足」ではなく、 ・基礎の抜け ・学習方法のズレ ・モチベーション低下 といった環境要因がほとんどです。 保護者のちょっとした声かけや、短時間の質の高い勉強で、得意科目はもう一段階伸びます。 得意科目が再び伸び始めると、勉強全体のやる気も上がり、苦手科目にも良い影響を与えます。 "得意科目を伸ばす"ことは、実は子どもの自己肯定感を高める最も効率的な方法です。 ぜひ今日からできる小さな工夫を取り入れてみてください。
(毎日個別学習Smile) 2025年11月17日 13:34
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ31
1.なぜ「苦手科目が多すぎる」に悩むのか?(理由)
中学生になると教科も増え、テスト範囲も広くなり、"苦手"と感じる科目が複数出てくるのは自然なことです。ですが「苦手科目が多すぎる=自分はダメだ」という思い込みが生まれると、子どもも親も焦りや不安を抱えやすくなります。 また、苦手科目が多いという認識があると、「何を優先すべきか」がぼやけてしまい、結局どれも中途半端になりがち。勉強時間を増やしても、やり方がその子に合っていなければ効果が出ず、さらに「自分だからできない」と自信を失うという負のスパイラルも起こりえます。 さらに、「苦手科目=避けたい教科」「苦手なまま先に進む教科」が蓄積されると、定期テストや受験での選択肢が狭まるという不安が親には付きまといます。こうした状況を放置すると、子どもは勉強自体を避け始め、苦手がさらに苦手を呼ぶ構図になってしまうのです。
2.「苦手科目が多すぎる」を"克服可能なチャレンジ"に変える5つのステップ(方法)
① 現状を"苦手教科とその原因"で整理する
まず、子どもと一緒に、どの教科が苦手なのか、なぜ苦手なのかを具体的に書き出します。
例えば「数学:関数が苦手」「英語:長文読解が苦手」「理科:化学反応式がわからない」というように。原因があいまいなままでは「苦手科目」扱いが広がるばかりです。
② 苦手教科の中で"優先する1科目"を決める
苦手が多いときは、一度に全部を直そうとせず「どれか1つ」を選んで集中する方が効果的です。親子で相談して、「この教科を先に立て直そう」と決め、他の教科は「並行して少しずつ」という形に落とし込むことで、負荷を減らせます。
③ その教科に合わせた"学び方"を変える
苦手教科の克服には「方法を変える」ことが鍵です。例えば、数学が苦手なら「図を書いて」「声に出して公式を読む」「友達に説明させてみる」など、自分の理解スタイルに応じて方法を変えてみます。英語が苦手なら「音声を聞いて繰り返す」「短い英文から声に出す」など、負担を小さくして取り組める工夫を。
④ 進捗と習慣を"見える化"する
選んだ1科目に対して、「毎日10分+週末30分」のようなルーティンを作ります。親子でカレンダーやホワイトボードに「今日これをやった」「○がついた」と可視化していくことで、苦手教科にも"できている感"が育ちます。できたら親が「よくやったね」と声をかけることも重要です。
⑤ 成功体験を小さく積んでいく
苦手科目を克服するには、小さな成功体験の積み重ねが自信を育てます。「今日は問題2問だけできた」「公式がひとつ思い出せた」など、目立たないけれど確かな"できた"を親子で拾い上げ、次への意欲をつなげましょう。苦手科目が"できる教科"に変わる転機は、こうした積み重ねの中にあります。
3.具体例:中学3年生Dさん+父親の「苦手教科を克服する3週間モデル」(具体例)
第1週:Dさんは理科と社会が苦手と感じ、「全部苦手だ」と思っていました。父親と「まず社会の歴史を立て直そう」と決め、歴史年号・事件・用語を紙に出して整理。
第2週:社会の年号を「音声で10回聞いて声に出す」「ノートに図でまとめる」学習に変えました。父親は「音声終わった?ノート書いた?」と毎晩確認。Dさんは「声に出すと覚えやすい気がする」と気づき、少し勉強時間が増えました。
第3週:次の小テスト前に「今日までに年号3つ習得」というミニ目標を立て、カレンダーに○をつける形で進捗を可視化。テストでは前回比+7点。父親は「よく頑張ったね」と言い、Dさんは「苦手がひとつ減った感じがする」と話しました。この成功体験が次の数学(苦手2番目)に移行するモチベーションになりました。
4.育つ可能性と親の安心(可能性)
・苦手科目が「克服すべき課題」から「自分で変えられる教科」へ変わる。
・学び方を変えることで、他の教科にも応用が効き、全体成績の底上げにつながる。
・親子の対話が深まり、親として「どこが苦手か」を知り"どう支えるか"が見えるようになる。
・子ども自身が「苦手でもやれば変わる」と感じられるようになり、自己効力感・自信が育ちます。 親としては「苦手科目が多すぎる」という漠然とした不安から、「具体的に一緒に改善できる」という安心に変わっていきます。
締めの言葉
「苦手科目が多すぎる」と感じることは、むしろ成長のチャンスです。一度に全部直そうとするのではなく、「まずひとつ」を選び、方法を変え、習慣を整え、親子で小さな成功を拾いましょう。苦手科目を「やっとわかる」「少しできる」へと変える旅を、親子で始めてください。あなたの支えが、子どもの学びを変える力になります。
(毎日個別学習Smile) 2025年11月10日 12:59
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ30
1.なぜ「内申点が心配」になるのか?
(理由)
中学生の保護者の多くが、「内申点(通知表・評定・各教科の評価)が下がったら受験できる高校が狭まるのでは?」という不安を抱えています。特に中3・中2で成績の波があったり、学習習慣が定着していなかったりすると、内申点の低下が"未来の選択肢を減らす"という恐れに直結します。 さらに、内申点は「塾のテスト」や「学校の授業理解」「提出物・態度・授業参加」といった多面的評価が絡むため、「自分の点数だけやればいい」という単純な努力では十分でないケースがあります。つまり、成績(テスト)と内申(通知表)のギャップを親子で理解しないまま進むと、「何をどうすれば内申が上がるのか」が見えず、子どもも親も焦りを抱えやすくなるのです。
2.「内申点を作る」ための5ステップ(方法)
① 現状を"教科別・評価要素別"に整理する
まずは、過去の内申(学校評定)・テスト点数・提出物・授業態度・部活動・定期考査の成績を親子で確認します。どの教科が低く、どの評価項目(出席・態度・提出・理解度)に課題があるかを具体的に洗い出すことが、対策の第一歩です。
② 基礎と提出物・授業参加を最優先にする
内申点を上げるには「理解+態度+提出」が揃うことが重要です。例えば、数学で定期考査の点数が落ちていれば、公式・基本問題に遡って復習し、さらに授業ノートを毎回提出できる形にします。英語なら単語・文法の理解と、宿題・ワークの提出をルーティン化する。
③ 学び方と参加姿勢を見直す
どんなに勉強時間を増やしても、授業中に寝ていたり発言しなかったりすれば、内申の評価が下がる可能性があります。視覚的に自分が授業に"参加している"証拠(ノートの書き込み・質問メモ)を残すよう促しましょう。
④ 学習計画とルーティンを再設定する
次の定期考査までに「毎日〇分は予習」「授業後10分で復習」「宿題・提出物は授業翌日までに終わらせる」など、具体的かつ継続可能なルーティンを親子で決め、進捗を可視化します。親は「今日、提出できたね」「ノートきれいに書けたね」と必ず声をかけて承認することが、子どもの習慣化を支えます。
⑤ 親子で"内申点アップ会議"を定期化する
月に1回、親子で「今月の内申へのアクション振り返り+次月の目標設定」を行います。例えば「次回、数学の提出物を100%出す」「国語で授業中に1回発言する」という目標を決め、終わったら進捗をチェック。これが「内申点も自分で作れる」という実感を生みます。
3.具体例:中学2年生Cさん+父親の3ヶ月モデル(具体例)
週1回の"内申点アップ会議"で、Cさんは「理科の内申が3→2へ下がった」「提出物の未提出が2件ある」ことを確認。父親とCさんは「理科:授業ノートを毎回提出する」「宿題は授業翌日に必ず提出する」という目標を立てました。 次の定期考査では、理科のテスト点数が前回比+8点。授業ノート提出率も100%になり、通知表が3から3+へ上がりました。父親は「毎回提出できたのがすごい」とCさんを褒め、Cさんは「自分でも変わった気がする」と言いました。 このように、点数アップだけでなく、提出・授業参加・態度といった"見えづらい内申評価項目"を丁寧にクリアすることで、通知表の上昇は加速します。
4.育つ可能性と親の安心(可能性)
・内申点を自分でコントロールできる感覚が育つ
・テスト点数と通知表のギャップが縮まる ・高校受験・将来進路で選択肢が広がる
・親子のコミュニケーションが「評価」ではなく「成長」基軸になる 親としては「通知表が出るたびにハラハラする」日々から、「内申点を一緒につくっている」という手応えのある日々へと変わります。
締めの言葉
「内申点が心配」という声は、子どもの未来を想う親の深い愛です。 でも、その不安を「責め」にしてしまうと、子どもは心を閉ざしてしまいます。 今日から、成績と同じくらい"授業参加・提出・態度"の小さな一つ一つを丁寧に可視化し、親子で一緒につくる習慣にしていきましょう。あなたのサポートが、子どもの通知表も自信も変える手がかりになります。
(毎日個別学習Smile) 2025年11月 3日 13:12
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ29
1.なぜ「テストの点数が悪い」に悩むのか?
(理由) 中学生になると教科が増え、テスト範囲も広がり、勉強量が急に増えます。
点数が下がる一番の理由は、基礎が不十分なまま先に進んでしまうことです。理解があいまいな単元を放置したまま次に進むと、どんどん「わからない」が積み重なってしまいます。 また、以前の勉強方法が通用しなくなることもあります。中学の中盤以降は応用力が問われ、単純暗記では点数が取れません。「今までと同じやり方」では成果が出づらいのです。 さらに、親や先生の期待が高すぎると、それがプレッシャーとなり「また下がったらどうしよう」という不安に変わります。その結果、勉強への意欲そのものが低下します。 そして多くの子どもが陥るのが、「点数=自分の価値」と思い込むことです。点数が悪いと「自分はダメだ」と感じ、自信を失ってしまいます。これが最も危険なパターンです。自信を失った子どもは、勉強に向かう力を失ってしまうのです。
2.点数低下を反転させる5つの方法(方法)
① 現状分析から始める
まず、どの教科・どの単元で点数が下がったのかを明確にします。「どこでミスしたか」「どんな問題が苦手だったか」を一緒に整理しましょう。現状を見える化することで、焦りが減り、対策が見えてきます。
② 基礎固めを優先する
点数が下がったときこそ、焦って先に進まず、過去単元に戻ることが大切です。数学なら計算・公式・定理、英語なら単語・文法、理科社会なら重要語句・基本概念。基礎を固めることが、結果的に最短の近道になります。
③ 勉強方法を子どもに合わせて変える
子どもによって得意な学び方は違います。 ・図や色分けが効果的な「視覚タイプ」 ・音読や説明で理解が深まる「聴覚タイプ」 ・問題を解きながら覚える「体感タイプ」 自分に合わない方法を続けても伸びません。「やり方を変える」ことが成績回復の大きなきっかけになります。
④ 学習計画を明確にし、習慣を整える
「次のテストまでに何をどの順番でやるか」を明確にし、1日単位でスケジュールを決めます。親が「今日はここまでやってみよう」と具体的に声をかけ、終わったら「できたね」と承認することが大切です。習慣は「小さな成功体験の積み重ね」から生まれます。
⑤ ポジティブな声かけを意識する
点数が悪いときほど、「何ができなかったの?」ではなく、「どこまでできたの?」と聞いてあげてください。失敗の中にも成長の種があります。子どもが前向きに取り組めるように、日々の努力を認める姿勢が一番の応援です。
3.具体例(実際の親子の変化)
中学2年のBくんは、数学と英語の点数が2回連続で下がり、お母さんも心配していました。お母さんは「叱る」のではなく、一緒にテストを見直すことから始めました。 「どこでつまずいた?」「どうしてここで間違えたの?」と穏やかに話すうちに、Bくんは「証明問題が苦手」「長文になると集中が切れる」と自分から話すようになりました。 翌週からは、勉強方法を変えました。 数学は「定理を声に出して読む+図を書く」、英語は「短文を音読しながらノートに書く」。最初は面倒くさそうでしたが、「声に出すと覚えやすい」と気づいてから、勉強への抵抗が減りました。 母親は毎晩「今日も頑張ったね」と一言声をかけ、スケジュール表に○をつけました。 3週間後、次の小テストでは数学が10点、英語が8点上昇。「次はもう少し上げたい」とBくんの口から自然と出たとき、母親は涙が出るほど嬉しかったそうです。 このように、点数低下から立ち直るきっかけは「方法を変えたこと」と「親の関わり方の変化」にありました。
4.長期的に見たときの可能性(可能性)
点数が悪いという事実は、決して終わりではありません。むしろ「成長のサイン」です。 ・今の勉強のやり方が合っていない ・理解できていない部分が見つかった ・努力を形にする仕組みが必要 この3つに気づくことで、学び方が進化していきます。 勉強ができるようになる子どもたちは、共通して「修正力」があります。一度失敗しても、原因を見直し、やり方を変える。これができるようになると、テストの点数だけでなく、人生そのものに前向きな姿勢が身につきます。 親がその変化の最初のサポーターになれたら、点数以上の価値があります。「成績を上げる」よりも大切なのは、「自信を取り戻す」こと。そしてその第一歩は、親が「一緒にやり直そう」と寄り添うことです。
締めの言葉
成績が下がることは「終わり」ではなく「転機」です。 焦らず、責めず、共に向き合う姿勢があれば、子どもは再び学びに向かう力を取り戻します。親が「方法を変える勇気」を持つことで、子どもも「もう一度頑張ろう」と思えるのです。 「点数が下がったときこそ、やり方を変えるチャンス。 親が寄り添うことで、子どもの"もう一度やってみよう"が生まれる。」 今日からできる小さな一歩を、ぜひご家庭で始めてみてください。
(毎日個別学習Smile) 2025年10月27日 12:54
小学2年生から塾を探す親が増えている理由とは?
最近、「小学校2年生のうちから塾を考えています」というご相談が増えています。
以前は「小5の壁」と呼ばれ、小学校高学年になってから学習塾に通うケースが主流でした。
しかし、今では"その壁が3年前倒し"になりつつあるのが現実です。
なぜ今、小学2年生の段階で塾を探す家庭が増えているのでしょうか?
その背景には、教育の変化だけでなく、保護者の価値観や社会のスピード感の変化が深く関わっています。
1.「小3の壁」以前に気づく保護者が増えた
これまでよく言われてきた「小5の壁」とは、 ・授業スピードが一気に上がる ・抽象的な思考が求められる ・算数の文章題や割合、国語の読解が難しくなる などによって「急に成績が下がる」「やる気がなくなる」という現象を指していました。 しかし、近年では「小3の壁」という言葉が注目され始めています。 これは、小3で「勉強のやり方」や「自分で考える力」がまだ身についていないと、その先の学年で急に苦戦するというものです。 実際、小2の段階で次のような変化に気づく親御さんが増えています。 学校の宿題を"ただこなすだけ"になっている 教科書の内容を説明しようとすると「わからない」と言う 音読はできても意味を理解していない 計算ミスが増えてきた 家での学習習慣がつかない つまり、小2のうちに気づいた親ほど早く動く時代になったのです。
2.「低学年のうちに習慣をつけないと続かない」という実感
子どもが小学生のうちは、「まだ早い」「そのうちやる気になる」と思いたくなるのが親心。 しかし、多くの家庭が上の子や周囲の事例を見て実感しています。 「5年生になってから始めようとしたら、もう手遅れだった」 「勉強のやり方そのものが身についていなかった」 「ゲームや動画の誘惑に勝てなくなった」 こうした経験を耳にしたり、身近なママ友から聞いたりして、 「低学年のうちに生活リズムと勉強習慣をつけることが大事」 という意識が広がっています。 とくに最近は、AI教材やオンライン学習が普及し、「勉強=自分で管理する時代」になりました。 つまり、勉強ができる子より自分で学べる子を育てる必要があるのです。 その基礎をつくるのに最も適しているのが、小学2年生前後なのです。
3.学校教育の変化 ― 「考える力」重視へ
文部科学省の学習指導要領改訂によって、学校教育は大きく変化しています。 いまの小学生は、単に知識を覚えるだけでなく「なぜそうなるか」「自分の考えを言葉で説明する」ことが求められています。 たとえば算数の文章題では、 「りんごが3個あります。2個買い足しました。合計はいくつですか?」 という単純な問題から、 「りんごとみかんを合わせて◯個買いました。りんごはみかんより◯個多いです。 りんごはいくつ買いましたか?」 のように、文章を読み取って式を立てる"思考型"問題が増えています。 こうした問題に慣れていない子は、「読む力」「考える力」「整理する力」が必要になります。 つまり、「考える習慣」をつけるのが早ければ早いほど、学力の土台が安定するというわけです。
4. 親の不安の正体 ― 「つまずきが早く見える化」される時代
最近の保護者は、学校や家庭だけでなくSNS・AI教材など、さまざまな情報から子どもの理解度を"数値化"して把握できるようになりました。 アプリで進捗が見える、 テスト結果がすぐにデータ化される、 オンライン面談で学習分析が共有される。 こうした環境によって、 「うちの子、思ったより理解していないかも...」 と早い段階で気づけるようになったのです。 そのため、以前なら「小5になってからでいい」と思っていた家庭も、 小2の時点でつまずきのサインを見逃したくないと感じて動き出しているのです。
5. 「中学受験」や「AI時代」を見据えた早期意識
中学受験をする・しないにかかわらず、 最近の家庭では「将来を見据えて早めに基礎力を」と考える方が増えています。 特にSNS上で「中学受験は小3から本格スタート」といった情報が広まり、 「うちも小2のうちに下地を作っておこう」と動くご家庭が増加。 また、AI時代に突入し、「暗記より思考力」「点数より主体性」という価値観も浸透してきました。 保護者世代自身が"詰め込み教育"の限界を感じてきたため、 「子どもには"考えられる力"を」 という思いが強くなっているのです。
6.学校外での学びに"安心感"を求める家庭が増えている
コロナ禍を経て、学校と家庭の距離感が変わりました。 登校の制限やオンライン授業を経験したことで、 「学校だけに任せるのは不安」 という意識が広がったのです。 特に低学年のうちは、 ・先生の人事異動で授業の質が変わる ・クラス全体で進むため個別対応が難しい ・家庭でフォローしきれない など、学校だけでは対応しづらい面があります。 だからこそ、「学校以外に安心して相談できる場所を」 と考える家庭が、早期から塾を探すようになっています。
まとめ:これからの塾選びは「早く・無理なく・続けられる」が鍵
小2からの問い合わせが増えている背景には、 単なる"早期教育ブーム"ではなく、 「子どものペースで、無理なく学習習慣を身につけたい」 という親の切実な願いがあります。 勉強ができる・できないよりも、 ・自分から机に向かう習慣 ・失敗してもやり直せる力 ・考えることを楽しむ姿勢 これらを育てるには、実は「小学2年生前後」が最も伸びやすい時期です。
最後に、毎日個別学習Smileでは、 小2のお子さんでも安心して学べるよう、 一人ひとりのペースに合わせた"学習の入り口"づくりを大切にしています。 「まだ早いかな?」と思っても、実際に体験すると 「ここから始めておいてよかった」と感じるご家庭が多いのが特徴です。 もし今、お子さんの学び方に少しでも不安を感じているなら、 "学びの習慣づくり"を一緒に始めるタイミングかもしれません。
(毎日個別学習Smile) 2025年10月22日 14:39
あなたの塾、大丈夫?現場でよくある教え方ミス10選 〜通知表レベル別の指導と、集団塾・アルバイト講師の落とし穴〜
「一生懸命教えているのに、子どもの成績が伸びない...」 そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
実はその原因の多くは、"教え方のズレ"にあります。 どれだけ優れた教材やカリキュラムがあっても、生徒の理解度に合わない教え方をしてしまうと、成果は出にくくなります。
今回は、 通知表1〜5のレベル別に見る「理想の教え方」と「ありがちな教え方の間違いあるある」 「集団塾でありがちな教え方ミス10選」 「アルバイト講師にありがちな教え方ミス10選」 を、現場目線で一挙にご紹介します。
通知表レベル別「理想の教え方」と「間違いあるある」
通知表1の生徒:とにかく"つきっきり"で! 理想の教え方 小学生にもわかる言葉で、手取り足取り、一緒に解く。 理解よりもまず安心と自信を育てる段階です。
ありがちな間違い 「なんでこれがわからないの?」と叱る
黙って見守るだけ(=放置)
難しい言葉をそのまま使う
ポイント:この層は「わからないことが怖い」。先生が"翻訳者"になる意識が大切です。
通知表2の生徒:勉強の「やり方」を教える段階 理想の教え方 テキストの使い方・ノートまとめ・解き直しの方法など"型"を教える。
ありがちな間違い 「このページやっといて」で丸投げ
ノートが乱雑でもスルー
読ませるだけで定着させない
ポイント:内容より「どう学ぶか」を教える。基礎の型づくりが命。
通知表3の生徒:自走力を伸ばす段階 理想の教え方 間違え直し・時間配分・優先順位の付け方を練習させる。
ありがちな間違い テスト結果に一喜一憂で終わり
同じミスを放置
「もっと頑張れ」で済ませる
ポイント:"量"より"振り返り"。教えるよりも気づかせる指導が効果的。
通知表4の生徒:論理的思考を磨く段階 理想の教え方 「なぜ?」を問う。考え方の筋道を言語化させる。
ありがちな間違い 正解主義で終わる
深掘りせずパターン暗記
「こうすれば早い」と思考を奪う
ポイント:"速さ"ではなく"理解の質"を高める。
通知表5の生徒:分析・予測力を鍛える段階 理想の教え方 予測問題を作らせ、出題傾向を分析させる。
ありがちな間違い 難問ばかり与える
「全部できる」で終わらせる
自分の分析を軽視される
ポイント:この層は「考えさせる」ことが大切。教師は"問いを投げる側"になる。
集団塾でありがちな教え方の間違いあるある10選
1.全員同じスピードで進める 理解度の差を無視。できる子は退屈、ついていけない子は置き去り。
2. 「質問がない=理解した」と思い込む 質問できない子ほどわかっていない。沈黙は理解の証ではない。
3.「この問題はよく出る」で終わり "なぜ出るのか"を教えないと応用が利かない。
4. できない子を前で叱る 羞恥心が勝ってやる気がなくなる。信頼関係が崩壊。
5. 板書で満足する授業 ノートは綺麗でも理解はゼロ。
6.プレゼン力が高い先生が評価される "教え方がうまい"と"伝わる授業"は別物。
7. 前提知識が抜けたまま進む 置いていかれる生徒が静かに増える。
8.発表できる子だけ当てる 静かな子はずっと受け身。差が広がる。
9.テスト直前だけ詰め込み 定着していない知識は本番で崩れる。
10.平均点で満足する 個人の成長を見ない。塾全体が"できてる気"になる。
まとめ:集団塾の落とし穴は「平均思考」。学びは"全体"ではなく"個の変化"で測るものです。
アルバイト講師にありがちな教え方の間違いあるある10選
1.自分の勉強法を押し付ける タイプが違う生徒には逆効果。
2.「わかりやすく話す=教える」と思っている 生徒が手を動かす時間がない。
3.答えをすぐ教えてしまう 考える力を奪う最大のミス。
4.優しさ=甘やかし 間違いを指摘できず、成績が上がらない。
5. 「できた=理解した」と思い込む 確認問題を出さずに次へ進む。
6. その日限りの授業 前後のつながりがなく、一貫性ゼロ。
7.生徒が黙るとすぐヒント 考える時間を奪い、"待てない指導"になる。
8. 宿題を出して終わり やり方の確認やフォローなし。
9.「楽しかった」で満足 理解度を測らず、雰囲気で終了。
10.教室方針を知らずに我流で教える 内容がバラバラになり、保護者対応で混乱。
まとめ:アルバイト講師に必要なのは"伝える力"より"見取る力"。 生徒がどこでつまずいているかを観察し、寄り添う姿勢が重要です。
まとめ:成績を伸ばすのは「教える技術」ではなく「見極めの力」 生徒一人ひとりに合った教え方をするには、 「どのレベルの子に、どんな指導をすべきか」 を見極める力が欠かせません。 集団塾の平均主義、アルバイト講師の我流指導---- どちらも悪意はなく、「知らずにやっているミス」がほとんどです。 ですがその"ズレ"が、生徒のやる気と成績に大きく影響します。 塾という現場こそ、「教える」より「理解を導く」プロ意識が求められます。 最後に 教え方のズレを直す第一歩は、 「どの子にも通じる指導」ではなく 「その子に届く指導」を考えること。 あなたの通っている塾は、生徒一人ひとりに"合った教え方"ができていますか?
(毎日個別学習Smile) 2025年10月21日 20:36
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ28
1.なぜ「どんどん成績が下がる」のか?原因と理解すべきポイント
① 学習の基盤が揺らいでいる
中学生になると、教科数が増え、難易度も高まります。テスト範囲が広がる中で、基礎が固まっていないまま次の単元に進むと、知らず知らずのうちに"すきま"が広がり、成績低下につながることがあります。
②学習方法がその子に合っていない
単に勉強時間を増やしても、「やり方」があっていないと伸び悩みます。例えば暗記型学習が合わない子にただ暗記を強いても、頭に残らず、結果として成績が下がることがあります。
③モチベーションの低下と誤った自己認知
「どうせ自分はできない」「前回も点数取れなかったから」という思い込みが意欲を削ぎ、学習開始をためらわせ、さらに成績が下がる悪循環に入ることがあります。
④親子・学校・塾とのズレ
親が焦って声をかけすぎる、学校の授業と家庭学習の内容が噛み合っていない、塾の指導と家庭のサポートがバラバラ――こうしたズレも成績低下の背景として頻繁にあります。
2.下降トレンドを止め、巻き返すための5つのステップ(方法)
① 現状の"ズレ"を可視化する
この2〜3回のテストの結果をチェック。「どの教科・どの単元」で点が落ちているかを親子で見える化します。 学習時間・勉強内容・メンタル状況も同時に振り返ることで、原因の手がかりが見えてきます。
② 基礎に戻る"リセット"期間を設ける
成績下降を受けて「もう一度基礎事項を固める」フェーズを設けます(例:数学なら公式確認、英語なら基礎文法・単語復習)。 親が「リセットしても大丈夫」という安心のメッセージを出すことで、子どもも焦らず取り組めます。
③ 学習方法を見直す&その子に合わせる
視覚・聴覚・体験型など、自分の"学びやすさ"を探る時間を設けます。 短時間集中+小休憩の「ポモドーロ方式」や、問題を解いた後のまとめ時間など、方法を変えてみることで"学びの質"が上がります。
④ 学習計画と習慣を再構築する
「次のテストまで〇日、今日はこの教科を何分」というように、計画を立て親子で共有。 毎晩または毎週、実際に「何をどれだけやったか」をチェック。達成できたら小さなご褒美を設けるなどの工夫も有効です。
⑤ 親子で役割分担と協力体制を整える
「私は今日これを手伝うね」「あなたはこれを終わらせよう」という風に、親も関わる範囲・子どもの取り組む範囲を明確に。 成績低下に対して「あなたの責任」という雰囲気にならず、「私たちで立て直そう」という共同作業の姿勢が子どもの安心を生みます。
3.具体例:中学2年生Aくんと母親の巻き返し3週間モデル(具体例) 週 取り組み 変化・親のサポート
1週目 テスト結果・勉強時間のグラフ作成。「数学」「英語」で特に下がっていると判明。母親が「基礎リセット週間」と宣言。 子どもが「リセットしてもいいんだ」と納得し、少し気持ちが軽くなる。
2週目 学習方法を変更:数学は公式を色分けノートに、英語は音声+シャドーイング。計画表を作成し、毎日20分集中+5分休憩。 昨日より少し理解できた実感があり、子ども自身が「これ、いけるかも」と感じ始める。親が「昨日より進んでるね」と声かけ。
3週目 学習チェック会を設け、母親が「この3問、できるようになったね」と承認。テスト直前対策をスケジューリング。 テスト前に焦りが減り、自信を少しずつ取り戻す。成績UPが期待できる流れが見えてくる。
4.この取り組みを通じて育つ可能性と親の安心(可能性)
1.下降トレンドが反転する:仕組みを整え、方法を変え、親子で歩むことで、成績は上がる道が明確になります。
2.学び方が定着する:基礎→方法→習慣という流れを繰り返せば、「どう学ぶか」が自分で分かるようになり、将来の自立した学びにつながります。
3.自己効力感・自信の回復:小さな成功体験を積むことで、「自分にもできる」という感覚が戻り、勉強に対するマインドが変わります。
4.親子の信頼関係が深まる:成績低下を責めるのではなく、一緒に立て直す姿勢を示すことで、子どもは「味方がいる」と感じ、安心して挑めるようになります。
締めの言葉
成績が下がっていくのを見るのは、親にとってとても辛いことです。でも、それは子どもが"止まっている"わけではなく、"流れが変わりかけている"サイン。親としてできるのは、流れを変えるための舵を持つことです。 今日から、 「どこが下がったか」を確認して、 「基礎をもう一度固める」時間を設けて、 「学び方を一緒に見直して」、 「親子で計画を立て直し」、 「一緒に進む姿勢を示す」。 この5つを少しずつ、無理なく始めましょう。子どもとともに"下降"を"上昇"へと変える一歩を踏み出してください。あなたのサポートが、子どもの未来を変える力になります。
(毎日個別学習Smile) 2025年10月20日 12:49
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ27
1|なぜ「あとでやる」が習慣化してしまうのか?
(理由)
1.感情的な抵抗と"やりたくない心理"が先に勝つ
心理学的には、やりたくないタスクに対する内的抵抗----不快感・不安・失敗の恐れなど----が「先延ばし」の根源になると言われています
2.タスクが大きすぎて腰が重くなる
漠然と「宿題をやる」「復習をする」と言われても範囲が広すぎると、どこから手をつけたらいいか迷い、動けなくなってしまいます。小さく分けることが大切です
3.決断疲れと意志力の枯渇
1日に何度も意思決定を繰り返すと、意志力は消耗します。やるべきことを自分で考え続けること自体が先延ばしの原因になるという指摘があります
4.完璧主義や恐れが動きを止める
「完璧にやらないと意味がない」という思い込みが、始めることを怖がる心理を助長します。完璧でなくても進めることを許すスタンスが要です
2|"あとでやる"を防ぐ5つの実践ステップ(方法) 下記ステップを、親子で一緒に少しずつ取り入れてみましょう。
① まず「5分だけ」始めてみる
たとえ5分でもいいからやってみることで、抵抗の壁を破る一歩になります。心理学的には、始めること自体が先延ばし防止になり得ます
② タスクを極小に分割する
「数学1問」「英単語3語」など最小単位に分解すると、始めやすく、心理的障壁が下がります
③ 予定を先に書いてしまう(時間ブロック化)
その日やる時間をあらかじめスケジュールに組み込んでおくことで、決断エネルギーを節約できます たとえば、「放課後から30分」「夕食後20分」などブロックしておく。
④ 作業環境から誘惑を排除する
スマホの通知をオフにする・別の部屋に置く・集中できる場所に移動するなど、視覚・聴覚的な誘惑を減らすことで先延ばしを抑えられます
⑤ 自己理解と自分への許しを育てる
先延ばししてしまった自分を責めず、「その日は疲れていたんだね」と受け止める自己慈悲(self-compassion)の態度が、再挑戦のエネルギーを生むという研究もあります
3|具体例:中1女生の「あとでやる」パターンへのアプローチ ステージ 親の支援 子どもの行動
① あとでになりがち 「まず5分だけやってみようか」と提案 5分だけ教科書を開く
② 小分割タスク 「英語 単語3語+文法1文」などに区切る 小さな達成を重ねる
③ 時間ブロック 「夕食後20分は勉強時間ね」とタイムブロック その時間は他を触らず学習モード
④ 環境整備 スマホは別室、通知オフ 集中しやすい状態を作る
⑤ 信じて待つ 「今日は疲れてたね、明日はどうする?」と声掛け 自己反省しながら再スタートを決める
4|"先延ばし"を乗り越えた先にある可能性(可能性)
1.小さな一歩が習慣をつくる 5分から始める習慣が、30分、1時間へと伸びていく階段になります。
2.自己効力感の再構築 「やればできる」という感覚を取り戻すことで、自信が戻ります。
3.毎日を能動的に使えるようになる 先延ばしせず動ければ、余裕をもって復習・見直し時間を積めるようになります。
4.受験・将来でも役立つ自己管理力 先延ばしを克服するスキルは、高校・大学・社会生活においても強力な財産になります。
締めの言葉
「あとでやる」は誰もが一度は使う言葉ですが、それを繰り返すと未来への時間が奪われてしまいます。しかし、小さな一歩、明確な設計、優しい自己理解があれば、先延ばしの呪縛は解けます。 親としてできることは多くありませんが、一緒に"始める仕組み"を作ること、その過程を褒めること、環境を整えることだけでも、子どもの"行動できる力"は確実に変わっていきます。ぜひこの言葉を胸に--「今日の5分」を親子で設計し、未来への前進を支える一歩を始めてみてください。
(毎日個別学習Smile) 2025年10月13日 12:59
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ26
1|なぜ自信は折れやすいのか? 親が知っておくべき理由
● 小さな失敗が心の壁に変わる
中学生になると勉強内容は急に難しくなり、テストの結果や成績が顕在化します。繰り返し思うように点が取れなかったり、理解できないまま先へ進んだりすると、「どうせ自分はできない」というセルフトーク(自己否定)が育ってしまいます。
● 比較と評価が重くのしかかる
友達や兄弟との比較、先生や親の期待、過去の成績とのギャップ。そうした"比較軸"が自信を揺るがす原因になります。 良書や教育コラムでも、「他者との比較ではなく、自己成長軸で評価すること」が自信回復の要とされています。
● "できていない部分"ばかり目に入りやすい
人はネガティブな情報(できない、間違った点)を目立たせてしまいがちです。できている部分を見落とすと、自信が育ちにくくなります。
● 自信が低いと学びのスパイラルに陥る
自信がない → 手が止まる → 実践できない → さらに自信を失う...という負のループ。 教育心理学でいう「自己効力感」が低いと学習動機が持続しにくい、という研究もあります。
2|"自信を取り戻す"ための5ステップ(方法)
① 小さな成功体験を設計する
まずは確実に「できる」ことから始めます。 例:「英単語5語だけ覚える」「問題集1ページだけ解く」「教科書1段落を声に出す」など。 その成功を必ず振り返り、認める時間を持ちます。
② 成績以外の指標で「伸び」を捉える
学習時間、理解できた範囲、質問できた回数、ノートを整理したことなど、点数以外の「できたこと」を評価軸に入れます。 親子で「今日はこれを達成できたね」とチェックリストを使って確認する。
③ 自分の学びスタイルを探る
視覚学習(図・色・マインドマップ)・聴覚学習(声に出して読む・録音を聴く)・実践型(手を動かして解く)など、自分が理解しやすいスタイルを試して取り入れてみる。 親はその選択肢を一緒に提供し、子どもが「これがやりやすい」と感じられる方法を見つける手助けをします。
④ フィードバックと改善を回す習慣を作る
間違えた問題を直すだけでなく、「なぜミスしたか」「どうすれば解けたか」を振り返る時間を設ける。 親も聞き役に徹し、「次回ここに注意するといいね」と一緒に考える。
⑤ 自信の種を育てる声かけを意識する
批判・否定ではなく、承認と励ましを口にする。 例:「間違えても挑戦した姿がいいね」「そこまで頑張って続けてるの、すごいよ」 「できた」「進歩した」ことを大人が言葉にすることで、自己肯定感が養われます。
3|具体例で見る取り組みモデル(中2子ケース) ステップ 実際のやり方 親の関わり
① 小成功
数学の計算を10問ゆっくり解いてみる「10問できた!すごいね」と認める
② 非点数指標
今日15分勉強できた、ノートを整えた 「時間守れたね」「ノートきれいだね」
③ 学習スタイル探究
英語は声に出しながら、日本史はタイムライン図で整理 「どの方法がわかりやすい?」と一緒に試させる
④ 振り返り
解けなかった問題を分析、「ミスの原因はここかな」 親は聞き役+提案役に徹する
⑤ 声かけ
「この5分で集中できたの、すごい変化だね」 承認の言葉をかけることで自分の成長を実感させる
4|育つ可能性と中長期の変化(可能性)
1.自信が学びの起点になる
自分で「できた」を積み重ねる感覚が、自発的な学びを生みます。
2.自己効力感の育成
「私はやればできる」という感覚が自己効力感を高め、挑戦意欲を支えます。
3.モチベーションの内発化
外からの褒め言葉や評価に頼らず、学びそのものを楽しめる動機づけが育ちます。
4.将来の学びに強くなる
自己管理・振り返り・改善する力は高校・大学・社会でも役立つ汎用スキルになります。
締めの言葉(親御さんへのメッセージ)
あなたのお子さんが「勉強に自信が持てない」と感じるのは、決して恥ずかしいことではありません。それは、学びの途中でつまずき、視界を失っただけの状態です。 親としてできることは、完璧な答えを教えることではなく、小さな「できた」を一緒に見つけ、認め続けること。その積み重ねが心の芯を強くし、「自信を失った」から「自信を育てる」へと変わる道を築きます。 どうか焦らず、温かい眼差しで小さな歩みを一緒に見守ってください。あなたの支えが、子どもの「自信再起」の力になります。
(毎日個別学習Smile) 2025年10月 6日 12:23
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。