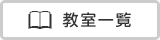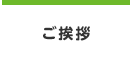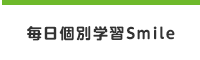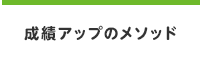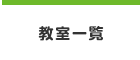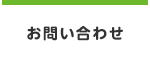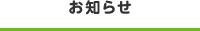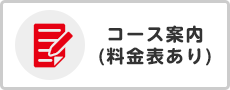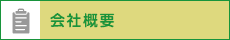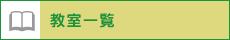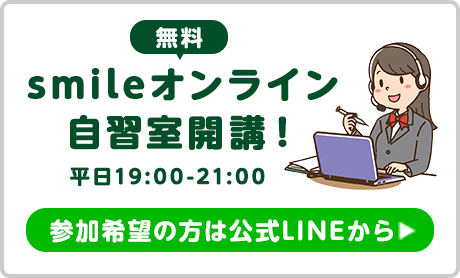月別 アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (14)
- 2025年7月 (30)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
HOME > スクールブログ > 三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ26
スクールブログ
< 三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ25 | 一覧へ戻る | 三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ27 >
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ26
1|なぜ自信は折れやすいのか? 親が知っておくべき理由
● 小さな失敗が心の壁に変わる
中学生になると勉強内容は急に難しくなり、テストの結果や成績が顕在化します。繰り返し思うように点が取れなかったり、理解できないまま先へ進んだりすると、「どうせ自分はできない」というセルフトーク(自己否定)が育ってしまいます。
● 比較と評価が重くのしかかる
友達や兄弟との比較、先生や親の期待、過去の成績とのギャップ。そうした"比較軸"が自信を揺るがす原因になります。 良書や教育コラムでも、「他者との比較ではなく、自己成長軸で評価すること」が自信回復の要とされています。
● "できていない部分"ばかり目に入りやすい
人はネガティブな情報(できない、間違った点)を目立たせてしまいがちです。できている部分を見落とすと、自信が育ちにくくなります。
● 自信が低いと学びのスパイラルに陥る
自信がない → 手が止まる → 実践できない → さらに自信を失う...という負のループ。 教育心理学でいう「自己効力感」が低いと学習動機が持続しにくい、という研究もあります。
2|"自信を取り戻す"ための5ステップ(方法)
① 小さな成功体験を設計する
まずは確実に「できる」ことから始めます。 例:「英単語5語だけ覚える」「問題集1ページだけ解く」「教科書1段落を声に出す」など。 その成功を必ず振り返り、認める時間を持ちます。
② 成績以外の指標で「伸び」を捉える
学習時間、理解できた範囲、質問できた回数、ノートを整理したことなど、点数以外の「できたこと」を評価軸に入れます。 親子で「今日はこれを達成できたね」とチェックリストを使って確認する。
③ 自分の学びスタイルを探る
視覚学習(図・色・マインドマップ)・聴覚学習(声に出して読む・録音を聴く)・実践型(手を動かして解く)など、自分が理解しやすいスタイルを試して取り入れてみる。 親はその選択肢を一緒に提供し、子どもが「これがやりやすい」と感じられる方法を見つける手助けをします。
④ フィードバックと改善を回す習慣を作る
間違えた問題を直すだけでなく、「なぜミスしたか」「どうすれば解けたか」を振り返る時間を設ける。 親も聞き役に徹し、「次回ここに注意するといいね」と一緒に考える。
⑤ 自信の種を育てる声かけを意識する
批判・否定ではなく、承認と励ましを口にする。 例:「間違えても挑戦した姿がいいね」「そこまで頑張って続けてるの、すごいよ」 「できた」「進歩した」ことを大人が言葉にすることで、自己肯定感が養われます。
3|具体例で見る取り組みモデル(中2子ケース) ステップ 実際のやり方 親の関わり
① 小成功
数学の計算を10問ゆっくり解いてみる「10問できた!すごいね」と認める
② 非点数指標
今日15分勉強できた、ノートを整えた 「時間守れたね」「ノートきれいだね」
③ 学習スタイル探究
英語は声に出しながら、日本史はタイムライン図で整理 「どの方法がわかりやすい?」と一緒に試させる
④ 振り返り
解けなかった問題を分析、「ミスの原因はここかな」 親は聞き役+提案役に徹する
⑤ 声かけ
「この5分で集中できたの、すごい変化だね」 承認の言葉をかけることで自分の成長を実感させる
4|育つ可能性と中長期の変化(可能性)
1.自信が学びの起点になる
自分で「できた」を積み重ねる感覚が、自発的な学びを生みます。
2.自己効力感の育成
「私はやればできる」という感覚が自己効力感を高め、挑戦意欲を支えます。
3.モチベーションの内発化
外からの褒め言葉や評価に頼らず、学びそのものを楽しめる動機づけが育ちます。
4.将来の学びに強くなる
自己管理・振り返り・改善する力は高校・大学・社会でも役立つ汎用スキルになります。
締めの言葉(親御さんへのメッセージ)
あなたのお子さんが「勉強に自信が持てない」と感じるのは、決して恥ずかしいことではありません。それは、学びの途中でつまずき、視界を失っただけの状態です。 親としてできることは、完璧な答えを教えることではなく、小さな「できた」を一緒に見つけ、認め続けること。その積み重ねが心の芯を強くし、「自信を失った」から「自信を育てる」へと変わる道を築きます。 どうか焦らず、温かい眼差しで小さな歩みを一緒に見守ってください。あなたの支えが、子どもの「自信再起」の力になります。
3か月体験コース紹介動画はこちら
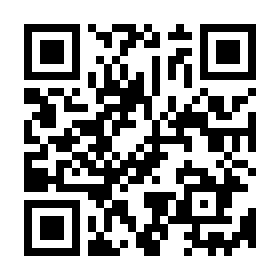
(毎日個別学習Smile) 2025年10月 6日 12:23
< 三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ25 | 一覧へ戻る | 三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ27 >