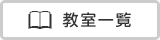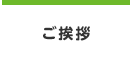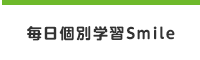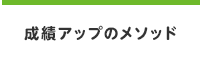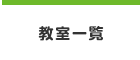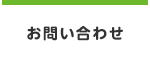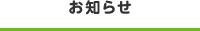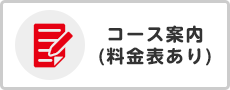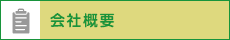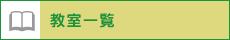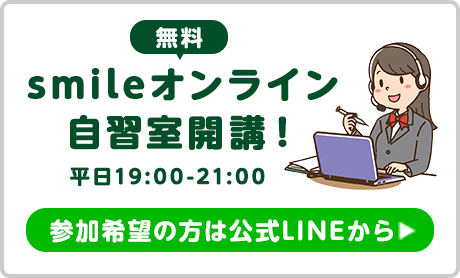月別 アーカイブ
- 2026年1月 (2)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (14)
- 2025年7月 (30)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
HOME > スクールブログ > アーカイブ > 2025年9月
スクールブログ 2025年9月
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ25
「"忙しいけど何もしていない"ように見える子どもには、見えない負荷や葛藤が隠れています。親は"見守る目"と"働きかけの仕組み"を整えることで、無為と思える時間の中にも、小さな学びの種を育てられます。」
1. なぜ「忙しいのに何もしない風」に陥るのか?(理由)
① 多忙と疲労が交錯して「動けない」
部活動・塾・習い事・友人関係など、スケジュールがぎっしり詰まっていると、精神的・肉体的にキャパシティを超えやすくなります。疲労が蓄積すると、何もできないような"無気力モード"に陥ることもあります。
② 何をすべきかが見えていない
忙しさに追われて、「勉強するべきこと・順番・方法」が明確でないと、スタート自体が遠く感じられ、行動できずじまいになってしまいます。
③ 心理的なブロックや抵抗が働いている
「勉強できていない自分」を責めてしまい、重圧を感じて手をつけられないケースもあります。過去の失敗や苦手意識が行動の壁になっていることも。
④ 見えないところでの学びが進行している
親から見えない形で読書・思考・調べ物をしていたり、頭の中で整理をしていたりと、"何もしないように見えている"だけで、実は思考の時間を使っていることがあります。
2. 「見える行動」に変えるための5つのアプローチ(方法・仕組み)
① まずは"最小行動"から始める
例えば「机の上に教科書を開くだけ」「ノートを出すだけ」「10分だけ復習する」といった、始めの一歩を超小さく設定する。習慣を作るときの原則です。
② タイムブロック方式を使う
忙しい日々の中で、あらかじめ「この時間は〇〇をやる」と枠を埋めておく。「夕食後20分」「寝る前15分」などをカレンダーに記入し、ルーティン化します。
③ 可視化ツール・タスク管理を活用する
ToDoリスト、ホワイトボード、スマホアプリなどで「今日/今週やること」を可視化。子ども自身がリストにチェックを入れる達成感を感じられるようにします。
④ 親子で"チェックイン"の時間を持つ
毎日または毎週、短時間でも良いので子どもと「今日はどうだった?」「次は何する?」と対話する時間を設ける。親が見守る姿勢を示すことで心理的な安心を作ります。
⑤ 忙しさの"隙間"を学びに変える工夫
移動時間・待ち時間など、ほんの数分の空き時間を使って「単語チェック」「暗記カード」「昨日の確認」などをさせる。こうしたスキマ時間の活用が積み重なります。
3. 実践例:中学2年男子「忙しいけど何も見えない」ケース ステップ 親の支援 子どもの行動
① 最小行動の約束
「帰ってきたら教科書だけ出してみよう」 教科書が机の上に置かれるだけで心理的スイッチが入る
② タイムブロック予約
「夜8時から20分は復習タイムね」 スケジュールに学習時間が確保され、始めやすくなる
③ 可視化リスト
ホワイトボードに「宿題・復習・提出物」3項目記入 チェックが入り、その日の終わりに達成感を味わう
④ 親子チェックイン
寝る前に「今日はどう?」と声かけ 子どもの気持ちを聴き、翌日のやる気につながる
⑤ スキマ時間活用
通学バス内で15分単語カード(アプリ使用) わずかな時間でも"勉強している自分"を実感できる
4. 長期的に育つ力と安心(可能性)
しかけ 子どもに育つ力 親に得られる安心 小さな行動から始める習慣 自発的に動く力
親が介入しすぎずとも動く姿が見える タイムブロック化 時間管理力 生活全体のバランスが見えるようになる
可視化とチェック 達成感・自己効力感 「今日は何をしたか」が明確で安心感 日々の対話 対話力・信頼関係 心の軸が揺れにくい関係になる
スキマ時間活用 隙間活用能力 忙しい中でも学び続ける力が育つ
5. 最新トレンドも味方にする:短時間集中 × デジタル教材活用
現在、中学生向けの 短時間集中型教材 の需要増が目立っています。たとえば、通信教育業界でも「1講座15分区切り」の構成が主流になってきています。これは、部活や習い事で忙しい生徒でも、細切れ時間を使って勉強しやすくする配慮です。 また、オンライン教材やAI対応教材では、自分のペースで進められ、苦手な部分を重点復習できる機能を持つものが増えています。 忙しい中でも「スマホでできる5分学習」「AIが弱点を診断してくれる教材」などを取り入れると、「何もやっていないように見える」時間にも、学びを仕込むことが可能になります。
6. 締めの言葉(親へのエール)
あなたの子どもが「忙しそうなのに何もしないように見える」ことに悩むのは、とても自然なことです。でも、その見えなさの裏には、疲れ・迷い・準備不足・見えない思考があるかもしれません。 親としてできることは、まず安心と共感を伝え、小さな行動を始められる設計を一緒にすること。何も動かないように見えても、最小行動=教科書を出すことすら、未来への種です。 短時間集中型教材やAI教材など、2025年の最新トレンドを味方につけながら、親子で学び方を再設計していきましょう。あなたの静かな見守りとちょっとした働きかけが、子どもの可能性を育てる強い土壌になります。 「忙しいけれど動ける人」になるための第一歩を、今日から一緒に始めませんか?
1. なぜ「忙しいのに何もしない風」に陥るのか?(理由)
① 多忙と疲労が交錯して「動けない」
部活動・塾・習い事・友人関係など、スケジュールがぎっしり詰まっていると、精神的・肉体的にキャパシティを超えやすくなります。疲労が蓄積すると、何もできないような"無気力モード"に陥ることもあります。
② 何をすべきかが見えていない
忙しさに追われて、「勉強するべきこと・順番・方法」が明確でないと、スタート自体が遠く感じられ、行動できずじまいになってしまいます。
③ 心理的なブロックや抵抗が働いている
「勉強できていない自分」を責めてしまい、重圧を感じて手をつけられないケースもあります。過去の失敗や苦手意識が行動の壁になっていることも。
④ 見えないところでの学びが進行している
親から見えない形で読書・思考・調べ物をしていたり、頭の中で整理をしていたりと、"何もしないように見えている"だけで、実は思考の時間を使っていることがあります。
2. 「見える行動」に変えるための5つのアプローチ(方法・仕組み)
① まずは"最小行動"から始める
例えば「机の上に教科書を開くだけ」「ノートを出すだけ」「10分だけ復習する」といった、始めの一歩を超小さく設定する。習慣を作るときの原則です。
② タイムブロック方式を使う
忙しい日々の中で、あらかじめ「この時間は〇〇をやる」と枠を埋めておく。「夕食後20分」「寝る前15分」などをカレンダーに記入し、ルーティン化します。
③ 可視化ツール・タスク管理を活用する
ToDoリスト、ホワイトボード、スマホアプリなどで「今日/今週やること」を可視化。子ども自身がリストにチェックを入れる達成感を感じられるようにします。
④ 親子で"チェックイン"の時間を持つ
毎日または毎週、短時間でも良いので子どもと「今日はどうだった?」「次は何する?」と対話する時間を設ける。親が見守る姿勢を示すことで心理的な安心を作ります。
⑤ 忙しさの"隙間"を学びに変える工夫
移動時間・待ち時間など、ほんの数分の空き時間を使って「単語チェック」「暗記カード」「昨日の確認」などをさせる。こうしたスキマ時間の活用が積み重なります。
3. 実践例:中学2年男子「忙しいけど何も見えない」ケース ステップ 親の支援 子どもの行動
① 最小行動の約束
「帰ってきたら教科書だけ出してみよう」 教科書が机の上に置かれるだけで心理的スイッチが入る
② タイムブロック予約
「夜8時から20分は復習タイムね」 スケジュールに学習時間が確保され、始めやすくなる
③ 可視化リスト
ホワイトボードに「宿題・復習・提出物」3項目記入 チェックが入り、その日の終わりに達成感を味わう
④ 親子チェックイン
寝る前に「今日はどう?」と声かけ 子どもの気持ちを聴き、翌日のやる気につながる
⑤ スキマ時間活用
通学バス内で15分単語カード(アプリ使用) わずかな時間でも"勉強している自分"を実感できる
4. 長期的に育つ力と安心(可能性)
しかけ 子どもに育つ力 親に得られる安心 小さな行動から始める習慣 自発的に動く力
親が介入しすぎずとも動く姿が見える タイムブロック化 時間管理力 生活全体のバランスが見えるようになる
可視化とチェック 達成感・自己効力感 「今日は何をしたか」が明確で安心感 日々の対話 対話力・信頼関係 心の軸が揺れにくい関係になる
スキマ時間活用 隙間活用能力 忙しい中でも学び続ける力が育つ
5. 最新トレンドも味方にする:短時間集中 × デジタル教材活用
現在、中学生向けの 短時間集中型教材 の需要増が目立っています。たとえば、通信教育業界でも「1講座15分区切り」の構成が主流になってきています。これは、部活や習い事で忙しい生徒でも、細切れ時間を使って勉強しやすくする配慮です。 また、オンライン教材やAI対応教材では、自分のペースで進められ、苦手な部分を重点復習できる機能を持つものが増えています。 忙しい中でも「スマホでできる5分学習」「AIが弱点を診断してくれる教材」などを取り入れると、「何もやっていないように見える」時間にも、学びを仕込むことが可能になります。
6. 締めの言葉(親へのエール)
あなたの子どもが「忙しそうなのに何もしないように見える」ことに悩むのは、とても自然なことです。でも、その見えなさの裏には、疲れ・迷い・準備不足・見えない思考があるかもしれません。 親としてできることは、まず安心と共感を伝え、小さな行動を始められる設計を一緒にすること。何も動かないように見えても、最小行動=教科書を出すことすら、未来への種です。 短時間集中型教材やAI教材など、2025年の最新トレンドを味方につけながら、親子で学び方を再設計していきましょう。あなたの静かな見守りとちょっとした働きかけが、子どもの可能性を育てる強い土壌になります。 「忙しいけれど動ける人」になるための第一歩を、今日から一緒に始めませんか?
(毎日個別学習Smile) 2025年9月29日 12:19
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ24
「勉強の仕方がわからない」は、能力の問題ではなく"設計の問題"。親が『どう始めるか』『どう続けるか』の地図を一緒に描いてあげれば、子どもは自分で動けるようになります。」
1)まずは安心して受けとめることが最優先(理由)
「何をやればいいかわからない」「どこから手をつければ良いか迷う」――中学生の多くが感じるこの混乱は、教科が増え、学習内容が複雑になる成長過程で自然に起きます。親の前で「わからない」と言えない子も多く、見えない不安が大きくなりやる気を失いやすいのです。 ここで重要なのは叱責ではなく共感と安心。「わからないね、じゃあ一緒に整理しよう」と親が言えるだけで、子どもの心は解け、学びの一歩が踏み出せます。 SEOキーワード:「勉強の仕方」「中学生」「親のサポート」「家庭学習サポート」
2)勉強の仕方を「見える化」する具体的方法(方法)
親が手伝えるのは「設計(プラン)」と「環境づくり」です。以下のステップで一緒に作業してみてください。
ステップA:今やるべきことを書き出す(可視化) 「宿題」「提出物」「次の定期テストの範囲」「苦手単元」を紙やホワイトボードに列挙します。 優先順位を「期限が近い」「テスト頻出」「苦手克服」の3つの観点で色分け。
ステップB:小さなタスクに分解する(分割) 大きな課題は小分け(例:英語→単語10個+文法1項目+長文1題)。 1タスクは10〜25分で終わる量に設定(ポモドーロ方式がおすすめ)。
ステップC:学習ルーティンを決める(習慣化) 「帰宅後にまず15分復習」「夕食後30分集中」など時間帯を決める。 親も同じ時間に自分の作業をする「共習タイム」をつくると効果大。
ステップD:振り返りと調整を習慣にする 週に一度、10分だけ「できたこと」「つまずいたこと」を一緒に確認。 成果が見えることで自己効力感が育ちます。
3)親がやりがちなNGと代替案(声かけの例)
NG:「もっと集中して!」「早くやりなさい!」 → 反発を生む OK:「たった10分だけ一緒にやってみようか」「ここを一つ終わらせたら小休止しよう」 → 始めやすく続けやすい 声かけは短く、具体的に。承認語(「やったね」「よく頑張ったね」)を必ず入れると、学習意欲は上がります。
4)教科別のシンプルな"始め方"具体例(具体例)
英語:単語10個 → 例文1つ声に出す → 簡単な英文を1行書く 数学:基本公式の確認(ノートに書く)→ 類題3問を解く → 間違いの解説を読む 理科・社会:教科書の見出しを声に出す→ 図や年表を5分でまとめる→ 関連する短い問題に挑戦 国語:本文を声に出して1段落読む→ 要旨を一行で書く→ 語句の意味を調べる どれも「できる量」に最初から設定することが鍵です。
5)ツール・環境の整え方(親のサポート)
目に見えるToDoボード(冷蔵庫や子どもの机横)で「今日の3つ」を表示。
タイマーや学習アプリ(集中タイマー、単語アプリ)を活用。 学習専用の場所を決め、スマホは目に入らない場所へ。 必要なら家庭教師や個別指導・自習室(MEOキーワード:家庭学習サポート、個別指導)を利用して環境を補強。
6)長期的な可能性 -- 勉強の仕方がわかるとどう変わるか(可能性)
自己効力感が高まる:小さな成功体験が自信に変わり、自発的に取り組む力が育つ。
時間管理ができるようになる:優先順位付けが身につき、テスト前の詰め込みから脱却。
学習が楽しくなる:理解が進むと達成感が生まれ、勉強自体に興味が出る。
将来設計の基礎ができる:自律的な学び方は高校・大学・社会で役立つ基礎力になる。
7)最後に親へのエール
親としては「教えたい」「助けたい」気持ちが強いほど、つい指示や叱責になってしまいがちです。まずは―― とにかく一緒に「やること」を見える化すること。 小さく始め、褒め、振り返るループを続けること。 この三つだけで、子どもの"勉強の仕方"は確実に変わります。焦らずに、親子で一歩ずつ地図を描いていきましょう。あなたの"そばにいる力"こそが、子どもにとって最大の学習サポートです。
1)まずは安心して受けとめることが最優先(理由)
「何をやればいいかわからない」「どこから手をつければ良いか迷う」――中学生の多くが感じるこの混乱は、教科が増え、学習内容が複雑になる成長過程で自然に起きます。親の前で「わからない」と言えない子も多く、見えない不安が大きくなりやる気を失いやすいのです。 ここで重要なのは叱責ではなく共感と安心。「わからないね、じゃあ一緒に整理しよう」と親が言えるだけで、子どもの心は解け、学びの一歩が踏み出せます。 SEOキーワード:「勉強の仕方」「中学生」「親のサポート」「家庭学習サポート」
2)勉強の仕方を「見える化」する具体的方法(方法)
親が手伝えるのは「設計(プラン)」と「環境づくり」です。以下のステップで一緒に作業してみてください。
ステップA:今やるべきことを書き出す(可視化) 「宿題」「提出物」「次の定期テストの範囲」「苦手単元」を紙やホワイトボードに列挙します。 優先順位を「期限が近い」「テスト頻出」「苦手克服」の3つの観点で色分け。
ステップB:小さなタスクに分解する(分割) 大きな課題は小分け(例:英語→単語10個+文法1項目+長文1題)。 1タスクは10〜25分で終わる量に設定(ポモドーロ方式がおすすめ)。
ステップC:学習ルーティンを決める(習慣化) 「帰宅後にまず15分復習」「夕食後30分集中」など時間帯を決める。 親も同じ時間に自分の作業をする「共習タイム」をつくると効果大。
ステップD:振り返りと調整を習慣にする 週に一度、10分だけ「できたこと」「つまずいたこと」を一緒に確認。 成果が見えることで自己効力感が育ちます。
3)親がやりがちなNGと代替案(声かけの例)
NG:「もっと集中して!」「早くやりなさい!」 → 反発を生む OK:「たった10分だけ一緒にやってみようか」「ここを一つ終わらせたら小休止しよう」 → 始めやすく続けやすい 声かけは短く、具体的に。承認語(「やったね」「よく頑張ったね」)を必ず入れると、学習意欲は上がります。
4)教科別のシンプルな"始め方"具体例(具体例)
英語:単語10個 → 例文1つ声に出す → 簡単な英文を1行書く 数学:基本公式の確認(ノートに書く)→ 類題3問を解く → 間違いの解説を読む 理科・社会:教科書の見出しを声に出す→ 図や年表を5分でまとめる→ 関連する短い問題に挑戦 国語:本文を声に出して1段落読む→ 要旨を一行で書く→ 語句の意味を調べる どれも「できる量」に最初から設定することが鍵です。
5)ツール・環境の整え方(親のサポート)
目に見えるToDoボード(冷蔵庫や子どもの机横)で「今日の3つ」を表示。
タイマーや学習アプリ(集中タイマー、単語アプリ)を活用。 学習専用の場所を決め、スマホは目に入らない場所へ。 必要なら家庭教師や個別指導・自習室(MEOキーワード:家庭学習サポート、個別指導)を利用して環境を補強。
6)長期的な可能性 -- 勉強の仕方がわかるとどう変わるか(可能性)
自己効力感が高まる:小さな成功体験が自信に変わり、自発的に取り組む力が育つ。
時間管理ができるようになる:優先順位付けが身につき、テスト前の詰め込みから脱却。
学習が楽しくなる:理解が進むと達成感が生まれ、勉強自体に興味が出る。
将来設計の基礎ができる:自律的な学び方は高校・大学・社会で役立つ基礎力になる。
7)最後に親へのエール
親としては「教えたい」「助けたい」気持ちが強いほど、つい指示や叱責になってしまいがちです。まずは―― とにかく一緒に「やること」を見える化すること。 小さく始め、褒め、振り返るループを続けること。 この三つだけで、子どもの"勉強の仕方"は確実に変わります。焦らずに、親子で一歩ずつ地図を描いていきましょう。あなたの"そばにいる力"こそが、子どもにとって最大の学習サポートです。
(毎日個別学習Smile) 2025年9月22日 13:40
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ23
「"何から手をつけていいかわからない"という迷いは、学びの羅針盤がまだ描けていないサイン。親が一緒に整理し、小さな一歩を設計することで、迷いは方向へ、混乱は自信へと変わります。」
1. なぜ「何から手をつけていいかわからない」のか?
親が知っておきたい理由
①学習内容が多すぎて圧倒されてしまっている
中学生になると教科数が増え、復習すべき範囲や準備すべきテストの内容が広くなります。科目・単元・宿題・ワーク・教科書・暗記物...と山積みになることで、「どこを先にやればいいか」がぼやけてしまうことが多いです。 ("勉強の仕方が分からない""何から手をつけていいかわからない"という悩みが、中学生・受験生の保護者・生徒で頻繁に上がっています。)
②目標設定が漠然としているため行動の方向性が定まらない
「成績を上げたい」「受験に合格したい」という大枠の目標はあっても、「どこの教科」「どの範囲」「どの問題集・ワーク」で始めるかが具体化されていないと、手が止まりやすいです。文献・教育サイトでも、まず目標を小さく設定することの重要性が強調されています。
③自分の苦手や弱点が見えていない
何から手をつければ良いかわからないのは、自分が"苦手な部分""つまづいている単元"が曖昧だから。どの単元が理解できていないかを特定できれば、そこから先へ進む道筋が見えてきます。
④勉強法・習慣がまだ定まっていない
正しい勉強のやり方/習慣が確立されていないと、「とりあえず教科書を読む」「とりあえずワークをやる」など手探りになり、結局どれも中途半端で終わってしまうことが多いです。教育サイトで「教科別の勉強法」「目標設定+ルーティンづくり」が必須要素として挙げられています。
2. 「何から手をつけたらいいか」がわかるようになる具体的な方法 以下のステップを親子で相談しながら進めていくことで、「何から手をつけるか」の迷いを整理できます。
ステップ①:今日~1週間以内の"直近の課題・期限"を書き出す まずは「宿題」「提出物」「次のテストの日程」「リスニングなどの宿題」「ワーク何ページ」など、今すぐ期限が迫っているものをリストアップします。これが「優先順位をつける土台」になります。たとえば、「来週のテストで出る単元」「先生が強調していたところ」などを入れます。
ステップ②:苦手科目・得意科目を棚卸しする 苦手だと感じている教科・単元、理解できていない内容を洗い出す。親が一緒にチェックして、「これは基本から復習が必要」「ここは少し進めば大丈夫」など判断する。「苦手の単元」から手をつけることが長期的な成果につながります。
ステップ③:教科別・単元別にやるべきタスクを細かく刻む 例として、英語なら「単語20個復習」「文法ワーク1ページ」「長文読解1題」、数学なら「公式の確認」「計算問題基本20題」「応用問題1題」など、小さなステップに分け、それぞれに時間を見積もる。親子でこのリストを作ることで、「何をすべきか」が明確になります。
ステップ④:優先順位をつける 「重要度 × 緊急度」で整理。例えば「テストで絶対出る」「学校の先生が強調していた」「次すぐ演習できる」ものを優先させる。あとは「やっておきたいけど少し後でも大丈夫」なものは後回しにする。リストに番号をつけたり、色を使って目立たせたりすると視覚的にもわかりやすくなります。
ステップ⑤:時間を決めて"習慣ルーティン化"する 例:毎日放課後30分、帰宅後30分、寝る前15分など、どこでどれだけやるか決め、その時間まずは小さく確実に続ける。慣れてきたら時間を延ばしていく。親が「その時間は勉強モード」というルールを一緒に作ると継続しやすくなります。
3. 実具体例:中学生受験生Aさんの「何から手をつければいいかわからなくなった」ケース ステップ 内容 親の関わり方 期待できる変化
① リストアップ 直近のテスト範囲・宿題・提出物を書き出す
一緒に課題を確認・書き出させる 見える「やるべきこと」ができ、手が動き始める
② 苦手科目の棚卸し 英語の長文が苦手・数学の図形問題が弱い
親が話を聴いて、どこがつまづきかを整理する 苦手の原因が明確になり復習の方向性が見える
③ 教科別タスク分け
英語:単語, 文法, 長文;数学:計算, 図形 一つずつ小さく区切る手伝いをする 少しずつ手を動かす自信がつく
④ 優先順位付け
テストで出るもの→弱点→余力ある範囲 親子で「これがまず必要だね」と話す 時間を効率よく使い、成果が見えやすくなる
⑤ 習慣ルーティン 夕食後20分間は宿題・提出物中心
親もその時間見守ったり共に学習する 勉強する雰囲気が日常に根づき、迷いが減る
4. 続けることで育つ可能性と親の安心 取り組み 子どもに育つ力 親が感じる安心
①リストを作る習慣 やることを整理できる力・自己管理 子どもの"混乱"が見えるものになる
②苦手の見える化 弱点改善と克服への自信 無駄な時間を減らせた実感
③小タスク分け 継続力と小さな達成感 "やり始めた"ことに喜びを感じられる
④優先順位設定 時間配分力・目標思考 効率よく成果を出す見通しが立つ
⑤ルーティン化 習慣という強さ 親が指示出しなくても始められる安心感
1. なぜ「何から手をつけていいかわからない」のか?
親が知っておきたい理由
①学習内容が多すぎて圧倒されてしまっている
中学生になると教科数が増え、復習すべき範囲や準備すべきテストの内容が広くなります。科目・単元・宿題・ワーク・教科書・暗記物...と山積みになることで、「どこを先にやればいいか」がぼやけてしまうことが多いです。 ("勉強の仕方が分からない""何から手をつけていいかわからない"という悩みが、中学生・受験生の保護者・生徒で頻繁に上がっています。)
②目標設定が漠然としているため行動の方向性が定まらない
「成績を上げたい」「受験に合格したい」という大枠の目標はあっても、「どこの教科」「どの範囲」「どの問題集・ワーク」で始めるかが具体化されていないと、手が止まりやすいです。文献・教育サイトでも、まず目標を小さく設定することの重要性が強調されています。
③自分の苦手や弱点が見えていない
何から手をつければ良いかわからないのは、自分が"苦手な部分""つまづいている単元"が曖昧だから。どの単元が理解できていないかを特定できれば、そこから先へ進む道筋が見えてきます。
④勉強法・習慣がまだ定まっていない
正しい勉強のやり方/習慣が確立されていないと、「とりあえず教科書を読む」「とりあえずワークをやる」など手探りになり、結局どれも中途半端で終わってしまうことが多いです。教育サイトで「教科別の勉強法」「目標設定+ルーティンづくり」が必須要素として挙げられています。
2. 「何から手をつけたらいいか」がわかるようになる具体的な方法 以下のステップを親子で相談しながら進めていくことで、「何から手をつけるか」の迷いを整理できます。
ステップ①:今日~1週間以内の"直近の課題・期限"を書き出す まずは「宿題」「提出物」「次のテストの日程」「リスニングなどの宿題」「ワーク何ページ」など、今すぐ期限が迫っているものをリストアップします。これが「優先順位をつける土台」になります。たとえば、「来週のテストで出る単元」「先生が強調していたところ」などを入れます。
ステップ②:苦手科目・得意科目を棚卸しする 苦手だと感じている教科・単元、理解できていない内容を洗い出す。親が一緒にチェックして、「これは基本から復習が必要」「ここは少し進めば大丈夫」など判断する。「苦手の単元」から手をつけることが長期的な成果につながります。
ステップ③:教科別・単元別にやるべきタスクを細かく刻む 例として、英語なら「単語20個復習」「文法ワーク1ページ」「長文読解1題」、数学なら「公式の確認」「計算問題基本20題」「応用問題1題」など、小さなステップに分け、それぞれに時間を見積もる。親子でこのリストを作ることで、「何をすべきか」が明確になります。
ステップ④:優先順位をつける 「重要度 × 緊急度」で整理。例えば「テストで絶対出る」「学校の先生が強調していた」「次すぐ演習できる」ものを優先させる。あとは「やっておきたいけど少し後でも大丈夫」なものは後回しにする。リストに番号をつけたり、色を使って目立たせたりすると視覚的にもわかりやすくなります。
ステップ⑤:時間を決めて"習慣ルーティン化"する 例:毎日放課後30分、帰宅後30分、寝る前15分など、どこでどれだけやるか決め、その時間まずは小さく確実に続ける。慣れてきたら時間を延ばしていく。親が「その時間は勉強モード」というルールを一緒に作ると継続しやすくなります。
3. 実具体例:中学生受験生Aさんの「何から手をつければいいかわからなくなった」ケース ステップ 内容 親の関わり方 期待できる変化
① リストアップ 直近のテスト範囲・宿題・提出物を書き出す
一緒に課題を確認・書き出させる 見える「やるべきこと」ができ、手が動き始める
② 苦手科目の棚卸し 英語の長文が苦手・数学の図形問題が弱い
親が話を聴いて、どこがつまづきかを整理する 苦手の原因が明確になり復習の方向性が見える
③ 教科別タスク分け
英語:単語, 文法, 長文;数学:計算, 図形 一つずつ小さく区切る手伝いをする 少しずつ手を動かす自信がつく
④ 優先順位付け
テストで出るもの→弱点→余力ある範囲 親子で「これがまず必要だね」と話す 時間を効率よく使い、成果が見えやすくなる
⑤ 習慣ルーティン 夕食後20分間は宿題・提出物中心
親もその時間見守ったり共に学習する 勉強する雰囲気が日常に根づき、迷いが減る
4. 続けることで育つ可能性と親の安心 取り組み 子どもに育つ力 親が感じる安心
①リストを作る習慣 やることを整理できる力・自己管理 子どもの"混乱"が見えるものになる
②苦手の見える化 弱点改善と克服への自信 無駄な時間を減らせた実感
③小タスク分け 継続力と小さな達成感 "やり始めた"ことに喜びを感じられる
④優先順位設定 時間配分力・目標思考 効率よく成果を出す見通しが立つ
⑤ルーティン化 習慣という強さ 親が指示出しなくても始められる安心感
(毎日個別学習Smile) 2025年9月15日 13:18
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ22
「"勉強がつまらない"という言葉は、子どもの心にある好奇心の目覚めを待っているサイン。親が興味の火種に寄り添い、小さな学びに"面白さ"を灯すことが、習慣とモチベーションの扉を開きます。」
1⃣ なぜ「勉強がつまらない」と感じるのか?
1.理解・喜び・興味の欠如が三大原因
勉強がつまらないと感じる要因は、主に「わからない」「喜びを感じない」「興味がない」の三つに集約されます。理解に乏しい教科では苦痛になり、勉強の意義を見いだせなければ意欲も湧きません。また、興味が伴わなければ続ける気になれません。
2.「好きと繋げる学び」が効果的
興味や好きなものと勉強を関連づけることで、没頭感ややる気が自然に芽生えます。例えばゲーム好きなら、プログラミングや文章力に結びつけるといった方法が響くことがあります。
3.学習環境と方法のマンネリ化も原因
同じ場所・同じやり方では飽きやすく、「勉強」という行為自体が苦痛に──という場合もあります。環境や学習スタイルを変えるだけで、新鮮な気持ちで取り組めるようになることがあります。
2⃣ 「つまらない」を「面白い」に変える 5つの親の工夫
① 興味と結ぶ第一歩を共につくる
子どもの「好き」や得意なこと--音楽、ゲーム、絵--と学習を結びつけ、学ぶ意味を見出す導きが重要です。例えば歴史を背景にしたゲーム、自作漫画に使う世界観を勉強で補強するなどの工夫。
② 学習スタイルに"遊び要素"を取り入れる
ゲーム理論や自分ご褒美、友達との問題対決など、楽しい仕掛けを使えば、勉強も"遊び感覚"で取り組むことができ、習慣化しやすくなります。
③ 環境や方法に変化を入れて新鮮さを保つ
リビングのカウンター、自習室、図書館など勉強場所を変えたり、教科ごとにやり方を変えることで集中力と興味が維持されます。
④ 分からないを放置せず"小さな理解"を積み重ねる
疑問点はその日のうちに質問したり調べたりする習慣づけが大切です。「分かった!」という実感が学びに楽しさを与えます。
⑤ 成功体験に価値を置く声かけを続ける
「できたね」が積み重なる環境は、内発的に学び続ける土壌になります。「わかる」→「楽しい」→「続けたい」へのサイクルを支えます。
3⃣ 実践例:勉強がつまらない中1女子の取り組みモデル ステップ 内容 意図
① 興味に結びつける 漫画の世界観を地理で語ってみる 学ぶ意義と楽しさの導入
② 遊び要素導入 10分タイムトライアル+ご褒美アリ 勉強を楽しいゲーム感覚に
③ 環境チェンジ 書斎→リビング→カフェ式自習室 気分転換により集中力アップ
④ わからない対処 分からないときはノートにマーク→翌日先生に質問 理解の積み重ねという実感形成
⑤ 小さな承認を 終わったら「よく頑張ったね」と伝える 自分を認める習慣を育てる
4⃣ 続けることで見える変化と親の安心感
1.親の工夫 子どもに育つ力 親の安心感
2.興味に寄り添う 学びに意義を感じる心 子どもの関心が見える嬉しさ
3.遊び感覚導入 継続への抵抗が少ない気持ち 楽しく続く姿への安心感
4.環境の変化 自己調整力 新しい習慣の芽生えに感動
5.理解を積む習慣 自律的学習力 質問できる安心できる環境づくり
6.承認の言葉 自己肯定と挑戦力 小さな成長を見逃さない喜び
締めの言葉
「"勉強がつまらない"という言葉は、盲点ではなく"心の窓の鍵"です。子どもの内にある好奇心の火を、興味と工夫でそっと灯すことで、学びは自然と面白くなります。親子で"学ぶ楽しさ"をもう一度一緒に築いていきましょう。」 つまらなさは、視点や接し方を変えるきっかけです。親子の"学びの再接続"に、ぜひ今日から少しずつ取り組んでみませんか?
1⃣ なぜ「勉強がつまらない」と感じるのか?
1.理解・喜び・興味の欠如が三大原因
勉強がつまらないと感じる要因は、主に「わからない」「喜びを感じない」「興味がない」の三つに集約されます。理解に乏しい教科では苦痛になり、勉強の意義を見いだせなければ意欲も湧きません。また、興味が伴わなければ続ける気になれません。
2.「好きと繋げる学び」が効果的
興味や好きなものと勉強を関連づけることで、没頭感ややる気が自然に芽生えます。例えばゲーム好きなら、プログラミングや文章力に結びつけるといった方法が響くことがあります。
3.学習環境と方法のマンネリ化も原因
同じ場所・同じやり方では飽きやすく、「勉強」という行為自体が苦痛に──という場合もあります。環境や学習スタイルを変えるだけで、新鮮な気持ちで取り組めるようになることがあります。
2⃣ 「つまらない」を「面白い」に変える 5つの親の工夫
① 興味と結ぶ第一歩を共につくる
子どもの「好き」や得意なこと--音楽、ゲーム、絵--と学習を結びつけ、学ぶ意味を見出す導きが重要です。例えば歴史を背景にしたゲーム、自作漫画に使う世界観を勉強で補強するなどの工夫。
② 学習スタイルに"遊び要素"を取り入れる
ゲーム理論や自分ご褒美、友達との問題対決など、楽しい仕掛けを使えば、勉強も"遊び感覚"で取り組むことができ、習慣化しやすくなります。
③ 環境や方法に変化を入れて新鮮さを保つ
リビングのカウンター、自習室、図書館など勉強場所を変えたり、教科ごとにやり方を変えることで集中力と興味が維持されます。
④ 分からないを放置せず"小さな理解"を積み重ねる
疑問点はその日のうちに質問したり調べたりする習慣づけが大切です。「分かった!」という実感が学びに楽しさを与えます。
⑤ 成功体験に価値を置く声かけを続ける
「できたね」が積み重なる環境は、内発的に学び続ける土壌になります。「わかる」→「楽しい」→「続けたい」へのサイクルを支えます。
3⃣ 実践例:勉強がつまらない中1女子の取り組みモデル ステップ 内容 意図
① 興味に結びつける 漫画の世界観を地理で語ってみる 学ぶ意義と楽しさの導入
② 遊び要素導入 10分タイムトライアル+ご褒美アリ 勉強を楽しいゲーム感覚に
③ 環境チェンジ 書斎→リビング→カフェ式自習室 気分転換により集中力アップ
④ わからない対処 分からないときはノートにマーク→翌日先生に質問 理解の積み重ねという実感形成
⑤ 小さな承認を 終わったら「よく頑張ったね」と伝える 自分を認める習慣を育てる
4⃣ 続けることで見える変化と親の安心感
1.親の工夫 子どもに育つ力 親の安心感
2.興味に寄り添う 学びに意義を感じる心 子どもの関心が見える嬉しさ
3.遊び感覚導入 継続への抵抗が少ない気持ち 楽しく続く姿への安心感
4.環境の変化 自己調整力 新しい習慣の芽生えに感動
5.理解を積む習慣 自律的学習力 質問できる安心できる環境づくり
6.承認の言葉 自己肯定と挑戦力 小さな成長を見逃さない喜び
締めの言葉
「"勉強がつまらない"という言葉は、盲点ではなく"心の窓の鍵"です。子どもの内にある好奇心の火を、興味と工夫でそっと灯すことで、学びは自然と面白くなります。親子で"学ぶ楽しさ"をもう一度一緒に築いていきましょう。」 つまらなさは、視点や接し方を変えるきっかけです。親子の"学びの再接続"に、ぜひ今日から少しずつ取り組んでみませんか?
(毎日個別学習Smile) 2025年9月 8日 11:43
三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ21
「親に反抗する子どもは、"自立への足音"を立て始めている証。親が関わりをコントロールから共感へシフトすることができれば、その足音は"対等な対話の歩み"に変わります。」
1. なぜ「親が関わると反抗される」のか?
①思春期の脳は批判や命令に"シャットダウン"反応を起こしやすい
親の助言を「自分への攻撃」と受け止めてしまい、言葉が耳に入らなくなります。この時期に大切なのは命令ではなく、共感と受容です。
②「反抗=自立の芽生え」と理解する視点が必要
精神科医の佐々木正美氏らは、思春期の反抗には「自立しようとする健全な反抗」と「危険な反抗」があると指摘し、前者は成長の証として温かく受け止めるべきだと語ります。
③過干渉は余計に心を閉じさせることがある
親の過度な介入や期待、怒りは、子どもの心理的自衛反応を引き出し、自立を妨げるリスクがあります。冷静な見守りが有効です。
2. 「関わりが反発を呼ばない」ための5つのポイント
① 共感の一言から始める
「今日は疲れてるよね」「やっぱり大変だったね」と感情に共鳴すると、心が自然に柔らぎ、言葉が入りやすくなります。
② 対話の入口は一緒に選ぶ形式で
「話したい?それとも一緒に何かしながら?」と選ばせることで、"聞かされる"ではなく"選ぶ関係"を育てられます。
③ 命令ではなく提案や協議で関わる
「~しなさい」ではなく、「~どう思う?」という問いかけで、意思決定への関与を促しましょう。
④ 小さな成果でも丁寧に認める
「そこの動き、すごく気づいたよ」「話を聞いてくれて嬉しいな」と承認を重ねることで、自信と信頼が育ちます。
⑤ 親自身も冷却時間を持ち、"見守る姿勢"を意識する
心がモヤモヤしたら、一呼吸おく。見守ること自体が信頼のベースになります。
3. 実践例:言えば言うほど反抗される中2男子の対応モデル ステップ 親の対応例 子どもの反応・変化
① 共感スタート 「学校、疲れてるよね」 怒りの前に「分かってくれてる」を感じる
② 選ばせる入口 「一緒に話す?それとも本読んでる?」 自分で「話したい」と選ぶ安心感
③ 提案型の関わり 「数学勉強、一緒にやる?」 善意が重荷にならず、自然な協力へ
④ 承認の習慣 「やってみた勇気、すごいね」 失敗が怖くなくなり、再チャレンジの意欲へ
⑤ 冷却時間を持つ 感情的になりそうなら、一旦離れる 冷静さが戻り、言葉が届きやすくなる
4. 続けることで育つ家庭と子どもの成長
①親の姿勢 子どもに育つ力 親が得られる安心
②共感から始まる対話 心を開く力 会話のきっかけが増える安心感
③自ら思考させる選択 自律と主体性 指示しない関係へ一歩進む安心
④提案型の関わり 自分で判断する意識 指示しなくても進む姿への期待感
⑤承認を積み重ねる 自己肯定と挑戦意欲 小さな前進に喜びを感じられる
⑥見守る姿勢 自立した成長 心の余裕と信頼の安心感
締めの言葉
「親が関わったことで反抗されると『関わることすら怖い』と感じるかもしれません。でも、その反抗は『自分を認めてほしい』というサイン。共感と選択、見守る姿勢を少しずつ重ねることで、親子関係は"命令"から"対話"へと変わっていきます。新しい始まりに向け、親子でそのドアをひらいていきましょう。」 反抗は疎外ではなく、成長への扉です。共感と対話で、その向こう側にある"自立へのステップ"を一緒に築いていきませんか?
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
1. なぜ「親が関わると反抗される」のか?
①思春期の脳は批判や命令に"シャットダウン"反応を起こしやすい
親の助言を「自分への攻撃」と受け止めてしまい、言葉が耳に入らなくなります。この時期に大切なのは命令ではなく、共感と受容です。
②「反抗=自立の芽生え」と理解する視点が必要
精神科医の佐々木正美氏らは、思春期の反抗には「自立しようとする健全な反抗」と「危険な反抗」があると指摘し、前者は成長の証として温かく受け止めるべきだと語ります。
③過干渉は余計に心を閉じさせることがある
親の過度な介入や期待、怒りは、子どもの心理的自衛反応を引き出し、自立を妨げるリスクがあります。冷静な見守りが有効です。
2. 「関わりが反発を呼ばない」ための5つのポイント
① 共感の一言から始める
「今日は疲れてるよね」「やっぱり大変だったね」と感情に共鳴すると、心が自然に柔らぎ、言葉が入りやすくなります。
② 対話の入口は一緒に選ぶ形式で
「話したい?それとも一緒に何かしながら?」と選ばせることで、"聞かされる"ではなく"選ぶ関係"を育てられます。
③ 命令ではなく提案や協議で関わる
「~しなさい」ではなく、「~どう思う?」という問いかけで、意思決定への関与を促しましょう。
④ 小さな成果でも丁寧に認める
「そこの動き、すごく気づいたよ」「話を聞いてくれて嬉しいな」と承認を重ねることで、自信と信頼が育ちます。
⑤ 親自身も冷却時間を持ち、"見守る姿勢"を意識する
心がモヤモヤしたら、一呼吸おく。見守ること自体が信頼のベースになります。
3. 実践例:言えば言うほど反抗される中2男子の対応モデル ステップ 親の対応例 子どもの反応・変化
① 共感スタート 「学校、疲れてるよね」 怒りの前に「分かってくれてる」を感じる
② 選ばせる入口 「一緒に話す?それとも本読んでる?」 自分で「話したい」と選ぶ安心感
③ 提案型の関わり 「数学勉強、一緒にやる?」 善意が重荷にならず、自然な協力へ
④ 承認の習慣 「やってみた勇気、すごいね」 失敗が怖くなくなり、再チャレンジの意欲へ
⑤ 冷却時間を持つ 感情的になりそうなら、一旦離れる 冷静さが戻り、言葉が届きやすくなる
4. 続けることで育つ家庭と子どもの成長
①親の姿勢 子どもに育つ力 親が得られる安心
②共感から始まる対話 心を開く力 会話のきっかけが増える安心感
③自ら思考させる選択 自律と主体性 指示しない関係へ一歩進む安心
④提案型の関わり 自分で判断する意識 指示しなくても進む姿への期待感
⑤承認を積み重ねる 自己肯定と挑戦意欲 小さな前進に喜びを感じられる
⑥見守る姿勢 自立した成長 心の余裕と信頼の安心感
締めの言葉
「親が関わったことで反抗されると『関わることすら怖い』と感じるかもしれません。でも、その反抗は『自分を認めてほしい』というサイン。共感と選択、見守る姿勢を少しずつ重ねることで、親子関係は"命令"から"対話"へと変わっていきます。新しい始まりに向け、親子でそのドアをひらいていきましょう。」 反抗は疎外ではなく、成長への扉です。共感と対話で、その向こう側にある"自立へのステップ"を一緒に築いていきませんか?
\今すぐ無料体験のお申込みが可能です!/ お子さまの学習に不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。 LINEで簡単!質問・申込・ご相談もすべてOK! LINEで体験申込今のうちに学習の「つまずき」を解消し、前向きなステップへ! お問い合わせ | 三重県四日市市、川越町の学習塾|毎日個別学習Smile(スマイル)
(毎日個別学習Smile) 2025年9月 1日 13:06
1
« 2025年8月 | メインページ | アーカイブ | 2025年10月 »