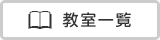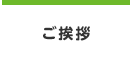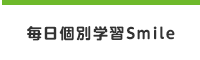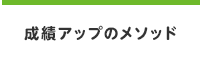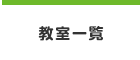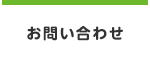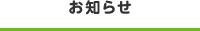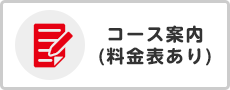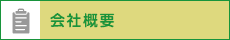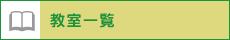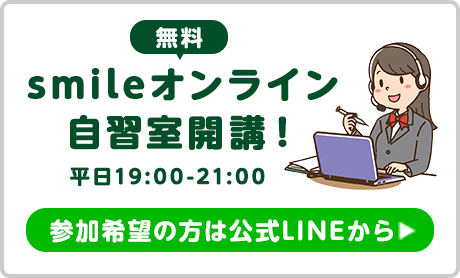月別 アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (14)
- 2025年7月 (30)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
HOME > スクールブログ > アーカイブ > 2025年5月 > 2ページ目
スクールブログ 2025年5月 2ページ目
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ130
忙しい親が抱える「子どもの勉強を見られない」悩み
現代の多くの親は、仕事や家事、その他の責任に追われ、子どもの勉強を直接見てあげる時間が取れないことに悩んでいます。特に小学生の子どもを持つ親にとって、学習の基礎を築くこの時期に関わりを持てないことは、大きな不安となります。
しかし、親が直接勉強を見てあげることだけが、子どもの学びを支える方法ではありません。限られた時間の中でも、子どもの学習意欲を高め、自己学習を促す工夫は可能です。
忙しくてもできる、子どもの学びを支える方法
1. 短時間でも質の高いコミュニケーションを
毎日5分でも、子どもと向き合う時間を持ちましょう。「今日学校で何を学んだの?」「どんなことが楽しかった?」など、子どもの話に耳を傾けることで、学びへの関心を示すことができます。このような対話は、子どもの自己肯定感を高め、学習意欲の向上につながります。
2. 学習環境を整える
子どもが自分で学習に取り組めるよう、静かで集中できる環境を整えましょう。学習机の周りを整理し、必要な教材を揃えることで、子どもは自立して勉強に取り組みやすくなります。
3. 学習計画を一緒に立てる
週末など時間が取れるときに、子どもと一緒に学習計画を立てましょう。「この日は宿題を終わらせよう」「この時間は読書の時間にしよう」など、具体的なスケジュールを決めることで、子どもは自分で学習を進める習慣を身につけます。
4. 学習の成果を共有する
子どもが勉強した内容や成果を、親に報告する時間を設けましょう。「今日はこんな問題が解けたよ」「この本を読んだよ」など、子どもが自分の学びを共有することで、達成感を感じ、次の学習への意欲が湧きます。
忙しい親でもできる、学びを支える具体例
例1:朝の5分間を活用
出勤前の5分間、子どもと一緒に朝食をとりながら、今日の予定や学習内容について話す時間を持つ。「今日は何の授業があるの?」「宿題は終わったかな?」など、簡単な会話でも、子どもは親の関心を感じ、安心します。
例2:学習記録ノートの活用
子どもに学習記録ノートをつけさせ、親が帰宅後に目を通す習慣をつける。「今日の勉強内容」「できたこと」「わからなかったこと」などを記録し、親がコメントを書くことで、子どもは自分の学びを振り返り、親とのつながりを感じます。
例3:週末の学習タイム
週末の30分間を「親子学習タイム」として設定し、一緒に勉強する時間を持つ。親が子どもの勉強を見たり、同じ空間で読書をしたりすることで、学習へのモチベーションが高まります。
忙しい親が子どもの学びを支える可能性 親が忙しくても、子どもの学びを支えることは十分可能です。大切なのは、時間の長さではなく、関わりの質です。短い時間でも、子どもに関心を持ち、愛情を伝えることで、子どもは安心し、自立した学習者へと成長します。 また、親が忙しい姿を見せること自体が、子どもにとっては「努力する姿勢」の手本となります。
親の働く姿勢や自己管理の様子を見て、子どもは学びの大切さや時間の使い方を自然と学んでいきます。
結びに
忙しさの中で子どもの勉強を見られないことに悩む親御さんへ。
あなたの愛情と関心は、短い時間でも子どもの心に深く届きます。日々の小さな関わりが、子どもの学びを支え、未来への力となります。 「忙しくて見られない」と悩むのではなく、「忙しい中でもできることは何か」を考え、実践していきましょう。その積み重ねが、子どもの学びを豊かに育てるのです。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月21日 13:25
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ129
はじめに:連絡帳が伝えきれない「学校のリアル」
小学生の子どもを持つ親御さんの多くが、学校からの連絡帳を読んでも、実際の子どもの学校生活の様子がわからず、不安や戸惑いを感じています。連絡帳は、学校と家庭をつなぐ大切なツールですが、その内容だけでは子どもの全てを把握することは難しいのが現実です。
連絡帳には、授業の進度や宿題、行事の予定などが記載されていますが、子どもの感情や人間関係、学習への取り組み姿勢など、日々の細かな変化までは伝えきれません。
そのため、親御さんは「本当に学校でうまくやっているのだろうか」「友達と仲良くしているのか」など、さまざまな疑問や不安を抱えてしまうのです。
なぜ連絡帳だけでは実態がつかめないのか?
1. 情報の限界
連絡帳は、限られたスペースに必要な情報を簡潔に記載する必要があります。そのため、詳細な説明や子どもの様子について深く触れることが難しく、親御さんが知りたい情報が不足してしまうことがあります。
2. 教師の多忙
教師は多くの業務を抱えており、全ての保護者に対して個別に詳細な連絡を取ることが難しい状況です。そのため、連絡帳の内容が形式的になりがちで、子どもの個別の状況が伝わりにくくなっています。
3. 子どもの自己表現の難しさ
子ども自身が連絡帳に記入する場合、自分の感情や出来事をうまく表現できないことがあります。そのため、親御さんが連絡帳を読んでも、子どもの本当の気持ちや状況が伝わらないことがあります。
連絡帳の行間を読むための方法
1. 子どもとの対話を大切にする
連絡帳の内容について、子どもと一緒に確認しながら話をすることで、子どもの学校での様子や気持ちを知る手がかりになります。「今日はどんなことがあったの?」「この宿題、難しかった?」など、具体的な質問をすることで、子どもも話しやすくなります。
2. 教師とのコミュニケーションを図る
必要に応じて、教師に直接連絡を取り、子どもの学校での様子について尋ねることも重要です。連絡帳だけでなく、電話や面談などを通じて、子どもの状況を詳しく知ることができます。
3. 子どもの行動や態度を観察する
家庭での子どもの様子から、学校での状況を推測することも可能です。例えば、帰宅後に元気がない、宿題に取り組む様子が変わったなど、些細な変化にも注意を払いましょう。
実践例:連絡帳を活用した親子のコミュニケーション 背景:
小学4年生のA君の母親は、連絡帳の内容が簡潔すぎて、学校でのA君の様子がわからず、不安を感じていました。
対応策: 子どもとの対話:
毎日、連絡帳を一緒に確認しながら、A君に学校での出来事を尋ねるようにしました。
教師との連絡:
月に一度、教師にメールでA君の様子を尋ねるようにしました。
家庭での観察:
A君の帰宅後の様子や宿題への取り組み方を注意深く観察し、変化があればA君に声をかけるようにしました。
結果:
A君は母親との会話を通じて、自分の気持ちを話すようになり、母親もA君の学校での様子を把握できるようになりました。また、教師との連絡を通じて、A君の学習状況や友人関係についても知ることができ、不安が軽減されました。
連絡帳を超えた子どもの理解の可能性 連絡帳は、学校と家庭をつなぐ大切なツールですが、それだけでは子どもの全てを把握することはできません。親御さんが子どもとの対話や教師とのコミュニケーションを大切にし、家庭での観察を通じて子どもの様子を理解することで、子どもの成長をより深く見守ることができます。
結びの言葉
連絡帳は、子どもの学校生活を知るための一つの手段に過ぎません。親御さんが子どもとの対話を大切にし、教師との連絡を積極的に行い、家庭での様子を観察することで、子どもの本当の姿を理解することができます。子どもの成長を見守るために、連絡帳の行間に込められたメッセージを読み解く力を養いましょう。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月20日 13:55
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ128
他の子と比べてしまう親御さんへ:その背景と対応策
小学生のお子さんを持つ親御さんの中には、他の子どもと自分の子どもを比べてしまい、不安や焦りを感じる方も少なくありません。しかし、子ども一人ひとりには個性や成長のペースがあり、他人と比較することが必ずしも適切ではないことを理解することが大切です。
他の子と比較してしまう背景
1. 情報過多の時代 SNSやインターネットの普及により、他の家庭の子どもの様子や成績などの情報が容易に入手できるようになりました。これにより、無意識のうちに自分の子どもと他の子どもを比較してしまうことがあります。
2. 教育への関心の高まり 教育熱心な親御さんが増え、子どもの成績や学力に対する関心が高まっています。その結果、他の子どもと比較して自分の子どもの学力に不安を感じることがあります。
比較から解放されるための方法
1. 子どもの個性を尊重する 子ども一人ひとりには得意なことや興味関心が異なります。他の子どもと比較するのではなく、自分の子どもの個性や興味を尊重し、伸ばすことが大切です。
2. 成長の過程を見守る 子どもの成長は一朝一夕にはいきません。短期的な成果に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で子どもの成長を見守ることが重要です。
3. 親自身の心のケア 親御さん自身が他人と比較することから解放されることも大切です。自分自身の価値観や考え方を見直し、他人と比較しない生き方を心がけましょう。
実践例:小学3年生のケース 背景:
小学3年生のA君の母親は、同級生のB君が塾に通い、成績が良いことを知り、自分の子どもと比較して不安を感じていました。
対応策: 子どもの興味を尊重:
A君が興味を持っていた科学実験に注目し、自宅で簡単な実験を一緒に行うことで、学習への興味を引き出しました。
成長の過程を見守る:
短期的な成績ではなく、A君の学習意欲や取り組む姿勢の変化に注目し、成長を感じるようにしました。
結果:
A君は学習への興味を持ち、自主的に勉強に取り組むようになりました。母親も他の子どもと比較することなく、A君の成長を喜ぶようになりました。
他の子と比べない子育ての可能性
他の子どもと比較することなく、子どもの個性や成長を尊重することで、子どもは自信を持ち、自らの力で成長していくことができます。また、親子の関係もより良好になり、家庭全体が明るく前向きな雰囲気になります。
結びの言葉
子どもは比べるものではなく、育てるものです。他の子どもと比較するのではなく、昨日のわが子と今日のわが子を比べ、その成長を喜びましょう。親の温かいまなざしが、子どもの未来を明るく照らします。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月19日 12:37
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ127
通知表の評価に悩む親御さんへ:その背景と対応策
小学生のお子さんの通知表の評価が気になると、多くの親御さんが不安を抱えるものです。しかし、通知表の評価は単なる数字ではなく、子どもの成長や学びの過程を示すものです。重要なのは、その評価の背景を正しく理解し、適切な対応をすることです。
通知表の評価が下がる主な原因
1. 授業態度の変化 授業中の態度が評価に影響を与えることがあります。例えば、先生の話を聞かずに友達と話したり、授業に集中できていなかったりすると、評価が下がる可能性があります。
2. 提出物の遅れや未提出 宿題や課題の提出が遅れたり、未提出だったりすると、評価に影響を与えることがあります。提出物は、学習の理解度や意欲を示す重要な要素とされています。
3. 忘れ物の多さ 授業に必要な教材や道具を忘れることが多いと、授業への準備不足と見なされ、評価が下がることがあります。
評価を上げるための具体的な方法
1. 授業態度の改善
授業中は先生の話をしっかり聞き、積極的に参加する姿勢を持つことが大切です。わからないことがあれば質問するなど、積極的な姿勢が評価につながります。
2. 提出物の管理
宿題や課題の提出期限を守るために、カレンダーや手帳を活用してスケジュール管理を行いましょう。親子で確認する習慣をつけると、忘れ防止にもなります。
3. 忘れ物の防止
前日の夜に翌日の持ち物を確認する習慣をつけましょう。チェックリストを作成するのも効果的です。
実践例:小学4年生のケース背景:
小学4年生のCさんは、前学期より通知表の評価が下がり、親御さんが心配されていました。特に、授業態度や提出物に関する評価が低下していました。
対応策: 授業態度の改善:
先生の話をしっかり聞き、わからないことは質問するように指導。
提出物の管理:親子で宿題のスケジュールを確認し、提出期限を守るようにサポート。
忘れ物の防止:前日の夜に持ち物を確認するチェックリストを作成。
結果:次の学期には、授業態度や提出物に関する評価が改善され、通知表の評価も向上しました。
通知表は成長の記録通知表の評価は、子どもの学びや成長の過程を示すものです。数字だけにとらわれず、子どもの日々の努力や変化に目を向けましょう。親のサポートが、子どもの成長を支える大きな力となります。
結びの言葉
通知表は、子どもの成長を映す鏡です。数字に一喜一憂せず、心の変化に耳を傾け、共に歩んでいきましょう。親の温かいまなざしが、子どもの未来を明るく照らします。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月18日 11:57
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ126
成績低下に悩む親御さんへ:その背景と対応策
小学生のお子さんの成績が下がってきたと感じると、多くの親御さんが不安を抱えるものです。しかし、成績の変動は成長過程でよくあることであり、必ずしも悪い兆候ではありません。重要なのは、その原因を正しく理解し、適切な対応をすることです。
成績低下の主な原因
1. 学習内容の難化
学年が上がるにつれて、学習内容が難しくなり、理解が追いつかなくなることがあります。特に算数や国語では、基礎がしっかりしていないと、応用問題でつまずくことが多いです。
2. 学習習慣の乱れ
生活リズムの乱れや、学習時間の減少も成績低下の要因となります。特に、ゲームやスマートフォンの使用時間が増えると、集中力が低下しやすくなります。
3. 自己肯定感の低下
成績が下がることで自信を失い、さらに学習意欲が低下するという悪循環に陥ることがあります。親の過度な期待や比較も、プレッシャーとなることがあります。
成績回復のための具体的な方法
1. 基礎の見直し
成績が下がった教科や単元を特定し、基礎から復習することが重要です。例えば、算数であれば、計算の基本に戻って練習を重ねることで、応用問題への対応力が養われます。
2. 学習計画の立て直し
無理のない学習計画を立て、毎日の学習習慣を整えることが大切です。短時間でも集中して取り組むことで、効率的な学習が可能となります。 3. ポジティブな声かけ
子どもの努力や成果を認め、励ますことで、自己肯定感を高めることができます。「頑張っているね」「少しずつできるようになってきたね」といった声かけが効果的です。
4. 学習環境の整備
静かで集中できる学習環境を整えることも重要です。テレビやスマートフォンの音が入らない場所で学習することで、集中力が向上します。
実践例:小学5年生のケース背景:
小学5年生のB君は、4年生までは成績が良好でしたが、5年生になってから成績が下がり始めました。特に算数の応用問題でつまずくことが多くなりました。
対応策: 基礎の見直し:
計算の基本に戻り、毎日10分間の計算練習を実施。
学習計画の立て直し:
1日30分の学習時間を確保し、週末には復習の時間を設ける。
ポジティブな声かけ:
「今日はよく頑張ったね」「少しずつできるようになってきたね」と励ます。
学習環境の整備:
静かな部屋で学習し、スマートフォンは別の部屋に置く。
結果:
3ヶ月後、B君の成績は徐々に回復し、再び自信を持って学習に取り組むようになりました。
成績低下は成長のチャンス成績が下がることは、子どもが成長する過程でよくあることです。
大切なのは、その原因を理解し、適切な対応をすることです。親が子どもを信じ、共に乗り越えることで、子どもは再び自信を取り戻し、成績も回復していきます。
結びの言葉
成績の波は、子どもの成長の証です。焦らず、見守り、共に乗り越えていきましょう。親のサポートが、子どもの未来を明るく照らします。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月17日 12:43
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ125
小学生の「勉強に対する自信がない」悩みの背景
小学生の子どもが勉強に対して自信を持てないことは、多くの親御さんが直面する共通の悩みです。この自信の欠如には、以下のような要因が考えられます
成功体験の不足:
達成感を味わう機会が少ないと、自信を持ちにくくなります。
学習内容の難易度の不一致:
難しすぎる、または簡単すぎる課題は、興味を失わせる原因となります。
目標設定の不明確さ:
具体的な目標がないと、学習の目的を見失いがちです。
生活リズムの乱れ:
睡眠不足や不規則な生活は、集中力や意欲の低下を招きます。
自信を育むための具体的な方法
1. 小さな成功体験を積み重ねる 簡単な問題から始めて、徐々に難易度を上げていくことで、自信とやる気を育てます。例えば、100マス計算や漢字の書き取りなど、達成感を得やすい課題から取り組むと効果的です。
2. 具体的で達成可能な目標を設定する 「今日は漢字を3つ覚える」「計算ドリルを1ページ解く」など、具体的で現実的な目標を立てることで、達成感を得やすくなります。
3. 学習内容を子どものレベルに合わせる 学習内容が難しすぎたり簡単すぎたりすると、やる気を失う原因になります。子どもの理解度に合わせた教材や課題を選ぶことが重要です。
4. 学習環境を整える 勉強する場所や時間を工夫することで、集中力を高めることができます。例えば、静かな場所でお気に入りの文房具を使う、勉強前にリラックスする音楽を聴くなどの工夫が効果的です。
5. 生活リズムを整える 十分な睡眠やバランスの取れた食事、適度な運動は、集中力や意欲の向上に寄与します。生活習慣を見直すことで、学習への前向きな姿勢を育てることができます。
実践例:
小学4年生のケース背景:
小学4年生のA君は、宿題に取り組む意欲が低く、親が促してもなかなか動きません。
対策:
目標設定:
「今日は漢字を3つ覚える」という具体的な目標を設定。
成功体験の積み重ね:
簡単な問題から始めて、徐々に難易度を上げる。
学習環境の工夫:
お気に入りの文房具を使い、静かな場所で勉強する。
生活リズムの見直し:
就寝時間を早め、十分な睡眠を確保。
結果:A君は、毎日の小さな目標を達成することで自信をつけ、勉強に対する意欲が向上しました。
可能性と展望子どもの勉強に対する自信は、親の関わり方や環境の工夫によって大きく変わります。小さな成功体験を積み重ねることで、自信とやる気を育て、将来的な学習意欲の向上につながります。
結びの言葉
子どもの自信は、待つものではなく、育てるものです。親が適切にサポートし、環境を整えることで、子どもは自ら学ぶ意欲を持つようになります。小さな一歩から始めて、共に成長していきましょう。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月16日 13:56
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ124
小学生の「勉強のモチベーションが低い」悩みの背景
小学生の子どもが勉強に対してやる気を持てないことは、多くの親御さんが直面する共通の悩みです。
このモチベーションの低下には、以下のような要因が考えられます:
成功体験の不足:
達成感を味わう機会が少ないと、勉強への意欲が湧きにくくなります。
学習内容の難易度の不一致:
難しすぎる、または簡単すぎる課題は、興味を失わせる原因となります。
目標設定の不明確さ:
具体的な目標がないと、学習の目的を見失いがちです。
生活リズムの乱れ:
睡眠不足や不規則な生活は、集中力や意欲の低下を招きます。
モチベーションを高めるための具体的な方法
1. 小さな成功体験を積み重ねる
簡単な問題から始めて、徐々に難易度を上げていくことで、自信とやる気を育てます。例えば、100マス計算や漢字の書き取りなど、達成感を得やすい課題から取り組むと効果的です。
2. 具体的で達成可能な目標を設定する
「今日は漢字を3つ覚える」「計算ドリルを1ページ解く」など、具体的で現実的な目標を立てることで、達成感を得やすくなります。
3. 学習内容を子どものレベルに合わせる
学習内容が難しすぎたり簡単すぎたりすると、やる気を失う原因になります。子どもの理解度に合わせた教材や課題を選ぶことが重要です。
4. 学習環境を整える
勉強する場所や時間を工夫することで、集中力を高めることができます。例えば、静かな場所でお気に入りの文房具を使う、勉強前にリラックスする音楽を聴くなどの工夫が効果的です。
5. 生活リズムを整える
十分な睡眠やバランスの取れた食事、適度な運動は、集中力や意欲の向上に寄与します。生活習慣を見直すことで、学習への前向きな姿勢を育てることができます。
実践例:
小学4年生のケース背景:小学4年生のA君は、宿題に取り組む意欲が低く、親が促してもなかなか動きません。
対策:
目標設定:
「今日は漢字を3つ覚える」という具体的な目標を設定。
成功体験の積み重ね:
簡単な問題から始めて、徐々に難易度を上げる。
学習環境の工夫:
お気に入りの文房具を使い、静かな場所で勉強する。
生活リズムの見直し:
就寝時間を早め、十分な睡眠を確保。
結果:
A君は、毎日の小さな目標を達成することで自信をつけ、勉強に対する意欲が向上しました。 可能性と展望子どもの勉強に対するモチベーションは、親の関わり方や環境の工夫によって大きく変わります。
小さな成功体験を積み重ねることで、自信とやる気を育て、将来的な学習意欲の向上につながります。
結びの言葉
子どものやる気は、待つものではなく、育てるものです。親が適切にサポートし、環境を整えることで、子どもは自ら学ぶ意欲を持つようになります。小さな一歩から始めて、共に成長していきましょう。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月15日 14:20
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ123
親御さんの悩み
「習い事が多くて、宿題をする時間がない」
「勉強と習い事、どちらを優先すべきか分からない」
「子どもが疲れていて、勉強に集中できない」
両立が難しい理由
時間の制約:
習い事のスケジュールが勉強時間を圧迫し、十分な学習時間を確保できない。
疲労の蓄積:
習い事で体力を消耗し、帰宅後の勉強に集中できない。
優先順位の混乱:
習い事と勉強のどちらを優先すべきか、親子で意見が分かれる。
解決策と方法
1. 週間スケジュールの作成
子どもの生活リズムに合わせた1週間のスケジュールを作成し、習い事と勉強の時間をバランスよく配置します。これにより、無理のない計画的な生活が可能になります。
2. 習い事の見直し
習い事の数や頻度を見直し、必要に応じて優先順位をつけます。特に、小学5年生以降は勉強の難易度が上がるため、習い事を1~2つに絞ることが推奨されます。
3. 学習と習い事の連携
習い事の前後に短時間の勉強時間を設けることで、学習習慣を維持します。例えば、習い事の前に15分間の復習時間を設けるなど、無理のない範囲で学習を取り入れます。
4. 家族の協力体制の構築
家族全体で子どものスケジュールを共有し、協力してサポートします。例えば、兄弟姉妹がいる場合は、上の子が下の子の勉強を見てあげるなど、家庭内での協力体制を整えます。
具体例ケーススタディ:
小学4年生のA君 状況: 週に3回のサッカー練習と、週に2回のピアノレッスンに通っており、勉強時間が確保できていない。
問題点: 宿題が終わらない日が続き、成績が低下。
対策:
習い事のスケジュールを見直し、ピアノレッスンを週1回に減らす。 サッカー練習の前に30分間の勉強時間を設ける。 家族で週間スケジュールを共有し、協力してサポート。
結果:
勉強時間が確保され、成績が向上。習い事も継続でき、バランスの取れた生活を実現。両立の可能性勉強と習い事の両立は、計画的なスケジュール管理と家族の協力により、十分に可能です。子どもの成長に合わせて柔軟に対応し、無理のない範囲でバランスを取ることが重要です。
結びの言葉
「習い事で得た経験は、勉強にも活かされる。バランスの取れた生活が、子どもの未来を豊かにする。」 子どもの可能性を最大限に引き出すために、勉強と習い事の両立を目指しましょう。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月14日 12:35
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ122
「また朝起きられなかった...」「学校に遅刻しそうって、いつも慌ててる」「夜はゲームや動画ばかりで...」 そんな毎日に、あなたは心配と苛立ちを感じていませんか? それは当然のことです。 夜遅くまで起きている子どもは、体も脳も回復できていない状態で1日を始めなければなりません。すると、集中力は落ち、感情のコントロールも難しくなり、結果として勉強の習慣化や学校生活にも悪影響を及ぼしていきます。 でも大切なのは、「今の習慣を責めること」ではなく、「新しい生活習慣を一緒に作ること」です。
子どもの睡眠リズムを整えることは、単なる健康管理ではなく、「未来の学力・人間力への投資」なのです。 なぜ夜遅くまで起きると問題なのか?
理由は3つあります:
成長ホルモンの妨げになる
22時〜2時の間は「成長ホルモン」がもっとも分泌される時間帯。この時間に寝ていないと、身長だけでなく脳の発達や記憶の整理にも影響が出てしまいます。
脳の記憶定着が妨げられる
睡眠中、子どもの脳は学習した内容を"整理・記憶"しています。寝る時間が遅いと、この記憶の定着が不十分になり、学習効率が下がります。 朝のリズムが崩れると1日が崩れる
朝、すっきり起きられない→朝食をとれない→学校で集中できない→自信を失う...という悪循環に入ってしまうこともあります。
解決の方法とステップ では、どのようにして夜型の生活を見直し、朝型に整えていけばよいのでしょうか?
以下に現実的な方法をご紹介します。
1. 「夜の30分ルール」を始めてみる いきなり21時就寝は難しいもの。そこでまずは「今より30分早く布団に入る」ことから始めてみましょう。 たとえば、就寝が23時なら22時半に。慣れてきたらさらに前倒ししていきます。
2. 「朝型アクション」でご褒美をつくる 朝起きたときに楽しみがあると、起きる理由になります。 例: 起きたら好きな音楽を流す 特別な朝ごはん(小さなお菓子など) 親子の5分間ゲームタイム(トランプやじゃんけん)
3. 「ブルーライトカット」で自然な眠気を促す 夜にスマホやゲームを見ていると、ブルーライトの影響で脳が「今は昼だ」と勘違いしてしまいます。 就寝の1時間前からは以下をおすすめします: 部屋の照明を暗めにする デバイスはオフかナイトモードに 紙の本を読む or 絵日記を書く 4. 「家庭全体のリズムを整える」 子どもだけに早寝を求めるのではなく、家族全体で21時半〜22時には静かになる時間を作ると、子どもは自然と眠くなります。
5. 「記録と承認」で継続力を育てる 起床時間、就寝時間を記録し、それを親子で「見える化」するとモチベーションが上がります。 「今日は7時に起きられたね!すごい!」と声をかけることで、子どもは"できた体験"を積み重ねていきます。
具体例:小5男子・ゲーム好きのケース 夜11時までSwitchをしていたAくん。翌朝はなかなか起きられず、学校ではぼーっとしていることが多く、成績も下降気味でした。
そこで保護者が実践したのは以下の4ステップ:
① ゲームは20時までと約束(タイマーを使って見える化)
② 21時以降は「家族で静かに過ごす」時間に
③ 起きられたらカレンダーにシールを貼って"見える達成"
④ 朝ごはんに「好きなフルーツを1つ選べる」制度を導入 3週間後には、自分からゲームを切り上げて布団に入るようになり、朝も6時半にはすっきり起きられるように。 成績も少しずつ回復し、家庭内の会話も増えたとのことです。
未来への可能性:
睡眠と学力の黄金バランス
睡眠を味方につけることは、学力・集中力・体力・情緒安定、すべての土台を整えることにつながります。 特に小学生期は、「親が生活リズムを一緒に整えてあげる」ことが可能な貴重な時期です。 夜更かしに悩む今この瞬間こそ、未来の土台を整えるチャンスです。 焦らず、怒らず、あきらめず。少しずつの積み重ねが、子どもを「朝の光の中で学べる子」に変えていきます。
結びの言葉 「よく眠ることは、よく学ぶこと。今日の夜が、明日の未来をつくる。」
(毎日個別学習Smile) 2025年5月13日 12:31
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ121
はじめに:ゲームに夢中な子どもに悩む親御さんへ
「うちの子、ゲームばかりで勉強しない」「注意してもやめないし、つい叱ってしまう」----そんな悩みを抱える親御さんは少なくありません。しかし、ゲームを一方的に悪者と捉えるのではなく、子どもの興味や特性を理解し、上手に付き合っていくことが大切です。
ゲームに夢中になる理由
子どもがゲームに夢中になる背景には、いくつかの要因があります。
達成感と報酬
ゲームは、クリアすることで達成感を得られ、次のステージへの意欲が湧きます。この「報酬系」が、子どもの脳を刺激し、夢中にさせるのです。
ゲームとの上手な付き合い方
1. ルールを一緒に決める
ゲームの時間や内容について、親子で話し合い、ルールを決めましょう。子ども自身が納得し、自ら守る意識を持つことが大切です。
2. ゲームの内容を理解する
子どもがどんなゲームをしているのか、内容や特徴を理解しましょう。一緒にプレイすることで、子どもの興味や考え方を知ることができます。 3. 他の楽しみを見つける
ゲーム以外にも、子どもが興味を持てる活動を一緒に探しましょう。スポーツや読書、工作など、多様な体験が子どもの世界を広げます。
4. ゲームを学習に活用する
近年、ゲームの要素を取り入れた学習法「ゲーミフィケーション」が注目されています。ゲーム感覚で学べる教材やアプリを活用することで、学習への意欲を高めることができます。
ファンタジー 具体例:
ゲームを学習に活かしたケース ある家庭では、子どもがゲームに夢中で勉強に手がつかないことに悩んでいました。そこで、ゲームの要素を取り入れた学習アプリを導入し、学習時間をゲーム感覚で楽しめるように工夫しました。また、学習の進捗に応じてご褒美を設定することで、モチベーションを維持しました。
この取り組みにより、子どもは学習への興味を持ち、ゲームとのバランスも取れるようになりました。 ゲームとの付き合い方がもたらす可能性 ゲームを通じて、子どもは問題解決能力や創造力、協調性など、さまざまなスキルを身につけることができます。
また、親子でゲームを楽しむことで、コミュニケーションが深まり、信頼関係が築かれます。ゲームを上手に活用することで、子どもの可能性は大きく広がるのです。
まとめ
子どもがゲームに夢中になることは、決して悪いことではありません。大切なのは、親が子どもの興味や特性を理解し、ゲームとの上手な付き合い方を見つけることです。ルールを決め、学習に活用し、他の楽しみを見つけることで、ゲームは子どもの成長を支える強力なツールとなります。 オンライン・タブレット教材は家庭学習のすらら 親子で協力し、ゲームを味方に変えることで、子どもの未来はより豊かで可能性に満ちたものになるでしょう。
(毎日個別学習Smile) 2025年5月12日 13:28