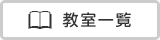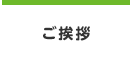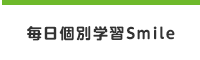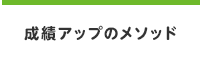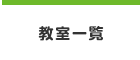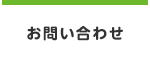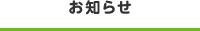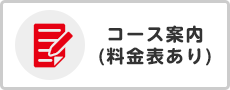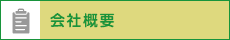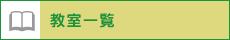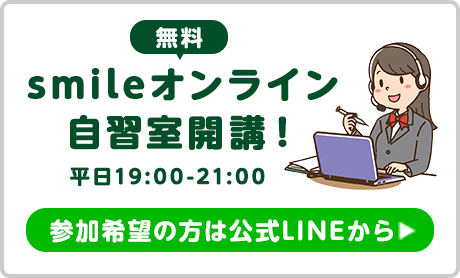月別 アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (14)
- 2025年7月 (30)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
HOME > スクールブログ > 小学2年生から塾を探す親が増えている理由とは?
スクールブログ
< あなたの塾、大丈夫?現場でよくある教え方ミス10選 〜通知表レベル別の指導と、集団塾・アルバイト講師の落とし穴〜 | 一覧へ戻る | 三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ29 >
小学2年生から塾を探す親が増えている理由とは?
最近、「小学校2年生のうちから塾を考えています」というご相談が増えています。
以前は「小5の壁」と呼ばれ、小学校高学年になってから学習塾に通うケースが主流でした。
しかし、今では"その壁が3年前倒し"になりつつあるのが現実です。
なぜ今、小学2年生の段階で塾を探す家庭が増えているのでしょうか?
その背景には、教育の変化だけでなく、保護者の価値観や社会のスピード感の変化が深く関わっています。
1.「小3の壁」以前に気づく保護者が増えた
これまでよく言われてきた「小5の壁」とは、 ・授業スピードが一気に上がる ・抽象的な思考が求められる ・算数の文章題や割合、国語の読解が難しくなる などによって「急に成績が下がる」「やる気がなくなる」という現象を指していました。 しかし、近年では「小3の壁」という言葉が注目され始めています。 これは、小3で「勉強のやり方」や「自分で考える力」がまだ身についていないと、その先の学年で急に苦戦するというものです。 実際、小2の段階で次のような変化に気づく親御さんが増えています。 学校の宿題を"ただこなすだけ"になっている 教科書の内容を説明しようとすると「わからない」と言う 音読はできても意味を理解していない 計算ミスが増えてきた 家での学習習慣がつかない つまり、小2のうちに気づいた親ほど早く動く時代になったのです。
2.「低学年のうちに習慣をつけないと続かない」という実感
子どもが小学生のうちは、「まだ早い」「そのうちやる気になる」と思いたくなるのが親心。 しかし、多くの家庭が上の子や周囲の事例を見て実感しています。 「5年生になってから始めようとしたら、もう手遅れだった」 「勉強のやり方そのものが身についていなかった」 「ゲームや動画の誘惑に勝てなくなった」 こうした経験を耳にしたり、身近なママ友から聞いたりして、 「低学年のうちに生活リズムと勉強習慣をつけることが大事」 という意識が広がっています。 とくに最近は、AI教材やオンライン学習が普及し、「勉強=自分で管理する時代」になりました。 つまり、勉強ができる子より自分で学べる子を育てる必要があるのです。 その基礎をつくるのに最も適しているのが、小学2年生前後なのです。
3.学校教育の変化 ― 「考える力」重視へ
文部科学省の学習指導要領改訂によって、学校教育は大きく変化しています。 いまの小学生は、単に知識を覚えるだけでなく「なぜそうなるか」「自分の考えを言葉で説明する」ことが求められています。 たとえば算数の文章題では、 「りんごが3個あります。2個買い足しました。合計はいくつですか?」 という単純な問題から、 「りんごとみかんを合わせて◯個買いました。りんごはみかんより◯個多いです。 りんごはいくつ買いましたか?」 のように、文章を読み取って式を立てる"思考型"問題が増えています。 こうした問題に慣れていない子は、「読む力」「考える力」「整理する力」が必要になります。 つまり、「考える習慣」をつけるのが早ければ早いほど、学力の土台が安定するというわけです。
4. 親の不安の正体 ― 「つまずきが早く見える化」される時代
最近の保護者は、学校や家庭だけでなくSNS・AI教材など、さまざまな情報から子どもの理解度を"数値化"して把握できるようになりました。 アプリで進捗が見える、 テスト結果がすぐにデータ化される、 オンライン面談で学習分析が共有される。 こうした環境によって、 「うちの子、思ったより理解していないかも...」 と早い段階で気づけるようになったのです。 そのため、以前なら「小5になってからでいい」と思っていた家庭も、 小2の時点でつまずきのサインを見逃したくないと感じて動き出しているのです。
5. 「中学受験」や「AI時代」を見据えた早期意識
中学受験をする・しないにかかわらず、 最近の家庭では「将来を見据えて早めに基礎力を」と考える方が増えています。 特にSNS上で「中学受験は小3から本格スタート」といった情報が広まり、 「うちも小2のうちに下地を作っておこう」と動くご家庭が増加。 また、AI時代に突入し、「暗記より思考力」「点数より主体性」という価値観も浸透してきました。 保護者世代自身が"詰め込み教育"の限界を感じてきたため、 「子どもには"考えられる力"を」 という思いが強くなっているのです。
6.学校外での学びに"安心感"を求める家庭が増えている
コロナ禍を経て、学校と家庭の距離感が変わりました。 登校の制限やオンライン授業を経験したことで、 「学校だけに任せるのは不安」 という意識が広がったのです。 特に低学年のうちは、 ・先生の人事異動で授業の質が変わる ・クラス全体で進むため個別対応が難しい ・家庭でフォローしきれない など、学校だけでは対応しづらい面があります。 だからこそ、「学校以外に安心して相談できる場所を」 と考える家庭が、早期から塾を探すようになっています。
まとめ:これからの塾選びは「早く・無理なく・続けられる」が鍵
小2からの問い合わせが増えている背景には、 単なる"早期教育ブーム"ではなく、 「子どものペースで、無理なく学習習慣を身につけたい」 という親の切実な願いがあります。 勉強ができる・できないよりも、 ・自分から机に向かう習慣 ・失敗してもやり直せる力 ・考えることを楽しむ姿勢 これらを育てるには、実は「小学2年生前後」が最も伸びやすい時期です。
最後に、毎日個別学習Smileでは、 小2のお子さんでも安心して学べるよう、 一人ひとりのペースに合わせた"学習の入り口"づくりを大切にしています。 「まだ早いかな?」と思っても、実際に体験すると 「ここから始めておいてよかった」と感じるご家庭が多いのが特徴です。 もし今、お子さんの学び方に少しでも不安を感じているなら、 "学びの習慣づくり"を一緒に始めるタイミングかもしれません。
3か月体験コース紹介動画はこちら
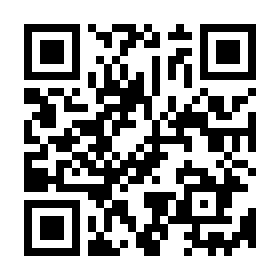
(毎日個別学習Smile) 2025年10月22日 14:39
< あなたの塾、大丈夫?現場でよくある教え方ミス10選 〜通知表レベル別の指導と、集団塾・アルバイト講師の落とし穴〜 | 一覧へ戻る | 三重県四日市市・三重郡川越町の今日も頑張る中学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ29 >