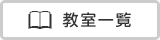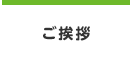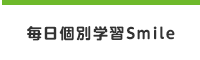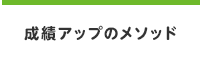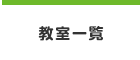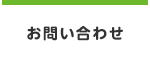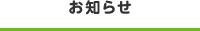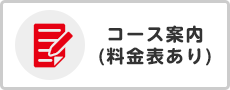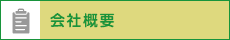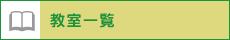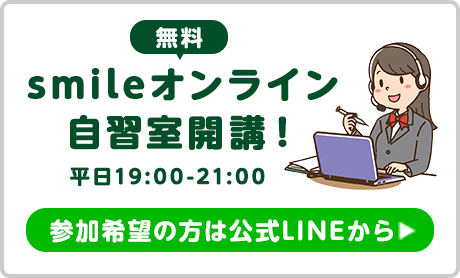月別 アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (14)
- 2025年7月 (30)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (32)
- 2025年4月 (29)
- 2025年3月 (32)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (19)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2022年10月 (7)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (10)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (3)
- 2016年4月 (1)
HOME > スクールブログ > 今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ151
スクールブログ
< 今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ150 | 一覧へ戻る | 今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ152 >
今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ151
なぜ「宿題の意味がわからない」という親が増えているのか?
教育トレンドの変化と疑問 2025年、教育現場では「子どもが学ぶ意味を実感できる宿題」への見直しが進んでいますが、まだ多くの宿題が「やらせればいい」という一括式。どうしても親の側も「なぜ、これを?」と疑問を感じてしまうことが増えています。「宿題って意味ある?」という子どもの言葉 学齢期になると「宿題って意味ある?」と問いかけられることが増え、そのたび大人も答えに困ってしまう...そんな親の不安が大きくなっているのです。
親自身が教育方針に迷いを抱えている DXやAI時代を背景に「宿題は本当に必要?」「量より質?」という議論が教育界で起きており、親の視点にも「宿題不要論」が影響を与えています。
親ができる5つのステップ
意味を見つめ直す
ステップ①:宿題の目的を親子で確認する 宿題は「授業内容の定着」「復習」「学習習慣の定着」が主目的です 親も子も理解することで、「やらせばいい」から「なぜ必要か」に気づくことができます。
ステップ②:「宿題の意味ってなんだろうね?」と一緒に考える 子どもと「どうして宿題あるのかな?」と問い合い、対話を重ねましょう。「意味が分からない」という問い自体を大切にし、ともに向き合うことで学びが深まります
ステップ③:小さな体験から「意味」を実感させる 「1日で70%忘れる」エビングハウスの忘却曲線を踏まえて、学校で習ったことをすぐ宿題で復習する意味を子どもと体験し、「やると覚えやすい」という実感を持たせましょう
ステップ④:親も横で学ぶ姿を見せる 「ママも今英語を勉強してるよ」「パパも今日読書記録をつけるんだ」と自分も一緒に学ぶ姿を見せることで、宿題=誰もがする大切な行動だと示すことができます
ステップ⑤:意味ない?と感じる宿題には手を加える 内容が古くて意味が感じられない宿題には、「先生に聞いてみよう」「アレンジしてみてもいい?」と子どもと一緒に考えてみる。主体性が芽生え、意味が見えてきます。
実践!親子で進める具体例 シーン
算数の宿題に取り組むときステップ
やり方 ① 目的を再確認 「これは授業で習ったことを復習する問題だね」
② 一緒に問い合う 「どうしてこの問題がここに入ってるんだろう?」
③ 意味を体験 「この問題をやると、わかった気がする?」と実感させる
④ 親も学ぶ姿を見せる 横で読んでいる本や勉強方法を共有
⑤ アレンジ提案 「この問題に絵を描いてみたらどうかな?」
結果:子ども自身が「やる理由」を見つけ、取り組む姿勢が明確になります。
意味を見つめ直すことで得られる可能性学習習慣の自立 →「やる理由」が見えるから自分で動く習慣が生まれます。 親子の対話が増える →宿題をきっかけにお互いの思考や価値観を共有する時間が増え、信頼関係が深まります。 質の高い学びに進化 →覚えるためだけの宿題ではなく、「考える」「工夫する」宿題に意味づけがなされ、学びの質が向上します。
締めの言葉
「親も子も『宿題ってなんで必要?』と問い続けること自体が、教育への最初の一歩。問いから始まる学びは、深く強い価値となります。」 「宿題の意味がわからない」という問いは、不安ではありません。それは、より良い教育を目指すための"問い直し"です。親子で問い合い、ともに答えを見つけるそのプロセス自体が、学びの質を高め、親子の関係を豊かにします。 今日から問いを共有し、学びの意味を日々の宿題へとつなげていきましょう。 この取り組みを続ければ、宿題は「形式的な義務」から「意味深い学び」へと変わり、未来への基盤となるでしょう。
3か月体験コース紹介動画はこちら
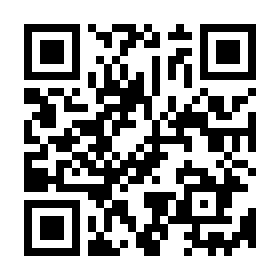
(毎日個別学習Smile) 2025年6月11日 14:48
< 今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ150 | 一覧へ戻る | 今日も頑張る小学生のお子様を持つお父さん、お母さんへ152 >